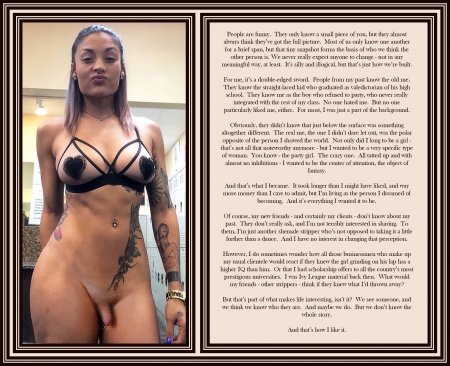
68 Pieces 「断片」
世間の人たちって、笑える。ほとんどみんな、他人の小さな断片しか知らないくせに、全体像を知ってるように思ってる。たいていの人は、他の人のことを短期間しか知っていないはずなのに、そんな小さい断片的なスナップショットで、その人がどんな人間と思うかの根拠にしてしまう。人々がそんな状態から変わるだろうなんて、少なくとも、意味がある形で人々が変わるだろうなんて、あたしたちは真面目にそう思ってはいない。バカで非論理的。だけど、人間はそういうふうにできている。
あたしにとって、このことは両刃の刃。あたしの過去の人たちが知ってるのは、昔のあたし。彼らが知ってるのは、卒業生代表として高校を卒業した真面目な若者。パーティに参加するのを嫌がり、クラスの他の者たちに本当の意味では馴染んではいなかった若者。誰もあたしを毛嫌いしたりしなかったけれど、特にあたしを好きだった人も誰もいない。大半の人たちにとって、私はただの背景の一部にすぎなかった。
はっきり言えることとして、彼らは、その表面のすぐ下に、何かまったく異なるものが隠れていたことを知らなかった。本当のあたし。決して表に出そうとしなかった真のあたし。その本当のあたしは、あたしが世間に見せていた人物の正反対の人物だった。今や、別に特記することでも何でもないことだけど、あたしは女になりたかった。そればかりか、あたしは、非常に特別なタイプの女性になりたいと思っていた。そう、パーティ好きの女の子に。しかも、クレージーなパーティ・ガールに。全身にタトゥーを彫って、全然気にしない女。みんなの注目の的、みんなのイヤラシイ妄想の対象になりたいと思っていた。
そして、あたしはその通りの人間になった。望んでいたより時間がかかったし、使ってもいいと思ったよりもずっとおカネがかかったけれど、でも、今、あたしは、なりたいと夢見ていた人間として生活している。まさにあたしが望んだすべてを叶えて生きている。
もちろん、あたしの新しい友人たちは、あたしの過去について知らない。ましてや、あたしのお客さんたちは、絶対に知らない。と言うか、みんな実際、あたしの過去について訊いたりしないし、あたしも特に話したいとも思っていないのだ。彼らにとって、あたしは、ただのありきたりなシーメールのストリッパーにすぎない。ダンスよりちょっと進んだのことも拒絶しないストリッパー。そして、あたしは、そういう見方をされることを変えるつもりはまったくない。
でも、時々、あたしは、どうだろうと思うことがある。あたしの常連となっているビジネスマンたちが、自分たちの膝の上に乗って股間をグリグリ擦りつけている女の子は、実は、自分たちよりも高いIQを持ってると知ったら、どんな反応をするだろうと。その女の子が、アメリカ中の複数の超有名大学から奨学金を申し込まれた人だと知ったら、どんな反応をするだろう? 当時、あたしはアイビー・リーグに入れる素材だった。今のあたしの友人たち、つまり他のストリッパーたちだけど、彼女たちが、あたしはその申し出を放り投げてきたと知ったら、どう思うだろう?
でも、それこそ、人生を興味深くするもののひとつじゃない? あたしたちは誰かを見て、そして、その人はどういう人物か分かったと思い込む。実際、分かるときもあるかもしれない。でも、実際は、その人の全人生まで分かっていはいないものなのだ。あたしを見て、あたしのことが分かった気になる? さあ、どうかしらね。
そして、まさに、そういう点が、あたしは好き。

68_Permanent 「恒久的」
「おはようございます、ケイト様」 あたしはお辞儀をしながら可愛らしく頬む。そして、体を起こして続けた。「朝食はあと10分ほどでご用意ができます。それまでの間、何かできることはございませんか?」
これが通常の朝の挨拶である。この半年間、毎朝、私はこれを繰り返してきたので、彼女がどう返事するかも知っていた。それでも、ベッドから起き上がる彼女にしっかりと注意を払った。眠りから覚め、目をこすり、そして私に目を向ける彼女。彼女が私の態度を吟味するのを感じる。でも、私はすべて完璧だと分かっている。黒と白の制服は、正確にあるべき姿で整っているはず。
「それ、脱ぎなさい」と彼女は言った。
私はためらわない。「はい、ケイト様」 そして、すぐに背中に手を回し、ドレスのチャックを降ろす。以前は時間がかかったけれど、今はそんなに手間取ることはない。ケイト様のメイドになってから、私は実に多くのことに慣れるようになった。2分ほどで、私の制服は綺麗に畳まれ、彼女のベッドに置かれ、そして、私は裸でその脇に立っていた。
ケイト様はじっと私を見据えた。表情が読み取れなかった。何か調べるような目で見据えられ、私は文字通り体を震わせていた。何か欠点を探しているのだろうか? それとも、単に私の体を目で堪能しているだけなのだろうか? 私には分からなかった。ただ、どちらの場合にせよ、彼女は失望しないだろうと分かる。私は自分の外見に充分すぎるほど手入れすることを学んできたのだから。
どのくらい時間が経ったか、ようやく彼女は反応した。溜息だった。「もう、これには飽きてきたわね。あなた、もうクビ!」
それまで取りすましていた私の仮面が壊れた。「クビ? 私をクビになんて、できるはずがないわ」と呟いた。
「もちろん、できるわよ。でも、心配しないで。あなたは自立するでしょう。あなたのような可愛い子はいつでも仕事を見つけることができるものなの。それに、私も輝かんばかりの推薦状を書いてあげるから」
私は打ちひしがれた。最も予想していなかったこと、それが、彼女が私をクビにすること。状況を見れば、そんなことができる可能性すら考えもしなかった。
「分かりました」 私はがっくり力が抜けて、肩を落とした。計画通り、丸1年続けるところまでは到達できなかった一方、昔の自分の生活に戻る準備をするなど、思ってもいなかった。「お医者様に予約を取ります。そうすれば元の状態に戻れるでしょう。こういうモノも取り除きます。そして……」
「何の話しをしてるの?」 と彼女は私を遮った。
「元の夫と妻の関係に戻ること。ずっと前からそういう計画だったから。つまり、丸1年は続けられなかったけれど……」
彼女は声に出して笑い出し、私は口ごもった。「夫と妻? お願いよ。そんなのありえない」
「じゃ、じゃあ、何の話しを?」
「私があなたを再び男性として見ることができるなんて、本気で思ってるの? このようなことを続けてきて?」
「でも私は男性なのです」 自分の口から間抜けな言葉が出ていると思いつつも、言い張った。「私はあなた様の夫なのです」
「確かにね。確かにかつてはそうだったかも。でも今は? 身分証明書にはイサベラ・ラモスってあるんじゃない? あなたに関係した人たちには、ジャック・レインは『自分探し』にチベットに行ったことになってるわ。2週間もすれば、死体が発見されて、ジャックの死体だと認定されるでしょうね。世の中の人たちにとって、あなたは、ただの違法移民のラテン系メイドにすぎないのよ」
頭の中がぐるぐるしていた。彼女は正しい。彼女は細かな点を見逃すとか、間違いを犯すようなタイプの人間ではない。彼女が私の昔のアイデンティティは消失したと言ったら、間違いなく、そうなっているのである。それを思い、私は大変困った状況になったと知った。
「お願いです。ど、どうか、そんなことはなさらないでください」
「もう決めたことよ。今日かぎりで、ここを出て行きなさい」
「でも、どこに行ったら?」
「そんなこと知らないわね。これはすべてあなたが思いついたこと。覚えているでしょ? あなたはロールプレイが大好きな人だった。まあ、そのロールプレイが恒久的なものだったと考えてみればいいんじゃない? セクシーなメイドとして1年だけ、ということじゃなかったと。そう思ったら、あなたみたいな人にとって、すごくワクワクすることじゃないの? さあ、朝食はどうなったの? あなたは、まだ、もう数時間は時間通りに働かなきゃダメなのよ。そういうふうに振る舞ってほしいわね」
「かしこまりました、ケイト様」 どう反応してよいか分からず、反射的にそう言っていた。私は、そそくさと、散らばった服をかき集め、仕事へと戻った。
