The First Day of your New Life 「新しい人生の最初の日」
「本当に準備はいいの? もう二日くらい先に延ばしても恥ずかしいことじゃないのよ?」
「もちろん、準備なんかできてないよ。どうしたってムリ。でも、たった二日で今の状態が変わるわけない。だから、先延ばしする理由がないんだ。むしろ早く片付けてしまった方がいいよ」
「あなた、今度のことを全部、間違って見てるわよ」
「そう? どんなふうに?」
「ジェス、今日は、あなたの新しい人生の最初の日なの。これからは、あなたに会う人は誰でも、あなたのことを美しい女性として見ることになるの。あなたはワクワクして喜ぶべきだわ。ナーバスになるのは確か。不安になるのも確実。でも、『片付けてしまう』ような状況ではないのよ」
「もし、僕が本当にトランスジェンダーだったら、そういうのももっともだし、良いことなんだろうけど、でも、君も僕も、僕がトランスジェンダーじゃないのは分かってるだろ?」
「あなたのカルテにはそうは書いてないわ」
「だって、君が僕の体を……」
「それは済んだことよ、ジェス。そして、変えることができないことでもあるの。だから、それを受け入れて、前を見て、新しい人生に漕ぎ出すべきだわ。そうじゃなきゃ、取り戻せない昔の生活にいつまでもしがみついて、気がくるってしまうことになるわよ」
「君のせいでね」
「議論しようとすればできるわよ。あたしがこういうことをしたのはあなたの行動の結果だって。なんだかんだ言っても、あなたが浮気したんだから」
「してないって! 千回は言ったはずだよ。あの女性とは何もなかったって! 彼女はただ……」
「はい、はい……全部、壮大な陰謀のせいなのよね。でも、だからといって、今の時点で何か変わるの? あなたは自分の過ちを認めたわけでしょ? それに、あたしが見るところ、あなたもあの道をもう一度たどりたいとは思っていないようだし。そうじゃない?」
「あ、ああ、そうだけど……」
「じゃあ、話し合う意味がないじゃない。さあ、早く服を着て。さもないと、職場に復帰する初日から遅刻することになってしまうわよ」
Out in the Open 「明るみに」 「分かってたわ!」 予想してなかった、姉の声がした。顔を上げると、バスルームのドアのところに姉が立っていた。両腕を組んで、嫌な笑みを浮かべてる。「分かってたんだから!」
何とかこらえたけど、思わずうめき声が出そうになった。姉がいきなりバスルームに来て、全裸のあたしを見たからではない。あたしはもともとちょっと露出好きなところがあるので、裸を見られても、そんなに気にはならない。裸を見られて、ちょっと嫌な感じはするけど、それでイライラしたりする(参考)ことはないだろう。でも、姉があたしのことを他の人にバラすかもしれないと、ちょっととは言えないほど不安になった。ああ、あたしが姉の元カレと一緒にシャワーを浴びてたことを考えれば、たぶん、その不安感は当たり前すぎる不安だったと思う。
自己弁護させてもらえれば、この事態は、あたしが計画したこととかではない。そんなことはするはずもない。単に、姉とジェームズが別れたすぐ前に、彼があたしの部屋に不意に入ってきて、あたしの秘密の女装趣味を発見したことがきっかけだった。ジェームズは、あたしのことを変な目で見るかと思いきや、むしろすっかり夢中になってしまい、その時を境にして、時々、彼はあたしとベッドを共にするようになったのだった。姉が彼を捨てた後は、一層、そうすることが増えていた。
「ちょ、ちょっと勘違いしないでくれよ」とジェームズはあたしを指さして、「これは全部、彼女のせいなんだ」
「彼女ですって?」と姉は金切り声を上げた。「アレックスは男よ!」
「もはや違うわ……というか、今や、あたしのおっぱいの方が姉さんのより大きいことに気づいてないの?」
それは本当のことだ。あたしは正確には豊満な胸をしてるわけじゃないけど、姉は昔から平らな胸を気にし続けてきていた。1年近くホルモンを摂取してきたこともあり、今はあたしの方がずっと大きくなっていた。もっと言えば、最大限に謙虚に言っても、あたしの方があらゆる点で姉より可愛いと言えると思う。多分そういうわけで、ジェームズは姉よりも、はるかにずっとあたしのことを大好きになったのだろうと思う。
「な、なによ!……このアバズレ!」 姉は叫んだ。「パパとママに言うから待ってなさい! あんたは終わりよ。パパもママもあんたとは縁を切るでしょうよ……そして……そして……うわん!」
姉は、不満の持って行き場をなくしたように両腕を掲げながら飛び出していった。数秒後、玄関ドアがバタンと閉まる音が聞こえた。その音は、姉がアパートから出て行ったことを告げていた。
「ドアのカギを交換しなくちゃ」あたしはそうつぶやき、その後、ジェームズに視線を向けた。「で、本当なの? あなたは、本気で、あの時、屈してしまっただけだったの? 全部、あたしのせいだと?」
ジェームズはおどおどとした笑みを浮かべた。「ああ言うほか思いつかなかったんだよ」
あたしは呆れたと言わんばかりに目を剥いて見せた。「まあどうでもいいわ。で、あたしたちどこまでいってたっけ?」
If you like this kind of stories, please visit Nikki Jenkins' Feminization Station https://thefeminizationstation.com/home/
Two Halves 「分身」
すべてを嫌悪していた。自分自身。自分の状況。否応なく生きている二重生活。僕自身の、僕だけの地獄で、どうやって抜け出られるか、手がかりすらなかった。もちろん誰にもバレていなかった。どうして他の人に知りえただろう。僕は完璧に本当の自分を隠すよう努力していたので、誰一人、より深く僕を観察してみようとすら思わなかったのだ。みんなにとって、僕は、ありふれた平均的な男で、ほかの男たち同様、自分がどこに向かってるのか、どうやったら目的地にたどり着けるのかをぼんやりとしか分からずに、ただとぼとぼと人生を歩んでいる人間にしか見えなかっただろう。
でも、そんな僕の奥にはひとりの女性が潜んでいた。幼い時からずっと、抑圧され否定され続けてきた女の子だ。僕は、こんなやつ、いつかしおれて消えてしまえばいいと願い、ずっと心の奥にしまい込んできた。確かに、しばらくの間は、それでうまくいった。それに、僕の方も周囲のみんなをうまくだます方法を会得していた。だけど、そうやってちょっとだけ自由を獲得すると、あの女は復讐心をもって戻って来るのだった。僕はひとりコンピュータの前に座り、僕の中にいるこの女性を解放してあげることを夢見ながら、よく化粧やウイッグやランジェリーのサイトを見て回った。そして、結局、僕は観念したのだった。結局、彼女を自由にしてあげたのである。
最初は、プライベートの時だけだった。そして、しばらくの間は、それで充分だった。でも、すぐに、彼女を抑えつけるのはできないとはっきりしてきた。彼女はもっと自由になりたがっている。そして僕は、そんな彼女を押しとどめるには、あまりに弱かった。僕が初めて、ためらいつつも女性として外に出たのは、そんな時だった。期待通りのスリリングな経験だった。女性としてパスしなかったのは自分でも分かっている。どうしてパスなんかできよう? その頃の僕は、ただの、女性服を着た男に過ぎなかったのだから。でも、僕は気にしなかった。もっとやってみたかった。だから、それから2年ほど、僕は練習を続けた。自分をできるだけよく見せる方法を学び続けた。それに、これは白状するが、いくらかホルモンの助けにも頼った。自分の女性性を隠す段階はとうに過ぎていた。もはや、女性っぽく振る舞うことを隠すこともなくなっていた。
もちろん、普段の生活では、誰にもバレていない。彼らには、僕は依然として、平均的なありきたりの男のまま。自分の男性性の仮面をかなぐり捨てて、みんなに僕がどれだけ美しい女性になれるかを見せたいと切望している。でも、それはどうでもいい。そんなことはできないのだから。できない理由は数え上げることができないほどある。でも、たとえそうでも、僕自身がフェチ的だと思ってることに他の人を招き入れることは、やめられないでいる。男性でも。女性でも。その中間の人でも。こだわりはない。みんな、僕を外見通りの女性としてだけ見て付き合ってくれている。そして、その点で、僕は自由を感じている。
でも、そんな現在ですら、まだ充分だとは思っていない。僕自身と僕の分身の彼女がひとつになり、全体で一つになりたい必要性を感じている。そうでなければ、気がくるってしまうだろうと。今は、必要だと思ってるこのことを実行するだけの強さが自分にあればいいのにと願うだけ。
To the Victor 「すべては勝者に」
「そんな目で見ないでよ。これは自分で招いたことでしょ? 分かってるはずよ」
「全然、罪悪感を感じていないのか? 僕を無理やりこんなふうにしたくせに……」
「無理やりですって? コーディ、それって強い言葉よ? あたしとしては、あなたに選択肢を提供したと考えたいところね。あなたに選択の余地を与え、そのうえで、あなたは自分にぴったりの選択肢を選んだと」
「選択肢だって? お前が僕に与えたことを選択肢って呼ぶのか? 僕には選択の余地などなかったよ。お前はそれを知っててやったんだ! こうでもしなければ、僕はすべてを失っていた!」
「ちょっと面白い思考実験だと思うけど、こういうのを考えてみて? あなたは、自分の本質部分をあきらめるけど、富と贅沢な生活は保持し続ける。そういうのと、あなたは自分の本来の在り方にしがみついたまま、これまでの血のにじむような労働の果実は手放すことになる、という選択肢。正直、あなたは後者を選ぶと思っていたわ。でも、実際はあなたは前者を選んだ。それを知って、あたしすごく満足したの。だって、かつてのあなたがどういう人間だったかを思うと、その選択って、なお一層、美味しい結果だったと思わない?」
「恨んでやる」
「ずっと前からこうなるのは避けられなかったのよ、コーディ。あなたがあたしに自分のオンナになれと脅迫したときからずっと、あたしとあなたは対立することになってきたの。そして、その戦いで勝利を収めたのがあたしであり、戦利品は勝者のものになるというだけの話。その結果、この素敵な写真撮影になったわけだし、後々、今のあなたについてベールをはがすことになるということ。ほんと、どうなるかしらね? 卓越した独身男性の一人と思われていた人が、実は女性になっていましたって発表されたら、世間はどんなふうに思うかしら?」
「お笑いの的になるだろうさ」
「多分ね。あるいは、ひょっとすると世間からすごく応援してもらえることになるかもしれないわよ。元オリンピック選手のケイトリン・ジェンナー( 参考)みたいに。あんなキモイ人ですら世間に受け入れられるとすると、あなたが受け入れられるチャンスもかなり高いかも。でも、正直に告白すると、その予想、間違っているといいなと思ってるわ。あなたが世間に滅茶苦茶に誹謗中傷されるといいなと思ってるの。みんなにあざ笑われるといいなと。……だって、みんながあなたのこと可愛いとか綺麗とか言ったら、大した懲らしめにならないでしょ? そう思わない?」
「じ、地獄に落ちろ……」
「あら、やだ。まずはあなたからよ、地獄に落ちたのは。これが、あなたにとっての地獄だから。ちょっと可愛らしい形の地獄。これから何年も、何年も、この地獄の中でのたうち回るといいんじゃない?」
Perfect 「完璧」
「お願いだからシャツを着てくれないか? その……君のそれ、気が散ってしょうがないんだ」
「あ、いや、ごめんね。あたしのこのおっぱい、自慢にしていいってメーガンは言ってるんだよ。あなたは、これ、好きじゃないの?」
「え? 当たり前だよ! あ、いや、そんなことないって言うべきか。ああ、もう……俺、この状況に、すごく動転してるんだ。君は、本当に、すべてが今のようになってしまってオーケーなのか? 俺は……」
「オーケーどころか、それ以上だよ。今の状態がすごく気に入ってる。前に比べて、ずいぶんちやほやされるようになってるんだから!」
「で、でも……君は一度も……こういうことが始まる前は、君が……分かるだろ……君が女になるなんて、ほのめかしすらしなかったじゃないか。俺、どうしても、メーガンがキャロルと一緒になれるように、君のことを操って、こういう状態に変えたんじゃないかって思わずにいられないんだ。俺は、君がどんなことであれ、自分自身で望んでないことをさせられたりするのを見てられないんだよ」
「あたしのことをそんなに心配してくれるなんて、本当にやさしいのね。でも、あたしは大丈夫よ。これこそ、あたしが求めていたことなの」
「本当なんだね?」
「そう思ってるけど? ちょっとぼんやりしてる感じはするけど、でも、みんながハッピーになってくれたらいいなと思ってるだけなの。メーガンとキャロルにふたりが愛し合ってると言われたとき、こうなることがベストだなって思えたの。だって、あなたには、してほしいことを何でも喜んでする女性をゲットでき、それと同時にメーガンとキャロルは一緒になることができる。誰も損はしないでしょ?」
「でも君は女性じゃない……」
「今は女性よ。あなたが女性に求めている体の特徴をしっかり備えていると思うわ。キャロルほど可愛いわけじゃないのは分かってる。でも……」
「そんなことないよ! 君は最高だよ。完璧だよ、たとえ……」
「よかった! 本当に良かった。あたし、あなたがあたしを欲しないんじゃないかって、すごく心配していたの……でも今は、できるわね……あたしたちずっと一緒でいられる。あたし、あなたが求めることならどんなことでもしてあげる。あたしにしてほしいことを教えてくれるだけ……それだけでいいのよ」
「俺は……多分、後悔することになるだろうと分かってるんだけど、でも……もう、我慢できないよ。俺と一緒に寝室についてきてくれないか? そして、この状況をはっきりさせることにしよう」
Two Birds 「一石二鳥」
「こんなのとんでもない考えだよ。君もそう思っているんだろ?」
「何? いや思ってないよ。なんでそんなこと言うんだ?」
「こんな考え、狂ってるってことの他に?」
「ドラマのヒロインみたいなこと言うのやめろよ。この手のことはどこにでもあることだよ」
「映画を含めるなら話は別だけど、こんなことそうどこでもあることじゃないよ。それに、映画を含めたって、君が思ってるほど、普通のことじゃないよ。『ミセス・ダウト』( 参考)なんてずいぶん前の映画だし」
「そうか? 『トッツィ』は? 『ビッグママ・ハウス』は? 『プリティ・ダンク』も。いくらでも挙げることができるよ」
「まず第一に、そういう映画は1本を除いて、全部ひどい映画だ。第二に、それと今回のことは全く別の話だということ」
「その通り。だって、実際、お前が自分から進んでやったことだしな。それにしても、お前、本当に最高だよ」
「ここで怒るべきなのか、感謝すべきなのか分からないが、そんなのどうでもいいや。その点に突っ込むつもりはないよ。僕が言いたいのは、そういう映画では、主人公が女装して、ちょっと人づきあいが下手な大学1年生を誘惑しようとしたりしていないという点。その点だけでも、そういう映画とはすごく違うことになるということ」
「俺の弟は人づきあいが下手と言ってるわけ? あいつはただの恥ずかしがり屋なだけだよ! それに、弟には、ちょっとでいいから気がある人がいるかもって示してやるだけでいいって点ではお前も俺も同じ意見だっただろ? あいつはマジで可愛いやつだし……」
「それなら、君のガールフレンドたちに頼めばいいことだって、言ったよね? どんな娘だって僕なんかより適任だと思うのに」
「それについては何千回も言ったよね! 弟は……あいつは……男の娘が好きなんだよ。分かってるだろ? そっちがすごく好きらしいんだ。つか、弟のネットの履歴は全部そればっかり。それに、そういう役割を演じる準備をしたがってるのは、他ならぬお前だろ? カメラの前でトランスジェンダーの女を演じる練習をするのに、現実にそういうのを演じるより良い方法ってあるか? お前はメソッドアクター( 参考)だと思ってたけど?」
「その通り。僕はメソッド役者。つか、今回のことについて僕が用意した筋書きのことを忘れたんじゃないのか? あの食事制限やらエクササイズやら、何もかも……」
「お前も、そういう努力が無駄になってしまうのは嫌だろ? だからさあ、やれよ。これが自分のためになるって分かってるだろ? それに、これをしてくれたら俺は本当に助かるんだ。一石二鳥だよ」
「どうでもいいけど。でも、もし彼が……もし、事態が変な感じに変わったら、僕は抜けるからね。これに関しては、質問はなし、で」
「ああ。分かった。もちろん。必ずそうするから」
あたしに身体を押し付けていた男の人はどんな人なのって思って、よく見たら、割とハンサムな人で、Tシャツとジーンズというシンプルな服装をしてた。胸の前で両腕を組んでいたけど、すごい筋肉の腕で、ちょっと身体を動かしても、筋肉がピクピク動いていた。とても強い印象を与える男性で、身長は軽く180センチを超えると思うし、この人より大きな胸板をしてる男性は、ここには誰もいない。 再びステージに目を向けたら、ベティが満面の笑顔であたしに向かって両手を振っていた。お客さんたちが一斉に振り返って、あたしに目を向けた。知らぬ間に、あたし、この小さなショップにぎゅうぎゅう詰めになっているイヤラシくて、エッチな気分になってる男たちの注目の的になってしまってるじゃないの! すぐに店の外に出たかったけど、あたしの後ろにはさっきのふたり組の大きな男性が立ちふさがっていて、入り口には戻れなかった。身を縮めて隠れたかったけど、ベティがあたしに手を振ってるのに気づいたからか、男たちは、ぞろぞろと動いて場所を開け、ステージへと通じる細い通り道を作ってしまった。スポットライトがあたしを照らす。男たち全員の視線があたしに向けられた。溜息や、口笛が聞こえる。みんな、あたしのことを褒める声。まあ、あたし自身を褒めているというより、この服装のせいでものすごく肌を露出してしまっていることを褒めたたえる声なのは確かだけど。 もう逃げられない。仕方なく、一度、深呼吸をして、作り笑いをし、ベティが立っているステージへ上がった。ベティの後ろに立ってるアダムにも目を向けた。彼は嬉しそうに微笑みながら、あたしのことを見ていた。 「ケイト! 来てくれて本当にうれしいわ」 ベティは興奮した様子でそう言って、あたしをハグした。 「ベティ、あなた、お客さんたちがいるって言ってなかったわよ……しかも、こんなにたくさんいるなんて!」 ベティはうふふと笑って、あの太いバイブを掲げ、あたしにウインクした。 「確かに宣伝はしたけど、本当に短期間だったのよ。だから、あたしもあなたと同じくらい驚いてるの。ケイト、お願い、ちょっとだけ、ここに立って待ってて。この仕事を片付けちゃうから」 ベティはそう囁いて、観客たちの方に向き直った。 「はい、皆さん! 中断しちゃってごめんなさい。さっきお話ししようとしてたことだけど、これを使うときは、本当に少量の潤滑剤しかいらないの。あとの仕事は、ここにいる殿方がおっしゃったように、このバイブが全部してくれるのよ。皆さんの奥さんでも、彼女でも、あるいは彼氏でも、このバイブを使ってあげたら、みんな感謝して皆さんをいっそう愛しく思うようになるはず」 ベティは「彼氏でも」と自分で言いながら、自分で笑っていた。 あたしもちょっと驚いていた。だって、男性があんな太いバイブをお尻に入れるところなんて、想像すらできなかったから。お客さんたちをざっと見てみると、確かにゲイの男性もいるかもしれないと思った。お客さんの大半は30代から40代の男性で、女性も何人かいたけど、その人たちは連れの男性にくっつくようにしていた。ともかく、誰もがあたしたちを見ていたし、もっと言えば、男性の大半はあたしに目を向けていたと思う。 「で、うちが紹介する、次の新製品は、なんと、トニー・ハング( 参考l)のおちんちんの鋳型を使って作ったディルド。本物の複製なのよ……しかも、今日の今の時間から販売開始! ケイト、そこにあるディルド、取ってくれる?」 ベティは、後ろの低いテーブルを指さした。 あたしは何が何だか分からず、ぼーっとしていたけど、ベティはニコニコしながらディルドを渡すように身振りで指示している。いいわよ、分かったわ。合わせてあげるわ。さしずめ、あたしはベティにとってのバンナ・ホワイト( 参考l)ね。 振り向いて、そこにあった低い台を見た。実際はテーブルじゃなかった。なんか、スーツケースを、テーブルクロスみたいなので覆ったようなものが、床に置かれてただけ。ともあれ、そこへ行ったけど、その途端、会場から口笛やため息が聞こえた。あたしの後姿を見ての反応? 思わず体が強張ってしまった。ここにいるたくさんの男たちがあたしのことを見てる!
しばらくたち、ようやく頭がはっきりしてきた。気がつくと、あたしは自分が出したドロドロの中に突っ伏していた。お尻の穴からはウェンディの出したものが垂れ流れ、口の周りはジーナが出したものでベトベトになっていた。 体を起こして、頭を振った。そんなあたしを、ウェンディとジーナはニコニコしながら見ていた。ふたりとも最初は不安だったのだと思う。でも、今はそんな不安状態なんかとっくに乗り越えてるのは明らか。というか、ふたりとも、もっとやりたがってる。あたしは、確かに疲れていたけど、このふたりには、求めていることをしてあげなくちゃ。 「あなたのおかげで、あたし、今はすっきりした気分になってるの……あなたって、すごい名医さんだわ」とウェンディはイタズラっぽい笑みを浮かべた。ウェンディは、あたしが、彼女に話したこと以上のことをしてきたのを知ってるみたいな感じだった。 「あたし、前から、アイデアでいっぱいなの」 するとジーナが「あなた、他のモノでもいっぱいになってるんじゃない? ウェンディのスペルマがお尻の穴から溢れ出てるわよ」と言った。ジーナも、もう、恥ずかしがる様子は消えていた。「それ、舐めてもいい?」 それを聞いてびっくり。一瞬、彼女が何を言ってるのか理解できなかったくらい驚いた。でも、あっという間にジーナは床に仰向けになってあたしの隣に横たわった。ジーナの赤毛の美しい髪にあたしのスペルマがべっとりついている。ジーナは指で自分の口を指してから、あたしの脚を突っついた。彼女が何をしてほしがってるのか、分かる。 仰向けの状態から身体を回してうつ伏せになり、それから両膝を突いて体を起こした。ジーナの方に移動したけど、頑張りすぎたせいで、ふらふらしてる。でも、何とか彼女の顔にまたがった。お尻を向けて。振り返って彼女の顔を見ると、目をキラキラさせながらあたしを見てる。熱くて情熱的な目つき。ジーナは、さっき、おちんちんをしゃぶってもらいたがっていた時も、熱っぽく情熱的な顔をしていたけど、今は、それ以上にあたしのお尻を舐めたがっている様子。 ゆっくりと注意しながらお尻を降ろした。あたしのアヌスのすぼまったお口で彼女の可愛いピンク色の唇にキスをするような感じで触れた。ジーナは、それに応じるようにキスを返し、あたしのすぼまった穴の小さなヒダを唇で擦るようにしていたけど、すぐに口を大きく開けて、吸い始めるのを感じた。最初はためらいがちに、あたしの穴にチュッチュッと軽く吸うようにしてる。でも、すぐにその舌が穴の中に入ってきて、中を探るように動き始めるのを感じた。 「ああん、ジーナ……!」 そう喘ぐと同時に、すぐに手を胸に持って行って、自分でギュッと握った。ジーナの舌がアヌスの中を掻きまわして、出てくるウェンディのスペルマをぴちゃぴちゃ味わってる。さらには唇をすぼめて、強く吸引し始めた。ズルズル音を立てて吸い出して、ごろごろ喉を鳴らして飲み込んでいる。
ふたりいる妻たちのひとりが私たちの顔を見て言った。「ドニーもあたしも、この20年ほどのエンターテインメントが向かって来た方向に、とても心配しているの。子供たちはほとんどの時間、何らかの装置の画面に目を向けて過ごしているように思うから。パソコンの画面とかテレビとかゲームとか。この世代は、何かを行う種族のではなく、何かを見る種族になってきているわ。だから、エミーに、行動の一部に参加できるような方法を考えてって頼んだわけ。その成果が、これなのよ」 それを聞いて、私もジェイクも圧倒された。この技術は、私が知ってる中で、最も目を見張る技術だ。しかも、それを開発したのは7歳の子供たちだとは。隣でジェイクがつぶやくのが聞こえた。「どうやら、このオファー、真剣に検討すべきなようだ……」 エマがスキップしながら部屋に入って来た。その姿を見て、改めて彼女がまだ幼い子供だと思い知らされる。彼女はアンドリューの膝の上に飛び乗って、抱きついた。アンドリューはエマの脇の下をくすぐり、それを受けてエマはキャッキャッと笑い転げた。天才と超天才の間で行われる交歓の行為としては、あまりに家庭的すぎるやり取りに見える。 そのエマがジェイクに言った。 「ねえ、ジェイク? 新しいオペレーティングシステムを発表するとき、あたしたち、それがどれだけ優れているかを証明するコンテストを開催したいと思ってるんだ。みんなが知ってるIPアドレスでシステムを立ち上げるつもり。その上で、そのシステムにハッキングできたら、誰にでも100万ドルをあげるの。地球上のすべてのコンピュータおたくに参加してもらいたいから…… 「……あたしの妹たちもコンピュータおたくで、2年位前に、政府がうちのデータベースに侵入しないようにファイアウォールを作ったわ。で、最後のファイアウォールの後ろにちょっとしたモノを置いておいたの。そこまで突破できた人へのご褒美としてね。でも、誰もできなかった。それに、そもそも、あたしたちのデータベースはそのコンピュータに置いてなかったし…… 「でね、今度のにも同じことを仕掛けておいたわ。だからうちのオペレーティングシステムに侵入できた人は、100万ドルに加えて、コレもゲットするのよ」 そう言って、エマはリモコンのスイッチを押した。突然、画面にドニーとディアドラのほぼ等身大の画像が現れた。互いに抱き合いながら素っ裸で眠っているふたりの画像だった。私は息をのんだし、隣のジェイクも息をのんだ。こんなセクシーなヌード画像は見たことがない。 妻たちのひとりが小さい声ながら叫び声をあげた。「アンドリュー! あなた、この写真は隠しておくって約束したでしょ!」 アンドリューは申し訳なさそうな声を出そうとしたが、少なくとも私やジェイクと同じく画像にじっと見入っていたのには変わりがない。 「ディー・ディー、エマが何かをしたいと思ったら、僕が何をやっても止められないって。君も知ってるだろ? それに、これは優れたアートだよ。僕が撮った中でも最高の作品だよ」 ディアドラとドニーのふたりとも、顔を真っ赤にしていた。でも、私もちょっと応援したい気持ちだった。 「本当に。アンドリューの言う通りですよ。とても美しい写真ですよ。どうかご検討していただきたいのですが、これを『コスモ』誌の編集局に見せるのを許してほしいです。絶対、表紙に使いたいと言うと思いますよ。そうでなくとも、少なくとも私の記事のトップには必ずなります。それほど、目を見張るような素晴らしい画像だもの!」 妻たちはアンドリューを睨み付けていた。一方、アンドリューは無邪気に平然とした顔をしていた。エマのしたことも無邪気なことなら、アンドリューも無邪気な気持ちなのかもしれない。種馬状態のアンドリューだけど、今夜は、珍しく仕事から解放される夜になるんじゃないかしら。 ようやく、妻たちのひとりが子供たちに「もう寝る時間よ」と言った。子供たちは、ちょっとぶつぶつ文句を言ってたけれど、大半が目を擦っていたのも事実。女の子も男の子もそれぞれ寝室のある二階へと上がっていった。ひとりエマを除いて。
今や指は彼女のあそこに完全にハマっている。俺は指の動きを止めた。それでも、彼女の膣の筋肉は収縮を繰り返し、時折、キューっと締め付けてくる。 「それから、俺の兄は何をしたんだ?」 そう訊いて、ミセス・グラフに顔を寄せ、耳たぶを軽く噛んだ。 「彼のアレがすっかり抜けるまでゆっくりと前のめりになったわ。それから優しくあたしを仰向けに寝かせて、彼も両膝をついた。浅瀬だったけどまだ海の中。波に身体を洗われてる中、彼の瞳を見つめた。それだけでもイキそうになっていた。海の音が信じられないほど大きく聞こえていて、裸の身体に風が吹きつけていて、別世界に入ってるような気持だったわ」 ミセス・グラフはそう言いながら周囲を見回し、誰か立ち聞きしていないか確かめた。 「それで?」 俺は指を奥深くに入れたまま、優しく促した。 「彼はそのまま両膝をついてひざまずいたけど、その時の彼、信じられないほど素敵だった。あたしの足元にひざまずく彼の濡れた体が明るい月明りに照らされて輝いていた。あの時ほど、あたしは自分が生きていると実感したことはなかった。あなたのお兄様があたしの両脚を持ち上げて、足にキスを始めた時、あやうく叫び声をあげてしまいそうになったわ。彼、あたしの足の指を1本ずつ口に含んで吸い始めた時のビリビリするような興奮、あんな興奮は初めてだったの。波が何度も何度もあたしたちに寄せてきて、時々、あたしの全身が波に被るときもあった。風は暖かかったけれど、濡れた乳首に風が当たって、乳首は固く、痛いほど敏感になっていた。そんな状態の中、足の指の間に舌を伸ばされ、そこを舐められたら、あそこを触ってもいないのに、あたしはイキ始めたの」 俺の性奴隷は、そう言いながら片手を下げて、俺の腕をつかみ、優しく揉んだ。 「俺の兄に足を舐められ、イキ始めた時、お前は自分の旦那のことを思っていたんじゃないのか?」 俺は、彼女の女陰の中、指を1本くねくねと動かし、訊いた。 「あっ、いいえ」 俺の指からの刺激に、ミセス・グラフは俺の腕をぎゅっと掴み、目を閉じ、喘いだ。 「夫のことはすっかり頭から消えていた。頭の中は、あなたのお兄様に、あたしへの愛の行為をずっと続けていてほしいと、それだけになっていた。信じられないほどエロティックな状況のせいで、あたしの身体は火が付いたようになっていたの。かつてないほどに。あの日の夜のようなことは、もう二度と経験できないと思うわ」 と言いながらミセス・グラフはさらに少しだけ両脚を広げた。 「じゃあ、俺がお前を誘惑し、お前の身体を貪ったあの日の夜は、兄との夜と並べると、たいしたことじゃないと言いたいのか?」 そう訊きながら、指を素早くあそこの中から引き抜いた。 「ち、違うの……そう言いたいんじゃないの……」と彼女は指を抜かれたのを惜しむ顔になった。
2021052701 僕たちが認めている、妻のあの逞しい彼氏で、何が大好きかと言えば、いつも5分前に来るって言ってくるところだ。その連絡を受けたら、それまでしていたことを全部止める。そして、彼はカウチにミシェルを倒して、僕の目の前で彼女を貪る。それが終わったら、僕は彼にありがとうと言い、握手をし、そして彼は帰って行く。彼は本当に寝取られ夫婦の扱い方を心得ているんだよ。  2021052702 「君が妊娠する相手にレイを選んでくれて本当に嬉しいよ。僕はこの赤ちゃんには、素晴らしいお父さんになるって約束するよ」 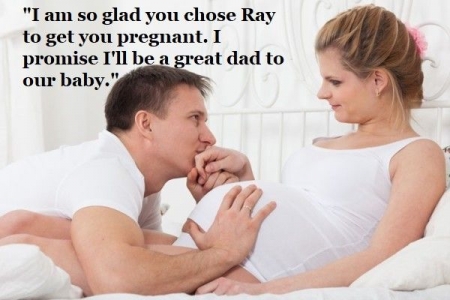 2021052703 「夫にとって屈辱的でしょって? 全然。夫のジョージが、逞しい彼氏のスペルマを喜んで味わってるって素晴らしいことだと思うの」  2021052704 「だいたい20分くらいしたら、僕は妻が僕の小さなちんぽにはまったく目もくれなくなるだろうと悟った」  2021052705 妻と彼女の彼氏のペニス。この写真を撮るのがどれだけ甘美に屈辱的だったことか。  2021052706 「君が家に帰ってきて、僕が君の身体についた彼の味を味わえる時が一番好きだ」 「うーん、もっと強く抱いて。彼のが中から染み出てきてるの」  2021052707 「おはよう、あなた。あら、あたしたちのためにコーヒーを淹れてくれたの? あなたって本当に優しいのね}  2021052708 「あら、あなた」 「そのドレス、新しいの?」 「ええ、今夜の彼とのデートで着るつもりで買って来たの」 「ずいぶん高そうだけど」 「ええ、そうなの。あなたのクレジットカードの決裁書をチェックしておいてね。ともあれ、明日の朝まで、またね」 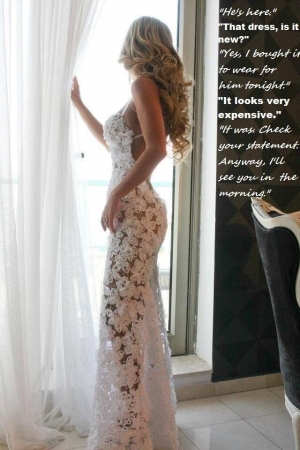 2021052709 「じゃあ、携帯、切らないように。この男を気に入ったら家に連れ帰るから。その時は、あなたに予備の寝室で待機してもらうから」  2021052710 「ちょっといい? これはただのデートなんだから、あなたは何も心配する必要ないのよ」 
「早く入って! 早く!」 コリーンは僕を中に引っ張り込み、ドアに鍵をかけた。中は思ったより広いスペースだった。トイレというより、文字通りの広めのバスルームと言える。妻は裸足でスキップで跳ねるようにして、便器に座ってニヤニヤしているウェイトレスのところに行き、彼女にまたがった。彼女の太ももの上に腰を降ろしながら、ブロンドの髪を鷲づかみにして、唇を重ねた。鼻息も荒々しい長々としたキスだった。 僕は心臓が高鳴っていた。コリーンの大きなバッグを肩に下げたままドアのところに立ち尽くしたまま、何が目の前で起きてるのかと認識できずにいた。本気で、妻がこんなに早くコトを進めるとは予想していなかった。よっぽど切羽詰まった気持ちになっていたのに違いない! ジーンズの前がきつくなってくるのを感じた。 「ぼんやり突っ立ってないで!」と、妻は僕の方を振り返った。例のウェイトレスは、妻の肩の向こうからニコニコしながら射るような視線でこっちを見てる。「ここの床、気持ち悪いでしょ。あなたに、あたしたちのための大きくてセクシーなマットレスになってほしいの」 僕は言い返したりはしなかった。その後に続くと思われる褒美を考えたら、そんなことはわずかな代償だ。加えて、僕は紳士でもある。素早くシャツを脱ぎ、床に敷き、その上に仰向けに横になった。幸い、ここは実に大きなバスルームだ。トイレに加えて、シャワーもあり、着替えるスペースもある。だから、僕のような長身でも楽に横たわることができた。 横たわって顔を上にしていると、コリーンがウェイトレスの腕を取って便器から立たせるのが見えた。その後、妻は手を彼女の後ろ首に当てて、前のめりにさせ、立ったままキスを始めた(コリーンは堂々と仕切るタイプの性格だし、筋肉質の肉体でもあるけれど、身長は155センチくらいしかない。ウェイトレスの方がずっと背が高い)。 コリーンが僕の頭をまたがった。僕の顔の左右に足が来る形だ。これだと、彼女の官能的なキャラメル色のふくらはぎと太ももをしっかりと見ることができる。太くて、見てるだけで涎れが出そうになる肉づきだが、何時間もジムやプールで鍛えてきただけあって、信じられないほど引き締まった脚だ。 しかも、今日はパンティを履いてこなかったようだ。彼女の濃い目の肌色の大きなペニスが僕を見下ろしていた。大きくなっている途中らしい。ゆっくりと固さを獲得し、徐々にドレスの服地を持ち上げていってる。このブロンド髪のウェイトレス、これを知ったらどんな反応を見せるかな? ふたりがピッタリと身体を寄せて抱き合った。コリーンのペニスがさらに大きくなっていく。包皮が剥けて、中からテカテカに輝く半球が顔を出した。ドレスの生地がさらに持ち上がり、テントのようになっていく。 ペニスが鎌首をもたげるのに合わせて、大きな睾丸も前の方に移動した。その陰から姿を見せたのが、褐色に近い色の濡れた唇だ。少し口を開いて、中のピンク色の肌を見せている。この姿、僕は何回見ても飽きることがない! 「あれぇ?!」ウェイトレスが叫んだ。気づいた瞬間だな。「それ、何なの?」 彼女はちょっと引きさがって、視線を下げ、妻の盛り上がったドレスを見た。片方の眉毛だけを持ち上げ、何かあいまいな笑い声をあげた。 「それって……何か……ディルドとか? ええ? マジで? あなた、そういうのを用意してきたってこと!?」 彼女はちょっと気分を害してるようだった。コリーンが、朝食に巨大なストラップオンを持ってくるような厚かましい人なのかもしれないと。 妻は、余裕に満ちた顔で笑った。「ディルドじゃないわよ。ちょっと見てみる?」 普通なら、怒りを感じて立ち去っていくだろうけど、このウェイトレスには、薄地のスカートを通して、太った亀頭の輪郭が見えているはず。それに加えて、生地の下、それがヒクヒク動いてるのも見えているはず。彼女は好奇心から立ち去ることができなくなっていた。 僕は内心、ほくそ笑みながら彼女の様子を見ていた。これまでの経験から、普通、どの女たちもよく似た反応をしてきた。ショックと怖れ。だけど、最終結果も、普通、よく似た結果に終わるものだ、と。 このウェイトレスも自分を抑えきれなくなったようで、いぶかしげな顔をしながら、妻に近づき、下に手を伸ばし、コリーンのドレスをめくり上げた。 「何、これ!」と悲鳴を上げた。「まさか?? どうして??……」 完全勃起した野獣を見つめながら、彼女は言葉にならない言葉をつぶやき続けた。33センチの肉塊が血流でドクンドクンと脈動している。電柱のように直立してるが、根元に向けては、不運な小動物を食べた後の蛇のお腹のようなカーブを描いてる。ウェイトレスはまばたきもしなかった。普通、これは、欲望がショックを凌駕した時に見せる反応だ。この反応を見せたら、その人は、もう、引き返すことはできないことを示す。
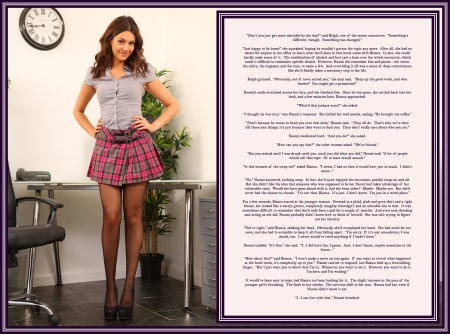 Sissy Secretary 15 「シシー秘書15」 「日ごとに可愛くなっているんじゃない?」と、重役のラルフが声をかけた。「でも、どこか違うなあ。何か変わったような……」 「ただ出張から帰って嬉しいだけよ!」とナオミは、これ以上、この話題を続けないようにと願いながら、わざとキャーキャーした声で答えた。何と言っても、あのホテルの一室でビアンカと何をしたかなど、会社の人に知られたいなどとは思っていなかったから。実際、ナオミ自身、あの出来事はほとんど分からなくなっていた。アルコールと肉欲が相まって、あの出来事の最初から最後までモヤがかかっているような感じで、ひとつひとつの詳しいことを思い出すのが困難になっていた。とは言え、ところどころ覚えている部分は確かにあった。少しだけ挙げれば、ふたりの汗、唾液、オーガズム、それにオモチャなどなど。それに全体を覆う感覚として、深い満足感。自分の人生で必要欠くべからざる大切な1歩をようやく進むことができたといった感じの満足感。 ラルフはにやりと笑った。「どうやら、出張は君には良かったようだね。仕事を頑張り続けるといいよ、そうすれば、どうなるか誰も分からないよ? もしかしたら、昇進できるかもしれないよ!」 ナオミの顔に笑みが広がり、彼女は嬉しい言葉を言ってくれた彼に感謝した。ラルフが出ていった後、彼女は自分のデスクに座って一息ついていたが、何分も経たずにビアンカが近寄って来た。 「あのバカ、何がしたいって言ったの?」 「いいえ、ただ優しくしてくれただけだと思うわ」とナオミはアイスコーヒーを掲げて見せた。「これ、彼からもらったの」 「それは、あなたをそのデスクにうつ伏せにさせたいからよ」とビアンカは言った。「みんな、そうしたがってる。あたしたちは、そのためにここにいるようなものだから。そういう優しい贈り物や言葉は、全部、あなたとエッチしたいため。あなたという人間には、本当のところ、全然興味を持ってないの」 ナオミは驚いて、唾をゴクリと飲んだ。「あなたもなの?」 「どうしてそんなことが言えるの? あたしたち、お友達よ」 「でも、あなたは、あたしが酔っぱらうのを待ってて……そして……あたしにああいうことを……ああいうことのことをレ〇プだという人も多いわ。少なくともセクハラにはなるかと」 「それって、ストラップオンを使ったから? これだけは信じて、あれがあなたにあんなに痛い思いをさせることになるとは知らなかったの。あたしは決して……」 「やめて」とナオミは顔を背けた。実際は、ナオミはビアンカと関係を持ったことも、あのストラップオンの痛みも、何もかも心から楽しんだ。だけど、自分の友人のはずの人が、自分がお酒に酔っていた状態を利用したという事実はどうしても好ましくは思えなかった。しらふだったなら、ビアンカとあの行為をしただろうか? 多分したかも。あるいは、しなかったかも。でも、実際には、自分は、するかしないかを選択できる状態ではなかったのだ。「それじゃないの、ビアンカ。ただ……分からない。いろいろあって、今はちょっと、自分が自分じゃない感じで……」 ビアンカは、何秒か、黙ってナオミを見つめた。ピンクとグレーのプレイド・スカート( 参考)とタイトなブラウスを着たナオミは、やっと成熟期に入ったばかりの、エロさ満点の女子高生にしか見えない。しかも、可愛らしい女子高生。時々、ナオミが女性化してから2か月程度しか経っていないのを思い出すのが難しく感じるほど。その一方で、このように見事に女性化して服装も仕草も完璧である今ですら、おそらくナオミは自分自身をどう考えてよいか分からずにいる。いまだに自分のアイデンティティが何なのかを探ろうとしている最中なのだ。 「あなたの言うとおりだわ」とビアンカは、頭を左右に振った。ビアンカが、自分の立場を過剰に利用してしまったことは明らかだった。あまりにも早く行動に移してしまったのだ。すべてがばらばらに崩れてしまう前に急いで手を打たなければならない。「ごめんなさい、ナオミ。言い訳になるか分からないけど、あたしも酔っていたわ。そうでなかったら、何もしようとしなかったと思う」 ナオミは頷いた。「いいのよ。あたしは……あたしも楽しんだと思うし。それに……よく分からないけど……多分、いつか、何かの時に……」 「こういうのはどう?」とビアンカが言った。「今後、あたしからは二度と、あなたに何かをしようとはしない。でも、ホテルの部屋で起きたことをもう一度してみたいと思ったら、それは完全にあなたに任せることにする」 ナオミが何か返事をしようとしたが、ビアンカは人差し指を口の前に立てて制した。「でも、あたしはいつでもそのつもりだということは知っていてほしいの。いつでも、あなたがしたいと思った時なら。どういう形でしたいと思っても、あたしはそのつもり。あたしはいつもそばにいて、あなたのことを待っているから」 ビアンカがそれを求めていないなら、簡単に無視できていただろう。ナオミの呼吸が少しだけ早くなった。頬にほんのりと赤みがさした。落ち着かなそうに何度も椅子に座りなおしている。ビアンカはナオミの心を捕らえたのは明らかだった。たとえ、ナオミ自身はその自覚がまだないのではあるが。 「そ、それなら……それならば、あたし、これからもやっていける」とナオミは息を吐き出すようにして言った。 If you like this kind of stories, please visit Nikki Jenkins' Feminization Station https://thefeminizationstation.com/home/
店内はすでに大混雑だったので、入ってきたドアを閉めるのもひと苦労。ましてや、前に立ちふさがる男たちのせいで、先に進むことなどできなかった。ベティはステージにいるのは確実なんだけど、声を出して、この人たちの注意を惹きつけるのもイヤだったので、あたしはただ立って、男たちの肩越しにステージを見る他なかった。 思った通り、ベティがステージに立っていた。椅子のように見えるモノの隣に立っている。椅子なのかしら? 鮮やかな色のカバーがかかっていてよく分からない。ベティはかなり大きなバイブを手に持っていて、そのセクシーな機械仕掛けのペニスの説明をしていた。 改めて思うけど、ベティは素敵! 長い黒髪は緩いウェーブで両肩まで伸びていて、背中にかかる感じが官能的。角ばった両肩は肌が見えている。というのも、着ている白いブラウスが、彼女の大きめの胸は覆っているけど、胸から上は露わになっているから。下はミニスカート。セクシーな腰とお尻をぴっちりと包んでる。もちろん靴はハイヒール。 あたしは、ベティのセクシーな姿を食い入るように見ていたけど、ふと、さっきの駐車場での男の人たちも、あたしのことを同じような目で見ていたのだと気づいた。なんてこと? あたしもあの変態男たちと同じになっていたということなの? ひょっとして、この前、娘のクリスティと密接な関係になってしまったせいで、今もあたしの性的な感覚が際立ってしまっているということかも? ベティが立っているステージをよく見てみると、彼女の後ろに大きな体の男性が立っていた。思わずハッと息をのんだ! あれほど大きくて、あんなキリッとしてて、逞しさと強さを放っている人は、確かめなくても、他に考えられない! アダムだわ! あのストリップクラブで、フランクにレイプされそうになっていたあたしとリズを救い出してくれた、あの優しい大男! でも、どうして彼がベティを知っているの? 突然、あたしの後ろでドアが開き、男がふたり入ってきた。駐車場であたしの大切な場所をじっくり見てた、あの男たち! ちらっとふたりの様子を見ると、ふたりともあたしの長い脚とお尻を盗み見している。 店内はすごく混んでいたので、ふたりは、入って来たドアを閉めるにも、あたしの身体を押さなければいけないようだった。 ふたりはぎこちなさそうにドアを閉めたけれど、ひとりはあたしの横から胸を押し付けていたし、もうひとりは後ろからあたしのお尻に股間を押し付けているように感じた。当然、あたしは身体をこわばらせて、身構えた。店内がひどく混んでいるのは分かっているけど、このふたり、わざとあたしに身体を押し付けてきているように感じる。 あたしは振り返って、後ろから股間を押し付けてくる男の方を向き、「やめてください!」という表情を見せた。 「すまない。ここはすごく混んでるんで」と彼はつぶやいた。 あたしは何も言わなかった。けれど、あたしが見せた表情で、もし何かしたら、当然の報いを受けさせるから覚悟しなさいとっていうメッセージは伝わったんじゃないかと思った。 再び、ステージに目を向けると、ベティは売り出したい商品を見せているところだった。でも、あたしの目はアダムがどこにいるのかと探すのだった。
ウェンディはぐいぐい押し続けてくる。彼女のおちんちんがどんどん奥へと入ってくる。1センチくらいずつ、徐々に奥に入ってきてる。そして、その1センチ奥へと入れられるごとに、快感が増えていった。まるで、ウェンディのおちんちんがあたしの中にある、すべての快感ボタンを的確に押しまくってくる感じ。そして、そうされるとかえって、ジーナのおちんちんを咥えた頭をいっそう速く上下したくなる気持ちになった。ジーナが両手であたしの頭を押さえてる。あたしの頭の動きに合わせて、手で押し付けてくる。これをジーナが喜んでいるのが分かる。 とうとう、ウェンディのお腹があたしのお尻に押し付けられるまでになった。彼女の女の子っぽい、柔らかそうにぷっくり膨らんだ下腹部が、あたしの大きなお尻に当たってる。彼女のタマタマが揺れて、あたしのタマタマをピタピタと叩いてる。とうとう、根元まで完全に入れられちゃったと分かった。すごい! キチキチに詰め込まれてる! それに、何と言うか、ウェンディの本当のエッセンス、中核部分があたしの中に来てくれたという感じ。 すると、ウェンディがゆっくりと引き抜き始めた。思わず、切なそうな泣き声をあげてしまう。抜かれる時も入れられる時と同じくらい気持ちいい。ひょっとすると抜かれる時の方がいいかも。そう思っていたら、ウェンディは、先端のところだけが残ってるところまで抜くと、一気に叩きこむようにして戻してきた。彼女の突きに押されて、ジーナのおちんちんを喉奥まで飲み込まされた。その刺激に、危うく、失神しそうになった。 でも、その後は、一定のリズムができてきて、この行為に没頭することができた。3人とも、完璧なハーモニーでリズムを奏でた。仰向けになってるジーナは、腰をリズミカルに突き上げて、あたしの口に入れたり出したり。後ろにいるウェンディは、両手をあたしのお尻に添えて、素敵な可愛いおちんちんを入れたり出したり続けてる。そして、あたしはふたりの間に四つん這い。よくテレビとかで、豚が、焚火の上で、口からお尻まで串刺しにされて、丸焼きになっている光景とかが出てくるけど、まさしくあのイメージだった。ウェンディとジーナのふたりのエッチなおちんちんに串刺しにされて、熱く焼かれてるあたし。でも、それがとても、とても嬉しい。気持いい! あたし自身のおちんちんも、早く発散したいとビンビンになっていて、ふたりの動きに合わせて揺れていた。 最初にイッたのはジーナ。あたしは、彼女の両脚に乳房を擦りつけていたのだけど、その彼女の両脚が、突然、キューっと緊張し始めた。どうしたのかなと思ったけど、次の瞬間、ジーナはお腹の底からだすような低い唸り声を出した。そして、またその次の瞬間、これまでになく強く腰を突き上げてきた。そしてさらにまた瞬間、ジーナのおちんちんの中をスペルマが急速に上がってくるのを感じた。で、次の瞬間、熱い奔流が口の中に撃ち出された。このムッとした味と香りがたまらない。 次々にドロドロの塊があたしの口に撃ちこまれ、口の中がいっぱいになる。味わいつつ、懸命に飲み込み続けた。でも、そうしていた間に、ウェンディが楽しんでいたお尻の穴を無意識的にキューっと収縮させていたのかも。 あたしが急にアヌスを締め付けたせいで、ウェンディは限界を超えてしまったよう。ウェンディは左手で爪を食い込ませるくらい強く、あたしのお尻の頬をつかんで、右手ではあたしのお尻をぴしゃりと平手打ちした。それと同時に、これが最後と言わんばかりに、強く押し込んできて、その次の瞬間、熱いモノがあたしの中に撃ち出されるのを感じた。 自分の体の中の様子がイメージできる感じだった。ウェンディの放った精液があたしの直腸をいっぱいに満たして、そこで収まりきらなくなったものが、あたしの菊の花みたいに狭いところから溢れ出て、そこを塞いでるウェンディのおちんちんにびちゃびちゃに降りかかる様子。口の中とアヌスに同時に撃ち出されたドロドロを受けて、あたしはひとたまりもなかった。両ひざがガクガク言い出した。ふたりのペニスに貫かれ、それだけで身体を支えているあたし! なのに、オーガズムが襲ってきて、急に体が軽くなる。いつまでも永遠に、このままふたりに貫かれている状態でい続けたいと。あたし自身が何かを噴出した音を聞いた。どうやら、あたしは潮吹きをして、熱い体液を寝室の床に振りまいたらしい。そして、自分自身、そのびしょ濡れの板の床に突っ伏した。もう、何が何だか分からない。
≪前ページ | HOME |
次ページ≫
|
