映画の中盤にかけて、ジョアン・ウッドワードは、メイクアップ、衣装そして新しいカツラのおかげで、とても可愛く変身した。そして、まさに映画がそのシーンになったとき、私は、ここにいるディアドラとドニーがジョアン・ウッドワードによく似ていると気づいたのだった。そして、その映画を見ていたまさにその部屋で、私の目の前で、あの光景が展開していったのである。そして、アンドリューは映画に集中できなくて困っているように見えたのだった。果たして、それはどんな光景だったのか? ディアドラもドニーも気づかないふりをしていたけれども、私には、ふたりともアンドリューの視線をしっかり感じていたと分かる。ふたりとも、カウチに座りつつも、何度も座りなおしたりを繰り返していた。そして、そうやって態勢を変えるたびに、ふたりのスカートは少しずつめくり上がっていた。アンドリューは、ふたりが見せる脚の肌に目を奪われているように見えた。この男性、深刻な状態と言えるほどムラムラしている。みんなが思っているように、本当にセクシーな男性なのかもしれない。 アンドリューはいったんキッチンに行き、そしてすぐに戻ってきた。あっという間にみんなにポップコーンとフルーツジュースが用意された。この人、とても家庭的な男性でもあるのだ。私は感心した。 映画は終盤に差し掛かっていた。寝室のシーンがあって、そのシーンではジョアン・ウッドワードはポール・ニューマンを誘惑しようとセクシーなネグリジェ姿になっていた。 そして、ちょうど良いシーンになりそうというところで、映画の中のジョアン・ウッドワードが突然、カメラ目線になったのである。まっすぐアンドリューを見ているように見えた。 そして彼女が言ったのだった。「パパ、どう思う? 私、上手にできてる?」 ジェイクがジュースが入ったグラスを床に落とした。みんなでトワイライトゾーンに入ってしまったの? アンドリューが笑顔になって言った。「悪くないよ。この前のよりはこっちの方がずっと好きだな」 次にアンドリューは、ジェイクと私に顔を向けて、「先週、彼女は『エミー・ダズ・ダラス』( 参考)で主演をやったんだ。観てて恥ずかしかったけど、エミーが女優としてデビーより上手なのは認めようと思ってるんだ」と言った。 画面の中、ジョアン・ウッドワードの顔をした人がジェイクと私の方を見た。「これは、私たちがVVと呼んでるものなの。バーチャル・ビデオ(Virtual Video)でVV。主要な登場人物は全員、デジタル化されているわ。バーチャルのヘルメットがあって、それを被ると登場人物のひとりになれるの。私はジョアン・ウッドワードになりたかった。パパがジョアン・ウッドワードの熱烈なファンだから」 アンドリューは困った顔をした。「エミー、僕のことをダシに使わないように!」 画面の中のジョアン・ウッドワードは笑って、彼に投げキスをした。これだけでもシュールな状況なのに、驚いたことに、画面の中のポール・ニューマンはジョアンに向かって、「どうしたんだ? 台詞を忘れたのか?」と言い出した。 ジョアンはポールの方を向いて「お黙り!」と言った。ポールは、あのトレードマークの「どうでもいいや」という微笑みの表情をした。 ジョアン(エマ)は私たちの方に向き直って話を続けた。 「台本はあなたの目の前に表示されているでしょ。今は7か国語でできる(だって、言語はそれしかしらないから)。でも、市場に出せる準備ができる頃には、すべての主要な言語はカバーできるでと思うよ……」 「……台本からちょっと逸れることもできるわ。でも、今のところは、大きく逸れてしまうと他の役者たちがついていけなくなるの。他の役者もバーチャルなら可能だけど。それに、役者の声を使うことも、自分の声を使うこともできるよ」 突然、ジョアンの口からエマの幼い声が出てきた。そして、顔や姿かたちが変形して、エマのイメージに変わった。これって、本当に変な感じ。 「ヘルプモードもあるのよ。演技のヘルプでも、批評的なヘルプも。見てみたい?」 ジェイクも私も頭を縦に振った。エマがどこにいるのか、私には分からなかったが、彼女の方は私たちが見えているに違いない。 「ヘルプについては数段階のレベルをプログラムしておいたわ。これは『パパのご講義』ヘルプモード」 ポール・ニューマンがゆっくりとあんどりゅー・アドキンズの姿に変わり、またゆっくりとポール・ニューマンの姿に変わった。 そのポール・ニューマンがしゃべりだした。「エミー、それはとても良いよ。でも、シーンにもっと気持ちを込める方法を知らなくちゃいけないよ。取り掛かる前に、自分が何を求めているかを頭に描くんだ。そして、本当の気持ちを隠さず、表に出す。A)自分の内面を見つめて、単語の意味をしっかり知ること。B)それから……」 彼はその後もだらだらと何かしゃべり続けた。エマの姿が元のジョアン・ウッドワードへと戻り、そのジョアンは指を自分の喉奥に入れて、オエッっと吐き出しそうな声をあげた。 「もう充分だよ! ジョークの意味はみんな分かったから」とアンドリューが言った。 ジョアンは少し微笑んだ。「それに『パパの運転』ヘルプモードもあるよ」 突然、ポール・ニューマンが立ち上がり、怒鳴り始めた。「お前、いったい何やってんだよ! お前、バカか、うすのろ!」 子供たちが皆クスクス笑い出した。ふたりの妻たちも笑っていた。 アンドリューが言った。「みんな、ヘルプモードの要点は理解したと思うよ。だから、もう終わりにしよう。僕が暴力的になって、役者たちをひどいやり方で排除し始める前にね」
俺はミセス・グラフの濡れた肉穴に指を出し入れしながら、質問を続けた。 「お前の旦那は、俺の兄のように、お前に対して魔法のような特別な夜をもたらしてくれたか?」 「い、いいえ」と、彼女は息を詰まらせ、小刻みに体を震わせ始めた。 両手ともテーブルの端をしっかりつかみ堪えているところを見ると、オーガズムに達しているのだろう。目を閉じ、下唇を噛んでいる。震えながら頭を俺に寄せ、顔を俺の胸板に当てた。膣肉が収縮を始め、俺の指をきつく締め付けてくる。 「兄に身体を上下に揺さぶられて、繰り返し貫かれ、お前は頂点に達したんじゃないか?」 「そうよ………」と、彼女は俺の首に熱い息を吐きかけ、同時に、コントロールできなくなったのか体をがくがく震わせ始めた。 彼女がオーガズムの頂点にとどまり続けた数十秒、ふたりとも何も言わず、沈黙の時間が流れた。テーブルの端を握る彼女の手は、あまりに強く握っているせいか、ほとんど血の気が失せていた。息づかいはどんどん乱れ、熱い吐息が絶え間なく俺の首筋から胸にかけて吹きかけられる。言葉については沈黙が続いたが、体は雄弁に訴えていて、狭い肉筒は発作を起こしたように繰り返し収縮を続け、そのたびに愛液を分泌し、俺の指を濡らした。 しばらく経ち、ようやくミセス・グラフの震えが引き始めた。 「その後、兄は何をした?」 ミセス・グラフは、乱れた呼吸を落ち着かそうと顔を俺の胸板に埋めたままでいた。テーブルをつかむ手の力も弱くなり、それに合わせて手に血が戻ったのか、急に普通の色に変わった。彼女は、一度大きく深呼吸した後、ようやく目を開いた。震える手を伸ばしてコーヒーカップを取り、ひとくち啜った。ゴクリと音が聞こえるような飲み方をした後、カップを元に戻す。そして、唇をひと舐めした後、顔をあげ、俺の目を覗き込んだ。 「あたしを抱いて、体を上下に揺すり続けたまま、ビーチの方へ歩き始めたわ。ビーチへとどんどん近づいていたけど、あたしは、何度も貫かれていて、ずっとイキっぱなしだった。水は徐々に浅くなっていて、とうとう、あたしの身体がすっかり水面から出てしまった。水中にいた時より、水の外に出た時の方が全身の神経がピリピリする感じだった。風は暖かだったけど、濡れた体に当たると刺激が強くて。両脚は彼の腰に巻き付けたまま。もちろん彼のアレもあたしのアソコに入ったまま。そのままの格好で、波打ち際まで来てしまったの」 ミセス・グラフは、そう言って、また目を閉じ、頭を少し後ろに倒した。
2021052101 あなたがあたしのようになるわけないのは分かってるわよね。でも、あたしのパンティを履けばセクシーな気分になるんじゃない?  2021052102 ねえ、これから元カレとエッチするところなのよ。だからいつものようにあたしのパンティを履いて、一晩中オナニーしててもいいわよ。あたしの許可を取ることないわ。許可しなくたって、どうせそうするつもりなんでしょ……だから、そういうつまらないことであたしに電話かけてこないで。  2021052103 あなたがあたしのことを思ってるのは知ってるわ。 ただ、あなたはあたしと一緒になりたいと思ってるわけじゃないのよね……あなたはあたしになりたいの、シシー君。  2021052104 あなたのような変態シシーは、あたしのアソコを見たりはしないもの。 そうじゃなくて、あたしの靴を履いてみたいと好奇心をもってるもの。  2021052105 この考えに慣れることね。 シシーは、おちんちんをしゃぶってるあたしくらいにセクシーには見えないということ。  2021052106 あなたがシシーなのは知ってたわ。そういうわけだから、あたしはあなたの親友との今夜のデートに履いていくパンティを選ぶのをあなたに手伝ってって頼んだの。 あなたなら趣味がいいって思ったから。  2021052107 賭けてもいいけど、あなた、脚の間におちんちんじゃなくて、あたしのみたいなおまんこがついていたらいいのにって思ってるでしょ。そうしたら、どんな感じか分かるだろうって。 あなたにはお尻の穴はあるけど、それとこれとは同じじゃないって分かってるのよね。 まあ、いつまでも夢を見続けていなさい、シシー君。  2021052108 あたし知ってるのよ。あなたがあたしの下着を身に着けながら、自分と同じような他の負け犬たちとチャットしていたいんだって。だから、そのまま続けてなさいよ、その間に今夜のデートに行く準備をしてるから。  2021052109 あなた、あたしと同じランジェリーを着てるの? でもあなたとあたしの違いは、あたしの方はすごく素敵に見えるけど、あなたの方は役立たずの気持ち悪い負け犬にしか見えないって点ね。 自分でもそういう気持ちになるのが好きなんでしょ? 違う?  2021052110 あなた、ただいま。ミルクを欲しがっていたわよね? 家に置いてなかったので、お隣さんにもらいに行ったわ。そしたら、突然、おとなりさん、あたしの目の前でシコシコし始めたのよ(まあ、あたしもちょっとだけ搾り取るのを手伝ってあげたけど)。どうする? コーヒーに入れる? それとも、あたしのおっぱいからじかに啜りたい? 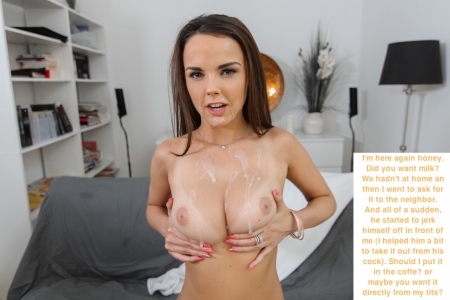
「あっ」と、戻っていくウェイトレスの背中に妻が声をかけた。「ごめんなさい。もうひとつあるの。このお店、どこかにお手洗いはある?」 ウェイトレスは髪をなびかせ振り返った。「もちろんです。奥のドアから出て右側に」とカフェの奥にある網戸ドアの向こうを指さした。 「お願いだから、案内してくれる?」 コリーンは立ち上がりながら、甘い声で頼んだ。「あたし、すごい方向音痴なの」 実際は違う。もっとも、ウェイトレスは案内できて嬉しそうで、ふたり一緒に歩いて行った。コリーンは僕に見える方の頬だけをちょっと歪ませ、笑みを見せた。彼女、さらに獲物に魅力を振りまこうとしてるのか? しばらく通りを歩く観光客やサーファーや引退してくつろぐ老人たちを眺めてすごしていたが、ふと、コリーンがトイレに行ってからかなりの時間が過ぎていることに気づいた。加えて、僕の注文したコーヒーはまだ来てない。どうなっているのか聞こうにも、例のウェイトレスの姿も見えなかった。 僕の心配に反応するかのように、突然、スマホが鳴った。コリーンからのメッセージが入っていた。「女子トイレに来て。ちょっとヘルプしてほしいの」とある。 ひょっとして生理の問題かな? 僕は妻のバッグを取り、トイレに向かった。たいていの問題には、女性のバッグの中に役立つものが入っているに違いないから。カフェの中を足早に進み、奥のドアから外に出た(そこには、良い雰囲気のちょっとした野外のスペースがあって、テーブルも植木もあるし、日よけもある。ここに座って食べたほうがよさそうだな)。そのスペースの脇の方、ツタの天蓋の下に女子トイレがあった。僕は優しくノックした。 中からは、くぐもった笑い声が聞こえてくる。違うドアをノックしたのかな? 「あなたなの?」とドアの向こうから声がした。コリーンの声だった。 「ああ。大丈夫か?」 「うーん、ちょっと中に入ってきてくれる?」 また、ひそひそ声での笑い声が聞こえ、その後、ちょっとして鍵が開けられる音がした。僕はためらいがちにドアを押し、そのとたん、どうして僕のコーヒーが来なかったのか理解した。あのウェイトレスは、僕の妻へのサービスで忙しかったのだ!
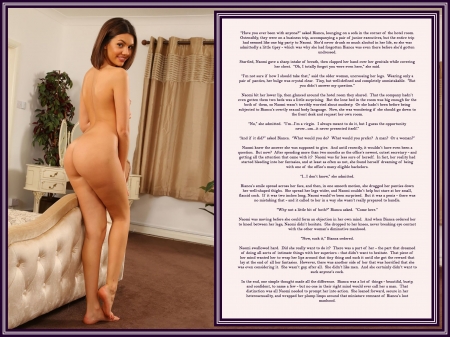 Sissy Secretary 14 「シシー秘書14」 「あなた、誰かと経験ある?」とビアンカは、ホテルの一室、部屋の隅にあるカウチにくつろぎながら言った。表面的には、ふたりは、それぞれ若手の重役に付き添いという仕事で出張に出ているように見えるが、ナオミにはこの出張は最初から最後までひとつの大きなパーティのようにしか思えなかった。ともかく彼女はこれまでの人生でこんなに酔ったことはないと思うほど酔っていて、多少、ろれつが回らなくなっているのも自覚していた。……そんなわけで、ナオミは服を脱ぐまでビアンカが同じ部屋に来ていることを忘れていたのだった。 ナオミはビックリして、ハッと息をのみ、片手で陰部を隠し、もう一方の手で胸を隠した。「あっ、あなたがここにいたこともすっかり忘れていたわ」 「その言葉、どう取っていいか分からないわね」とビアンカは組んでいた脚を解いた。彼女もパンティだけの姿で、股間が盛り上がっていることは一目瞭然だった。小さいけれども、しっかり輪郭が浮き出ていて、完全に間違いようがない。「でも、私の質問にまだ答えてくれてないわよ?」 ナオミは下唇を噛んだ。そして、自分がいるホテルの一室を見回した。会社がこの出張に際してビアンカと同室なのにベッドがひとつだけの部屋をあてがったことは、少し驚きだった。ベッドはひとつだけとは言え、ふたりで寝るのに十分大きなキングサイズではある。だから、ナオミは極度に心配して気恥ずかしさを感じていたわけでもなかった。あるいは、ビアンカがあからさまに性的なことをほのめかす身振りや態度をとるのに接するまでは、そうだったとでも言おうか。今は、フロントデスクに行って部屋替えを要求すべきかどうか迷っている。 「いえ……あたしは……経験ないの。いつでも、そのつもりはあったんだけど、そういう機会が……うーん……そういう機会がなくって」 「じゃあ、そういう機会が現れたら?」とビアンカが訊いた。「どうするつもり? どっちがいいの? 男? それとも女?」 ナオミはどっちで答えるよう期待されているか知っていた。つい最近までは、そういうことは質問にすらならなかった。でも今は? 会社の一番の新入りで、一番愛らしい秘書となってから、すでに2か月以上。それに応じて、男性幹部たちにずいぶん注目され、ちやほやされてきた。ナオミは自分自身がどうしたいのか、以前とは全く異なり、確信が持てなくなっていた。正直言えば、すでに現実生活が彼女の妄想に刺激を与え始めており、少なくとも時々ではあるが、彼女は、自分が会社にいる多くの適切と思われる独身男性のひとりと一緒になるのを夢見ていることがあるのだった。 「あたし……あたし分からないんです」とナオミは告白した。 ビアンカの顔に嬉しそうな笑みが広がった。そしてビアンカは、滑らかな動きで、形の良い太ももに沿って自分の下着を降ろし、両脚を大きく広げたのだった。 ナオミは、ビアンカの柔らかく萎えている小さなペニスを見つめないではいられなかった。それが5センチもない代物であれ、それを見てナオミは驚いたことだろう。だが、それがペニスであることは変わりがなかった……見間違えるはずがない……。そして、それが自分に呼び掛けている。自分には心づもりがちゃんとできていないようなことをさせようと。 「ほんのちょっとだけ、両方をやってみるのはどう?」とビアンカが言った。「こっちに来なさい!」 ナオミは、心の中でそれへの反論を用意できないでいる間に、体の方が動いていた。 「私の脚の間に正座して!」 ナオミはためらわなかった。ゆっくりと両膝を床につけた。その間、ナオミはビアンカの小さな男性の印から一度も目を離さなかった。 「じゃあ、吸いなさい」 ナオミはすぐに口の中に頬張った。本当にそうしたかったのだろうか? 確かに、ためらいたくないと思う心はあった。……自分の上役に当たる人とあらゆる種類の親密なことをするのを夢見る気持ち。その心の部分では、この小さなモノを唇で包みこみ、妄想の果てにあるご褒美を授かるまで、舐め、吸い続けたいと思っている。でも、心の中には別の部分もあって、そこでは、こういうことを考えることすら恐ろしいと思っている。何と言っても、自分はゲイではないのだ。男性が好きでもないのだ。それに、誰のであれ、そのペニスを吸いたくなんかないのだと。 だが、結局、あるひとつの単純なことを思い、すべてが変わった。ビアンカは、美しいし、ふくよかな肉体をしているし、自信にあふれているなど、いくつも性質があるけれども、いずれにしても、誰一人としてまともな心の持ち主なら、彼女を男性と呼ぶ人はいないだろうという点だった。その点こそビアンカと他の人とを分ける点であり、それを認識するだけでナオミを行動に移すのに充分だった。彼女は、自分はヘテロの性的嗜好を持つ人間であるという自意識を保ったまま、安心して前のめりになり、そのぷっくり膨らんだセクシーな唇で、ビアンカの失われた男らしさの残余と言える小さなペニスを包んだのだった。 If you like this kind of stories, please visit Nikki Jenkins' Feminization Station https://thefeminizationstation.com/home/
駐車場はいっぱいになっていて入れなかった。仕方なくビルの角を曲がり、ようやくそこに空きスペースを見つけた。車を止めて、エンジンをきり、しばらく運転席に座ったまま考えた。……本当にお店に顔を出すべきかどうか。 改めて駐車場を見回した。こんなに車が止まっているということは、お店もすごく混んでいるのは確か。しかも、みんな男たち! だって、こういう場所に男以外で誰が来るというの? そして、もう一度、自分の格好を見てみた。こんなに肌を露出している。ああ、ほんとに、こんなに……そして、こんなに小さなお店なのに、男たちでいっぱいだとしたら! すでに肌を露出しているけど、これ以上は絶対に肌を見せないよう、すごく注意しなくちゃいけないだろうな……。 気づくと、乳首が固くなり始めていた。それに脚の間も湿っぽくなってきている。ちょっとだけ、顔を出してくるのがいいかも。あんなに喜んでいたベティに悪いし。彼女に挨拶して、すぐに出てくれば構わないのじゃ? あたしがこういう格好してきたのは、そもそも男たちに見てもらって、焦らしてあげるのが目的だったのに、どうして、今になって怖気づいてるの? ダメよ、やっぱりお店に顔を出すべき……ほんの少しだけでいいんだから。 大きく深呼吸して、車のドアを開け、片脚を外に出した。もう一方の脚はまだ車の中。ちょうどその時、車のそばを男の人がふたり通りかかった。びっくりして、一瞬固まってしまった。ひょっとすると脚の間が見えてるかも! ちらっとその人たちを見たら、なんてこと、やっぱりあたしの脚の間を目を凝らしてみてるじゃないの! 素早くもう一方の脚を車から出して、両膝をくっつけて脚をそろえた。ふたりのことは無視して、何も起きてないようなふりをして、平静を装った。見えたとしても下着だけなんだから。 あ、違うわ! あたし、今は股間のところが開いてるパンティを履いているんだった。だとしたら、あそこの唇も……もしかすると、あそこも見えていたかも。 男の人たちはふたりとも、ヘッドライトに照らされた鹿のような目をして、舌なめずりしてた。濡らした唇がすぐに乾いてる。 ああ、ふたりともあたしのパンティを見たんだ。多分、それ以上、見られたかも! 車から出る時にも大きく息を吸ったけど、この時も、立ち上がる前に深呼吸しなくちゃいけなかった。肩で息をしたせいか、ドレスがずり上がるのを感じた。腰をちゃんと包んでるはずなのに、ここまで運転してきた間にずり上がっていたのか、もっと上までずり上がっている。 彼らに見られないようにと後ろ向きになったけど、それでもふたりの視線が向けられているのは感じていた。今度はお尻を見られている。どのくらい見せてしまってるんだろう? それとなく目を落として確かめたら、ドレスの裾が股間のところまで上がってるのが見えた。ということは、あの男たち、あたしの脚からお尻まで全部見たってこと?! 「ああ、もう! あたしったら、なんでこんなことやってるの?」と小声でつぶやき、ドレスの裾を引き下げた。 でも、あんまり強く引き下げないよう、注意しなくちゃいけなかった。強く引っ張ると、今度は上の胸の方が飛び出てしまうから。 ちゃんとした格好に戻ってると期待しながら、男たちの方に向き直り、横を通り過ぎた。最大限の意思の力を振り絞って、ふたりが見せてる飢えた顔を無視した。心臓がものすごく早く鳴っている! ふたりからちょっと離れたところまで来たとき、ふたりの話し声が聞こえた。 「おい、すげえエロいな!」 「ああ、まったくだぜ。あの女、ポルノ女優だと思わねえか?」 「ああ、そうに違いねえ! ありゃ、ポルノスターだぜ。お前、あのパンティ、見たか? まんこが見えてたぞ! お前も見ただろ?」 あたしがポルノスター?! ビルの角を曲がるとふたりの声は聞こえなくなり、あたしは入口へと向かった。 ああ、やっぱり、あの人たちにはアソコを見られていた! それはそれで、最悪なことだったけど、急に普通じゃないゾクゾクしたスリル感が沸いてきて、息づかいを普通に戻すのが大変だった。入口のドアの前に立ち、いったん大きく息を吸ってから、ドアを開けた。 すぐに目に入ったのは、群れをなす男たちの背中ばかり。みんな立っていて、部屋の向こうの壁際に設置されたステージのようなものに顔を向けていた。
ちょっとだけジーナのおちんちんを口から出して、後ろのウェンディの方を見た。ジーナは切なそうな声をあげたので、彼女を気持ちよいままにさせるため、唾で濡れたおちんちんを手でしごいてあげた。肩越しにウェンディを見上げると、彼女は乳房を揺らしながら、片手で自分の勃起を握って、もう一方の手を口に持って行ってるところだった。その手のひらにたっぷりと涎れ混じりの白濁を吐き出してる。あの可愛い顔のウェンディが、口からペッと唾を出してる姿! 言葉に表せないほどすごくイヤラシくて、すごくエッチ! ウェンディはあたしが見てたのに気づくと、ウインクして見せた。 ウェンディはその手をあたしのお尻に降ろして、まだ温かい濡れたドロドロを、丸見えになってるあたしのお尻の穴に擦りつけた。 ぶるぶるっと体が震えた。あたしがこれから何をされるか、はっきり分かったから。 あたしは、ずっと、こればかりは一生することがないだろうなと思っていた。それが今、あたしにされようとしてる。なぜか怖くなかった。むしろ、やってほしくてたまらない気持ちになっていた。それを求めるように、あたしは自然と腰を後ろに突きだしていた。 顔をジーナの方に戻し、彼女の固いおちんちんを口の中に戻す。ぐっと一気に喉の奥まで飲み込んだ。すでに貫通しているから、今度は簡単に飲み込むことができる。飲み込んだとたん、ジーナは安心したように、ハアーっと溜息を漏らした。 ジーナのおちんちんを舐め吸いしてると、お尻の穴をちょっと押される感じがした。ウェンディのベトベトした手があたしの腰を掴んで、ぐいっと引き寄せようとするのを感じた。見えてはいないけど、もう一方の手は彼女のおちんちんを握って、あたしのアヌスに狙いを定めているに違いない。 あたしは夢中になって頭を上下に振り、ジーナのおちんちんをしゃぶり続けていたけど、心はアヌスの方に集中していた。 「覚悟はいい?」 ウェンディの声が聞こえた。「私のおちんちんを頬張るのよ!」 その言葉を聞いただけで膝ががくがくしてくる。アヌスへの圧力がどんどん強くなってくるのを感じた。後ろからぐいっと押され、あたしは前につんのめり、ジーナの恥骨に鼻が押しつぶされる。喉は完全に塞がれ、反射的にヒクヒク痙攣してジーナのおちんちんを締め付けている(ジーナのヨガリ声からすると、よっぽどすごい快感を味わっている様子)。こんなに苦しく痛めつけられても、他に動ける場所がないので、なされるがままになっているほかない。 アヌスへの圧力はどんどん強くなってきた。だけど、その時、あたしは、ぐっとイキんだのだった。あそこの中から捻り出すときのように。そして次の瞬間、パッと中が開いたような感じがした。 ウェンディのおちんちんの先のところが中に入ったのだと分かる。あの太ったマッシュルーム状の先端が中に入ったのを受けて、限界まで広がっていたあたしの肛門がきゅうっと口を閉じる動きになったのだと分かった。あたしは、ジーナのおちんちんを咥えたまま、低い声で唸った。この感覚、信じがたい感覚だわ。こんなに……こんなに中がいっぱいにされた感覚は初めて。とても強烈。だけど、全然不快じゃない!
「ジェイク? あなたは法律関係の監督になってくれっていうアドキンズ家の申し込みについて、考えているところなの?」 「分からないんだ。僕がいま稼いでる額の4倍は出すって言ってくれている。でも、僕は元々、正義に燃える「熱血検察官」になりたかったんだ。まあ、現実は僕が抱いていたイメージとピッタリというわけじゃないけど。でも、まだそういうイメージが好きなんだ。何か重要なことをしてるんだって気持ちが」 「でも、この話もかなり重要のように聞こえるけど。やりがいのある大きな挑戦になると思うし、潜在的な力は計り知れないと思うけど?」 「ああ。本当にワクワクするチャンスだと思う。加えて、ドリューが嘘をつくのがありえないのと同じか、それ以上に、アンドリューは嘘をつかないだろう。命にかけても、ここの人たちは信頼しようと思ってるんだ」 この人の南部訛りはすごく魅力的だった。誠実だし、才能もある人のように思えた。誠実さというのは双方向的に作用するのかもしれない。アドキンズ一家は、ジェイクについて誠実だと思わなかったら、そもそも、こういう申し出をしてないと思う。ジェイクについて何か重要なことを知っておかなくちゃと感じた。 「この件について、あなたの奥さんはどう思っているのかしら?」 わざとらしい質問と聞こえていなければいいけどと思いつつ訊いた。 ジェイクは微笑んだ。「いや、僕には奥さんはいないよ。残念ながら。今は、僕が心配しなくちゃいけないのは僕自身だけ」 嬉しい返事。「たくさん出張しなくちゃいけなくなるのかしら? というか、かなり交渉の仕事があるような感じだけど」 「ドリューによると、交渉の大半はリモートでできるらしい。まあ、特にニューヨークとシリコンバレーには何回か行かなくちゃいけなくなるのは確かだけど。ワシントン州もあるかな。でも、あんまり出張はないと思う。出張はうんざりと思うほどにはならないと思う」 「何だか、彼らの提案を受ける方向に傾いているように聞こえるけど?」 ジェイクはそこまでは気持ちができているわけじゃなかった。「まあ、彼らがどんなのを用意しているのか見てみようと思ってるんだ。そうしてから、決断しようかなと」 そんな時、アドキンズ一家が、部屋へと集まり始めた。アンドリューは部屋に来ると、ひとつの壁にあるドアを開いた。そこには見たこともないほど巨大なフラットのテレビがあった。これを買うにはひと財産使ったはず。ここの人たち、本当にすごいおカネを持っているんだろうな。 とうとう、みんなが集まった。ドニーとディアドラは並んでひとつのカウチに座った。それぞれ男の子を膝に抱いている。どっちの子も親指をしゃぶっていた。アンドリューは左右の膝のそれぞれに女の子を乗せて、リクライニングに座った。もうひとり幼い女の子はジェイクの膝に登った。子供のなつき具合から、ジェイクが前にもこの家に来たことがあるのは明らかだった。 もうひとり女の子がいたはず。その子が私の膝に乗りたがるかもしれないと思って、部屋を見回したけれど、どこにもいなかった。 テレビのスイッチが入り、映画が始まった。多分、ディズニーの子供向けの映画だろうなと想像していたが、実際は、60年代の古い映画だった。主演はポール・ニューマンとジョアン・ウッドワード( 参考)。「パリが恋するとき」( 参考)という映画。観たことがないと思うけれど、とても良い映画だったと認めざるを得ない。軽いコメディー映画だった。 ジョアン・ウッドワードは、冴えないファッションデザイナーで、重要なデザイナーのデザインを盗むためにパリに派遣される女性の役。一方のポール・ニューマンは新聞記者だが、上司の妻を寝取ったためパリに左遷される男の役。 子供たちは、ひとり、またひとりと大人たちの膝から降り、床に寝転がって映画を見ていた。私は、残る最後の女の子はどこにいったのかと、いまだに不思議に思っていた。
「彼は息を吸うため水の上に出てきたの」とミセス・グラフは喘ぎながら言った。隣の席の人にも聞こえそうな大きな声だ。俺は素早く指を引き抜いた。 彼女は、乱れ、苦しそうな息づかいになっていた。目を閉じ、脚は俺が自由に股間をいじることができる程度に開いたままだ。 「それから兄は何をした?」 そう聞きながら、指で割れ目を撫で上げた。それを受け、彼女はハッと息をのんだ。 「顔を寄せて、あたしにキスをしたわ。舌が触れあった時、あたし自身の味が残ってるのを感じた。しばらく情熱的にキスを続けていると、彼があたしのお尻に両手を添えた。そして、ふたり、唇を重ねたままで、彼はあたしのお尻を抱え上げた。何が起きてるのか分からないでいると、今度は、いちど抱え上げられたお尻が降ろされるのを感じたの。そこには彼のアレが待っていたわ」 俺の奴隷である女教師は静かな口調で語ってはいたが、呼吸はますます乱れていた。俺が指を肉筒の中に戻すと、またも大きな喘ぎ声を漏らした。 ミセス・グラフは過去の出来事を語りつつ、脳内で再現しているんだろう。できるだけこれを続け、彼女を喜ばせてやろうと思った。彼女が興奮した思い出の一夜。それを思い出させ、もう一度だけ再体験させてやろう。だが、この後はその夜のことを二度と考えるなと禁ずる。最後の一回ということだ。 「で、中に入れられたのか?」 俺は顔を寄せ、彼女の首筋にキスをしながら、指をあそこに出し入れし始めた。 「ああ、そ、そうです……」 ミセス・グラフは喘ぎながら言った。 「身体を持ち上げられ、そして、また下げられて彼のアレを入れられた。水面に身体を持ち上げられたとき、そよ風が胸に当たって、乳首がいっそう固くなっていたわ。あたしは両脚を彼の腰に絡みつけて、彼は、あたしを持ち上げては降ろす動きを始めた」 「俺が今やっているようにか?」と、指を出し入れしながら、小さな声で訊いた。 「ええ、そう……」とミセス・グラフも小声で答える。 カウンターの方を見たら、例のウェイターが俺たちを見ていた。ポップコーン・マシーンの陰に隠れてこっちを見ている。まあ、あいつにはしっかり見せてやろう。チップ代わりにパンティを置いていくつもりだが、それに見合った良い思い出を残してやろう。
2021051701 今日のパーティ、最高よ、あなた。いま、トイレで一発してきたことろ。  2021051702 あなたの可愛くて無垢な妻は、もう、そんなに可愛くも無垢でもなくなったわね、寝取られさん。  2021051703 何で、あんた、あたしを見てるのよ? これは、あんたのためじゃないの。 これは、今夜クラブに来る本物の男たちのためなの。  2021051704 このドレスが何を意味するか、あたしもあなたも分かってる。 それなのに、まだ、あたしにはあなたのお友達を誘惑できないと思ってるわけ?  2021051705 今度のパーティはうまくいきそう。職場の男たちはみんな、この服装がいいって言ってるし。  2021051706 彼、あたしのアナルに出して、栓をしていったの。 栓を抜いて、彼のスペルマを全部吸い出して!  2021051707 あなたの妻がデートの準備をするのを見ること、しかも、あなたは招待されていないこと。これほど興奮することはない。  2021051708 この表情がすべてを語っている。彼女は他の男と姿を消すと。  2021051709 今夜は、男の人をふたりにしようと思ってるんだけど、あなた、どう思う?  2021051710 あたしに、バーのあの男に話しかけてほしいの? 
ウェイトレスの彼女が戻ってきた。足を広めに開いた快活な姿勢で僕たちの前に立っている。 「お待たせしました。お客さん、今朝はごきげん?」 「あの都会から離れてきたからね。最高よ」とコリーンは、何気なくメニューから顔をあげて答えた。「また、ここの、クールで美しい人たちと一緒になったんだもの!」と妻は、あの明るく人懐っこい笑顔を見せた。第一印象が重要だ。 「あら、おふたりはブリスベン( 参考)に住んでるの?」と彼女も笑みを返した。彼女は無意識的に妻の盛り上がった胸に目を向けていた。妻の乳房は、薄地のカラフルなサンドレス( 参考)の中、ひとの目を惹かないようにと頑張っていたが、どうしても目立ってしまうのだろう。 「そうだけど、自分で選んだわけじゃないんだけどね!」と僕は言った。彼女が、僕の露出した腕や肩の筋肉をちらっと見たようだ。 「うふふ……そうね、ここの方がずっとすごしやすいわよ。あたしなんか、もうここを離れられないもの」 「ちょっと聞いてもいい? あなたはここで午前中は働いて、午後はずっとサーフィンをしているんじゃ? あら? はずしてないわよね?」 彼女はケラケラ笑い出した。「アハハ。ええ、そんなところ。シーフィンはしないけど。だけど、ビーチは絶対に無駄にしないわ。特にこの時期は絶対に」 「じゃあ、絶好の時期にここにいるってことね!」 コリーンは、両腕をあげて、ほとんど雄叫びにちかい声で叫んだ。その様子を見てウェイトレスは陽気に笑った。「ここの人たちってみんなすごく素敵! っていうか、あなたを見てもそう思うもの!」と妻は、ブロンド髪のウェイトレスの頭からつま先まで視線を走らせた。見ていることをはっきり分からせるような仕草で。僕の妻は、本当に、時間を無駄にしない女だな。 ウェイトレスは長いポニーテールしている。その彼女が、パッと顔を明るくした。 「ほんと、あなたたち、ここにぴったりマッチした人たちだわ。おふたりは、アスリートなんじゃ? そうとしか見えないけど!」 妻のコリーンは普通はお世辞には引っかからない。だが、この言葉は嬉しかったのか、さらにこのウェイトレスを征服したい気持ちが燃え上がったようだ。 「違うの。でもあなたって優しいのね!」と妻は恥ずかしがっているふりをした。 ウェイトレスは仕事があったことを急に思い出したようだ。「とりあえず、コーヒーをお出ししますね?」 「あたしは何か……背が高くて白いのを食べたいけど……」と妻が言った。ワーオ、もう釣りを開始してる! コリーンはちょっとニヤッとした。その目ヂカラ充満の茶色い目がウェイトレスの心を射抜いたのか、彼女は女子高生のようにケラケラ笑った。注文を受け付けるノートパッドとペンの扱いがぎこちない。彼女は気づいていないだろうけど、君のデニムのショートパンツの中に隠れているおまんこは、もう僕の妻のモノになっているんじゃないかな。 「僕は、強めのブラックを、ロングで」と言った。すでに顔を赤らめてる彼女に、さらに意味深なことを言って困らせないようにしようとしたけど、思わず口から出てしまった(言いたかったことは、濃い目のコーヒーを注文したかっただけなのだが)。 「分かりました。すぐにお持ちします」と彼女は言ったけど、多分、しなくちゃいけない仕事を思い出そうとしたフリをしたんじゃないかと。本当は、妻の巧みな指にトロトロに溶かされるのを想像していたんじゃないのかな。
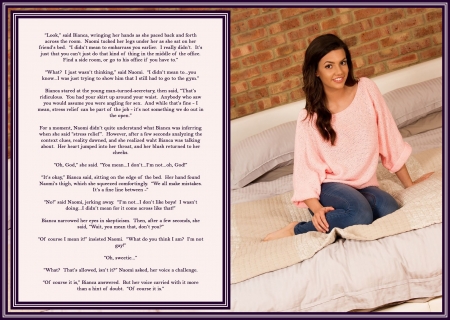 Sissy Secretary 13 「シシー秘書13」 「ちょっと聞いて」とビアンカは、部屋の中を行ったり来たりしながら、神経質そうに両手を揉んだ。ナオミはビアンカのベッドに腰を降ろし、両脚を畳んだ。「さっきはあなたに恥ずかしい思いをさせるつもりはなかったわ。本当よ。ただ、ああいうことはオフィスの中ですることじゃないということ。誰も来ない小部屋を探すか、どうしてもというなら、彼のオフィスに行くべきなのよ」 「何のこと? あたしは別に……」とナオミは答えた。「別にそういうことをするつもりじゃ……分かるでしょ?……もっとジム通いを続けなきゃってことを彼に示そうとしていただけなのに」 ビアンカは秘書に変身した若者の顔をじっと見つめ、そして言った。「そんなの変だわよ。あなたは腰までスカートをめくり上げていたのよ。そんなあなたを見たら誰でも、あなたはセックスをそれとなく求めていたと考えるわ。それに、そのこと自体は問題ないけど……って言うか、ストレスを和らげてあげることもあたしたちの仕事だから……だからと言って、ああいうことは、ひとの目があるところですることじゃないの」 ナオミは、しばらくの間、ビアンカが「ストレスを和らげる」と言った時、何を言わんとしているのか理解できなかった。でも、文脈を手掛かりにちょっと分析した後、突然、現実が見え、ビアンカが話していたことを悟ったのだった。その瞬間、心臓が喉から飛び出そうになり、頬が真っ赤に変わった。 「な、何てこと……まさか……そんな……あたしは、そんな……ひどいわ!」 「いいのよ」とビアンカもベッドに腰を降ろした。手をナオミの太ももに置き、なだめるように優しく揉んだ。「誰でも間違いはするわ。ふたつのことの区別は微妙なところがあるし……」 「いや!」とナオミはビアンカの手を振り払った。「あたしは……男になんか興味ないわよ! そんなつもりじゃなかったんだから……偶然、ああなっただけで、考えてしたわけじゃなかったんだから!」 ビアンカは疑っているように目を細めた。そして、ちょっと間をおいた後、口を開いた。「ちょっと待って。本気で言ってるの?」 「もちろん本気だわ! あたしを誰だと思ってるの? あたしはゲイじゃないわ!」 「まあ……」 「何? それって許されているんじゃない? 違う?」 ナオミの声には挑みかかるような調子がこもっていた。 「もちろん許されているわ」とビアンカは答えた。だが、その声には、疑っている調子が少なからず漂っていた。「もちろん、許されてるわよ」 If you like this kind of stories, please visit Nikki Jenkins' Feminization Station https://thefeminizationstation.com/home/
ちょっと脚を開いて、スカートの中に手を入れた。ちょっとめくりあげて、鏡の中の自分を見て、「あっ」と思わず声を出してしまった。だって、股間の生地からあそこの唇がはみ出していたから。しかも濡れてる! 人差し指を伸ばして、布地の割れているところに沿って撫でてみた。指にトローッとした湿り気がくっついている。その濡れた指を唇に近づけ、お口を開いた。そんな自分の姿を鏡で見ていたら……電話が鳴った! びっくりして跳ね上がり、素早く手を戻した。またベルが鳴る。 「んもうッ!」と、突然、邪魔され、不満げに叫んだ。 そして、またベルが鳴る。止まりそうにない。仕方なく、電話に駆け寄り、受話器を取った。 「もしもし!」 イライラした声になっていた。 「ケイト? あたし、ベティです」と若々しい声。 ベティ? あ、あのセックスショップの若いセクシーな店員さん! 「あら、まあ、ベティ。調子はどう?」 体が興奮しているのを隠そうと、わざと明るい声をだした。 「いいわよ。あなたとクリスティはどうしてるかなって、ちょっと気になって電話したの」 「まあ、ちょっとお家のお掃除をしたり、クローゼットの整理をしたり。まあ、そんなところ。クリスティは友達のところに遊びに出かけているわ」 嘘をついた。でも、いま、何か使って自分でアソコをいじろうとしてたなんて、言えっこないし。 「それは退屈ね!」 まさに核心を突いた返事! 「良かったら、お店に遊びに来ない? 今、積極的に紹介してる新製品があるの。あなたに手助けしてもらったら、楽しいことができるんじゃないかって。あたしが仕入れたモノ、ぜひあなた見てもらいたくて」と彼女は笑った。 ベティの笑い方、大好き。メロディがついてるように聞こえるし、幸せな気持ちを振りまく感じで、心を惹きつける。 「モノ? どんなモノ?」 急に好奇心がくすぐられてしまう。 「まあ、店に来て、ちょっと見てみて。絶対、気に入ると思うから」 ベティが「モノ」と言ったものは、アダルトグッズ以外にあり得ない。こんなに興奮して、しかもひとりでいる今の自分にとって、まさにアダルトグッズこそ、欲しいモノだった。 「ああ、面白そうね。じゃあ、30分くらい待ってて。すぐに行くから」 注意して、落ち着いた声で返事するようにした。でも、心の中ではすでにものすごく興奮していた。 「嬉しい! じゃあ、待ってるわね」とベティは電話を切った。 あたしこそ、嬉しい! ジョンや息子が帰ってくるまで性的な飢えをしのぐための自分専用の道具を手に入れるわけね! 鏡を見て、にっこり微笑んだ。この格好で出かけたら、どうなるかしら? すごくセクシーだし、胸がやっと隠れているドレスだから、確実に、すれ違った人たちに振り向かれるわね。鏡の中の自分にうっとりし、偶然その場に居合わせた男性を焦らすことになるかもと期待しながら、あたしは家を後にした。 ベティのお店に向かう途中、ちょっと引っかかっていることがあって、それを考えていた。ベティは「今、積極的に紹介してる新製品がある……あなたに手助けしてもらったら……」とかと言っていた。それってどういう意味だろう? 紹介しているって、誰に? 商品を買ってくれそうなお客さんのこと? それに、あたしの助けって、どんなこと? 急に、このドレスを着てきたことが、そんなに良いこととは思えなくなってしまった。お店に男性がいたら? しかもたくさんいたら、どうなるだろう? うつむいて自分の胸元を見た。胸の盛り上がった肌が丸見え。乳首にギリギリ近いところまで見えてるし、谷間も乳房の下まで見えている。さらに、その先の脚へと目を落とすと、こっちも、すごく露出していた。運転席に座ってる姿勢だと、股間からはみ出してるあそこの唇まで見えてしまいそう! 「ああ、どうしよう」と心配しながら、ベティのお店の駐車場へ車を入れた。
スペルマを舐めとったり、それを口移しで交換したり、キスしたり、揉んだり、口のものを飲み下したり。あたしたちはずっとそんなふうなことを続けていた。部屋には、3人のズルズル啜る音が響き、スペルマの臭いが立ち込め、そして何よりも興奮した熱気がムンムンしていた。3人でする、このイヤラシいお清めの行為がいつまでも終わらないかのよう。でも、どうしても、やめたいという気持ちにならない。それでも、とうとう、溜まっていたモノが少なくなってしまい、ようやくウェンディとあたしは最後のキスをして、互いに、口の中のものを飲み下した。体は涎れでテカテカになっていたけど、もう、しずくがぽたぽたすることもなくなっていた。体じゅうベタベタ。それに、信じられないほどエッチな気分。 ここでお終いにしたくなかった。もっと何かエッチなことをしたい。今は、ベッドに、あたしを真ん中に、左右にウェンディとジーナが座っている。でも、どっちかというと、ジーナの方が脚を大きく広げている。それを見て自然とどちらを選ぶか決まった。 あたしは素早くベッドから立ち上がり、くるっと回って、ジーナの脚の間に正座した。素早い動きだったので、ジーナはほどんど反応する隙がなかったみたい。あたしは、その位置につくと、両手で女の太ももの内側を押して、さらにもう少し、脚を広げた。 目の前にはジーナの大きなおちんちん。まだ、そそり立っていて、その根元からバギナ、そしてアヌスにかけてのところがヒクヒク動いてる。今にも爆発しそうになっているみたい。それにしても、本当に綺麗。そばかすがあるところが特に素敵で、そのおかげでとてもキュートで女性的に見える。同じことがまん丸のふたつの可愛いタマタマにも言える。幼い女の子が着るようなすごく丈の短いTシャツ。スペルマでベトベトになっているそのシャツを中から持ち上げてる大きな胸。それと並べて見ていると、このおちんちんもタマタマも、やっぱり女の身体についているものなんだなって納得できる。 でも、いつまでも、こうして惚れ惚れと眺めている気はなかった。このおちんちん、どうしてもあたしの中に入ってもらわないと、居ても立っても居られない。 顔を前に突き出して、口を開いた。ジーナは、そんなあたしを見ていたけど、何が始まるのか分からないのか、いぶかしそうな顔で固まっていた。 涎れを垂らしながら顔を前に出し、彼女のおちんちんを口の中に入れた。口を大きく開いたまま、できるだけ唇がおちんちんに触れないようにしながら、顔を突き出した。先端のところが喉の奥に触れた後も、構わずどんどん中へと飲み込んだ。嚥下反応を引き起こす場所に来て、あたしの喉の筋肉は彼女をぎゅっと引き締めた。オエッとなりそうなのを堪える。目に涙が溜まってきた。喉を塞がれたまま、唸り声をあげた。おちんちんの竿の底辺のところが舌に触れている。少し塩辛いけど、ベルベットのような舌触りがした。 昨日、ウェンディにしてもらったことだし、ポルノ動画で何度も見たことだけど、あたし自身は、これをしたことがなかったので、自分でしてて、これが本当に正しいやり方なのか、自信がなかった。でも、昨日ウェンディがしてくれた時、これがどれだけ気持ち良いことかは知っている。 口で優しく包むように、いっぱい涎れを出しながら、ゆっくりと頭を上下に動かし始めた。あたしの鼻が彼女のお腹の柔肌に埋もれている。鼻から息を吸うと、ジーナの香りで頭の中がいっぱいになった。舌先は彼女の陰嚢に触れていて、小さなタマタマを舌先で転がすのがちょっと楽しい。 少し吸い込んでみたけど、大半は、唾液をたっぷりまぶすのと、喉の筋肉で締め付けるのと、舌先でタマタマやその下の女のビラビラを撫でることに集中した。昨日、ウェンディがあたしに実演してくれたように。 ウェンディのことを思い浮かべたけど、そう言えば、あたしの視界に彼女がいなくなっていた。でも、代わりに彼女があたしに触っているのに気がついた。左右の手であたしの腰を掴んで、自分に引き寄せている感じだった。 ウェンディは何をしようとしているんだろう? でも、あたしの方は、夢中で、ジーナのしょっぱいおちんちんを咥えこんで、舌でタマタマを転がし続けていたので、ウェンディが何をしてるのか確かめる気にならなかった。すると今度は、お尻を持ち上げられるのを感じた。 今は、顔は下に向けているけど、両脚は伸ばして立っている姿勢にされていた。腰のところで曲がって直角を作ってる形。ウェンディは、あたしをジーナのおちんちんから引き離そうとはしていない。もっと言えば、この姿勢のおかげでジーナの棍棒があたしの喉のさらに奥まで入って来るという、嬉しい副作用が生まれていた。喉はすっかり塞がれてる。一方、お尻は高々と掲げられていて、ウェンディは、あたしのお尻の頬肉を左右に広げながら、おしりの穴を指でこねているのを感じた。
私は引き続きアンドリューに質問した。「さっき、あなたは、その新しいOSとかいうの、売り出したいモノのひとつだって言っていたわよね? ということは、もうひとつは何?」 「それは今夜、もう少ししたら見ることになるよ。30分くらいで、デモを見せられると思う」 まあ、そうね。2つ目の製品を見てみたら、ひとつ目の製品の価値についてヒントを得られるかもしれない。 今度はエマに顔を向けて訊いた。「エディとイディが何をしてるかは分かったわ。それに、エレは財務関係を担当ということよね? でも、エマ、あなたはどんなことを計画してるの?」 「アメリカ合衆国の大統領になるつもり」 私は笑い出した。「まあ、小さな女の子にしては、すごく大きな夢ね」 アンドリューがちょっと苦笑いした。「いや、その子にとっては、そんなに大きな夢というわけじゃないよ」 エマは父親に笑顔を見せた。「年齢制限を変える方法を見つけたらだけど、大統領になれと言われたら、次の選挙でなれるわ。共和党は、自分たちだけがタッチスクリーンの投票装置を設置できると思ってるけど、いずれ、あの人たちびっくりすることになるんじゃないかな」 私は愕然としていた。この子が大統領? 投票装置の設置って、何の話しなの? 奥さんのひとりが口を挟んで、この話題を止めさせた。「エマ? ディナーでは政治の話しはしないってことになっているでしょ?」 「ベッドでもね。そっちのことは忘れたの?」とエマが口答えした。 アンドリューもエマの話しはもう充分だと思った様子だった。「まあ、それでディナーは終わりってことになるかな? じゃあ、デザートの代わりに、ポップコーンとジュースを手に映画でも観るっていうのは、どうかな?」 映画 ジェイクと私は奥の部屋へと移動した。アンドリューとふたりの妻たちは、食卓の後片付けをしている。Eキッズたちも、それぞれ、後片付けで担当する仕事があるようだ。 ジェイクと一緒にカウチに腰を降ろした。この部屋は、多人数に対応できるようになっているのは明らかだった。この家族は大家族なのだから。ジェイクとは、ここに来てからほとんど会話をしていなかった。もちろん、私は、彼の話しに興味がないわけでは決してない。
≪前ページ | HOME |
次ページ≫
|
