 69 Control 「コントロール」 彼のためなら何でもする。 あたしは、どうしてもそうしてしまう。そして彼もそれを知っている。彼があたしをそういうふうにしたのだから、当然と言えば当然。彼があたしのすべてをコントロールしている。あたしは彼の遊び道具、彼のおもちゃ。そして、あたしも彼もそれを知っている。 以前の生活をほとんど思い出せない。ちょっとでも詳しいことを何とか思い出せたとしても、その記憶は夢を見ているようでぼんやりしている。フットボールの試合からチアリーダーのトップの女の子とのデートに至るまで、記憶の中に出てくる若い男が誰か認識できない。彼は強く、自信に溢れている。彼は男である。 今のあたしは、そのいずれの特質にも欠けている。 時々、誰かと認識できる人にも会うことがあるだろう。昔のガールフレンドかもしれないし、チーム仲間かもしれない。以前のコーチのひとりかもしれない。誰であれ、関係ない。彼らは顔に偏見に満ちた表情を浮かべているのが見える。彼らは嘲りの冷笑を隠そうとすらしない。そして、そんな彼らの気持ちもあたしには理解できる。あたしは男としてすべてを手に入れていた。そして、彼らの目には、あたしはそのすべてを投げ捨て、シシーになってしまったと映っているのだろう。 時々、彼らが真実を知ってくれたらいいのにと願う時がある。あたしには選択肢がなかった。彼はあたしから選択肢を奪うことに特に注意したのだ。その方法が、催眠術なのか、魔法なのか、何か他のことなのか分からない。でも、あたしには彼の指示を断ることができない。あたしは彼が言うことを行わなければならない。彼があたしに望む存在がどんな存在であれ、あたしはそんな存在にならなければならない。 しばしば、彼はいつかあたしを解放してくれるのだろうかと思うことがある。あたしの他にも若い男性や女性が加わって来ては去っていった。その人たちの誰も、あたしほど彼の関心を惹きつける人はいなかった。あたしは彼にとって初めての人だったのだ。だから、認めたくはないけれども、心の底では、彼はあたしを決して自由にしてくれないだろうと思っている。あたしは今のような人生を送るよう運命づけらえれている。彼の奴隷でい続けるよう運命づけられている。 最初、自分でもそうなるのも当然だと思っていた。彼があたしにパワーを行使し始める前は、あたしは彼にとって恐怖すべき人間だったのである。あたしは彼をイジメ続けた。情け容赦なく。しかもあたし自身に何か根深い精神的問題があったからでもなかった。家庭で虐待されていたわけでもない。あたしは、単に、あたしがすべてをコントロールしてると誰もに納得させたかっただけ。自分が望むことは何でもできると示したかっただけだった。 多分、彼はとうとう限界に達し、キレたということだろうと思う。そう思うし、そんな彼の気持ちは理解できる。あたしは過去の自分の行為を後悔している。過去の自分を憎んでいる。でも、だからと言って、あたしの今の待遇に値することにはならない。一生、彼の奴隷としてすごすことに値することにはならない。 とは言え、前にも言ったように、あたしにはこの件について選択肢がないのである。彼がすべてをコントロールしている。そして、彼はしたいことは何でもできるのである。
 69 Combination 「コンビ」 「正直言って、あなたが思ってるより簡単だったわ。催眠術的な暗示を何度かと、時折ちょっと背中を押して、たくさん女性ホルモンを与えたら、簡単に女性化にハマって来たのよ」 「彼は、父親に見放されたことも助けになったのじゃないか?」 「それもあると思う。でも、あたしたちは、それは別に計画してなかったわね。そのことが、あたしたちにとって正しい方向に彼を押す、ナイスなひと押しにはなったけど、でも、それも全部あの男のせい。あいつは、自分の子供が立派で自立した息子じゃなくて、トランスジェンダーの娘だという恥が耐えきれなかったってわけよ」 「あのバカ。当然の報いだよ」 「父親のこと? それとも息子の方?」 「両方? ただ、願いはひとつ。上院議員がまともな娼婦になるには歳をとりすぎているってわけではないことだけ」 「女体化したあの男にも、おカネを払う人はいると思うわ。念のため言うけど、別にルックスがいいから払うっていう人じゃないわよ。親父の方が、ここにいる息子みたいなルックスになるなんてありえない。でも、珍しさという売りがあるの。考えてみて、あの男みたいなヤツがよ? 平身低頭して、あたしを買ってくださいって懇願するのよ? それだけでも、充分、売りになるわ」 「僕には、相手できそうもないな」 「でも、ゲテモノみたいなルックスになるってわけでもないわ。あたしたちにも完成体について一定の基準があるの。それにあたしたちの医師たちは信じられないほど有能。だから、なんとかなると思う」 「それにしても、僕たち、本当に僕が話し合ってると思ってる人物について話し合ってるのかなあ? アメリカ合衆国の上院議員を女性化しようってことだよ? 政治家としてのキャリアの大半を、ゲイとレスビアンの権利を否定することに費やしてきた人間のことだよ?」 「差別主義者こそ、最高の淫乱になるものなの。適切に調教されたらだけどね」 「本当にできると思ってるのか?」 「できるわよ。すでに、彼くらいの年齢の非道な夫たちを何人も女性化してきたもの」 「ふたりをペアにして売ってもいいな。父と息子ってペアで」 「奔放すぎる淫乱コンビ。それいいわねぇ」 「そうしよう。何が必要かな?」 「まずは、議員のコンピュータへのアクセス。それが手に入ったら、さっそく今夜にでも、催眠の暗示をパソコンに仕込むわ」 「その手のことに詳しいヤツを用意しよう。こいつは面白くなりそうだ」 「何度やっても面白いわよ」
 69 Check 「チェック」 自分がいかに不幸だったか、あたしは全然知らずにいた。毎日、しなければならないことのリストにチェックして日々を過ごしていた。もっと良い人生があり得るなどまったく知らずに。朝起きて、箱にチェック印をつける。歯を磨く。チェック。シャワーを浴びる。チェック。仕事に出る。チェック。そんなふうに進行し、毎日が日常のルーティンをこなす作業になっていた。 かつて、あたしには夢があった。目標。野心。お金持ちで有名人になりたかった。家族を持ちたかった。子供たち。郊外に2階建ての家。飼い犬。それらが本当の自分の夢ではなく、自分が持つべきと周りから思われている夢にすぎないことを知る由もなかった。でも、それらの夢の背後には、自分でもうまく名付けることができない欲望が隠れていた。それが何であるか自分でも認識できない望みが。 自分がトランスジェンダーだと知らなかったと言ったら、信じられないと思われるだろう。でも、あたしは、それまでの人生の大半を、そういうことをひとつも知らずに生きていたことを理解してほしい。自分には、そういう感情があって、心の中で膨れ上がってきているというのは知っていた。兄たちと秘密基地を作るよりは、姉たちと人形遊びをしたかった。でも、そういうことを求めるものではないと思われていることも知っていた。だから、あたしは、無理強いして、その感情を無視したのだった。 学校に通う頃になると、事態は、同時に、容易にもずっと困難にもなった。あたしは、他の男子たちがどういうふうに行動するかを見て、それを見事に真似るようになった。誰もあたしの本当のところを知らない。それに、正直言えば、あたし自身、自分の本当のところを一種忘れていたと言える。自分の本性を無視することなんて、充分に長い間、別の存在のフリをし続けていると、皆さんが思っているより容易なことだと思ってる。 でも、思春期になり、その思春期というものがその醜い頭をもたげてくると、問題の大群を一緒に引き連れてくる。急に、それまでずっと自分の友だちと思っていた男の子たちが何か別の存在のように見えてきた。もちろん、あたし自身には、それが認識できなかった。どうして自分は? 男の子というものは女の子に惹かれるものだ。そうだよね? なのに自分は? しかし、しばらく時間をかけ、自分はやっぱり他の男子と同じなのだと自分自身を納得させた。でも、本当は違うのだ。そのことが何より明らかになるのが、体育の授業の後のロッカールームだった。今でも、時々、ロッカールームの夢を見る。あの時、自分が本当のところしたかったことの夢。あまりに恐ろしくて、とても口に出して認めることなどできなかった、自分がしたかったことの夢。 高校卒業後が、あたしが本気で毎日を否認の連続で埋めるようになった時だった。毎日、あたしはチェック・ボックスにチェックマークをつけて、自分が本当になりたいと思ってる姿を無視しようと努力したのだった。それは不毛な努力だった。というのも、夜遅く、独りになると、あたしはパソコンの前に座り、本当の裸の自分になる日々を送っていたから。それは妄想のレベルで止めるべきだったと思うし、実際、止めていたかもしれない。今のご主人様に出会わなかったら。 始まりは、ただのメールの交換だったけれど、そのメールで、彼は、徐々にあたしに女性化への階段を登るよう挑み続けてきたのだった。最初は、仕事に履いていくスラックスの下にパンティを履くこと。でもすぐに、それはもっと他のことへと拡大していった。そして、気がついた時には、あたしは完全に女装して、至福の穴( 参考)の前にひざまずき、生まれて初めてフェラチオをしていたのだった。それこそ、自分がなりたいと思っていた存在だった。 それでもまだ、それはあたしの生活の影にとどまっていたのだけど、ある日、彼がたったひとつ、単純な質問をしてきた時、それが変わった。その質問とは、「なぜ?」のひとこと。どうしてあたしは男性としての生活をして自分自身を苦しめ続けているのか? 自分は誰を喜ばしてあげたいと思っているのか? 誰に良い印象を与えたいと思っているのか? それらの質問に答えを出せずにいた時、自分の進むべき道が痛いほどはっきりと見えたのだった。 そして、あたしの日々のチェック・ボックスは変わった。ホルモンは? チェック。友人や家族にカミングアウトは? チェック。新しい服は? チェック。男性とデートは? チェック。女性になること? チェック。 幸せでいる? チェック。
 69 Blissful 「至福」 「その調子、いいわよ」と妻が猫なで声で言った。「この大きいおちんちんの上に乗るの」 彼女の顔面に唾を吐きかけ、断固拒否し、さっさと服を着て、ドアを出て行きたかった。でもできなかった。あたしがそれをできないことは、自分でも分かっているし、妻も分かってる。そして妻の彼氏も分かってる。 「いいぞ、ウォルター」と彼はペニスの根元を握った。「こいつ、デカいだろ。遠慮せず、喰らえよ」 「彼をそう呼ぶのはやめて」と妻が言った。「もう、その名前じゃないんだから」 「俺にとっては、こいつはいつまでもウォルターだぜ」と彼はあたしの体を上から下まで見ながら言った。他の何より、自分の裸体を隠したかった。女体化してしまったこの体を隠したかった。でも、抵抗は不可能だと分かっている。 「彼がこんな体の今でも、あのウォルターに見えるの?」と妻はあたしのウエストに腕を絡めた。お腹のあたりを愛撫しながら、あたしの耳に囁きかけてくる。「違うわよねえ?もう、ジャスミンと呼ばれる方がいいわよねえ? あなたもそう呼ばれるのが好きなのよねえ? そうでしょ?」 「は、はい。そうです」 その言葉が口から出るのを必死でこらえようとしたのに、そう返事してしまう。自分がいまだに抵抗しようとしてるわけが自分でも分からない。この1年にわたって、一度も勝利したことはなかった。カラダも、魂も、心も何もかも、このふたりに女性化されるがままになってきたのだ。激しく抵抗すればするほど、より悪い結果になってきた。 「それで、あなたもやっぱり、彼のおちんちんを入れたいんでしょ? ずんずん突いてもらいたいんでしょ? 違う?」 あたしは頷いてしまう。「そ、そうなんです……」 そうされたい欲望が体の中、ふつふつと湧き上がってくるのを感じる。そうなる自分が憎くてたまらないのに、彼に入れて欲しくてたまらなくなる。その肉欲、それは無視できない。だから、これまで通り、あたしはいつものことをしてしまう。つまり、屈服してしまうということ。 彼の上に乗った瞬間、気持ちが軽くなるのを感じた。そして、彼の長くて太い肉棒へと体を沈めるのに合わせて、あたしは、自分がかつてどんな男であったか、すべて忘れていく。それが一時的なことであるのは分かっている。でも、この行為をする何分間かは、あたしは、すべてを忘れ、至福の時に浸る。
 69 Blackmail 「脅迫」 ドアの前に立ち、セスは深呼吸をし、ボロボロの神経を落ち着かせようとした。でも、その効果はなかった。とは言え、彼は深呼吸したからと言って落ち着けるとも思っていなかったのだが。 ノックをせずに彼はドアノブを回し、そのホテルの一室に入り、後ろ手にドアを閉めた。そこまでの動き、彼はほとんど自覚なしで行った。そして、目的をしっかり持って、自信満々の様態で前に進んだ。実際には、そんな自信などひとかけらもなかったのだが。部屋の中央まで来て、彼はようやく部屋の中を見渡せる余裕ができた。 そのホテルの一室は、エレガントな室内装飾が施された豪華な部屋だった。ペントハウスのスイート・ルームにふさわしい室内だった。だが、彼の意識は、目の前のカウチに座る男にしか向けられていなかった。セスは、彼と目を合わせながら、肩をすくめ、着ていたロングコートを自然に床に落ちさせた。そして、ほとんど裸に近い体を露わにした。床に落ちたコートを脇によけながら、何のためらいもなくパンティも脱ぎ、横のコートに放り投げる。そして、最後に、ブラを外し、小ぶりの乳房を露わにした。腰を横に突き出し、彼は、脱いだブラを脇にぶら下げた。そして、自分の人生を破滅させようと脅かしている男と対峙した。 「あんたが見たかったのはこれでしょ、ウォルター?」 とセスは言った。その声には責めるような調子がこもっていた。 一方のウォルターは、あんぐりと開けた口を閉じることすらできず、ただ座ってセスを見ていた。明らかに圧倒されている様子だった。「俺は……俺は知らなかった……なんてこった……」 「あんたはあたしの正体を知っていた。だからあたしにこんなことをさせたんでしょ? 次は何? あたしにあんたのちんぽをしゃぶらせるつもり? あたしと一発やりたい? それとも脅迫のための写真を撮るだけ?」 「俺は……本当に……こんなこと、予想できたはずがなかった……」 「じゃあ、あの脅迫は何なの? 言われた通り、あたしはここに来た。あたしの秘密をしゃべらない限り、あたしはあんたが望むことを何でもするわ。それがお望みなんでしょ?」 「あ、あれは……ただのジョークのつもりだったんだ」とウォルターは言った。「ただの倒錯的な遊びとかそんなことだと思ってたんだ。変わったロールプレイと言うか。俺は本当に知らなかったんだよ……」 「あたしがトランスジェンダーだということを? あたしがカミングアウトしてないのは、ロンが途方もない性差別主義者の偏見の塊だからということを? もし、ロンが知ったら、何か他の理由をでっち上げてあたしをクビにするのが見え見えだからということを? ……ええ、確かに、あんたは、あたしを脅迫してきた時、そんなこと知らなかっただろうとは思ってるわ」 「俺はただ……こんなこととは……誓ってもいいよ、セス。本当に知らなかったんだ。君がちょっと風変わりなことにハマりこんでるなあと思っただけなんだよ。ああ、確かに、俺はそれを利用して君を蹴落とそうと用意していた。でも、君だって同じ立場だったら、俺に同じことをするだろ? だから、その点については俺は謝らない。だけど、こうなると……これだと、話しが変わってくる」 「どんなふうに?」 セスは、ライバルのウォルターが急に風向きを変えたことに少し戸惑っていた。 「俺は、人のフェチを利用してそいつを攻撃しようとする人間だ。だけど、これが君の正体だとすると、俺はそういうのに関わる気はないんだ」 「ということは、そこがあんたにとっての一線ということ? ふーん?」 「ああそうだ。そこは俺にとっての越えられない一線だ」 セスは長い時間、ためらい続けた。そしてようやく口を開いた。「これからどうしろと?」 「服を着て、部屋に戻ってくれ。そして、ふたりとも、今日のことは忘れることにしよう」 「それって……何か……良識的にすら聞こえるけど?」 「おっと、俺はこれからも君を攻撃し続けるつもりだよ。あの昇進は俺がいただく。別の方法でね。だけど、俺に関して言えば、君のジェンダーの件は立ち入り禁止だ。俺はあの差別主義者の元で働くだろうけど、だからと言って、俺も差別主義者にならなくてはいけないってことじゃないからね」
 69 Bimbo 「エロ女」 だって、エロ女でいる方が男でいるよりずっと楽しいんだもの。
 69 Be Careful What you Wish for 「望むことには注意して」 「そんな目で見ないで。そんな顔しても、何も変わらないわ」 「こういう顔でいた方が気分がいいんだよ」 「あなたって、時々、子供になっちゃうんだから。それ、分かってるでしょ? あなた自身も?」 「ジョシー、ボクは未熟な子供じゃないよ。あんな連中を招待することなんかなかったのに」 「あたしは、あなたがこの恥辱プレーっぽいことに興奮してると思っていたけど? それが、これを始めた時にあなたがあたしに言ったこと。あなたは、モノのように扱われるのを想像して興奮していた。みんなの目の前で辱めをうけることとか。あなたが、あたしに女性化するのを頼んだのよ? あたしが考えたことじゃないわ」 「でも、ボクの友だちをパーティに呼ぶなんてことは頼まなかったよ。パーティに出たら、ボクは裸で飲み物を渡しながら歩き回るんだろ? その間、ずっと体をベタベタ障られ続けることになる。それに、もし誰かがヤリたいと思ったら……」 「当然、あなたはその人に抱かれることになるかもね。ええ、そうよ。それも招待状に書いておいたもの。それに招待状には新しいあなたの写真も添えておいたわ。あなたとソレをすることだけの目的で来る人がたくさんいるんじゃないかしら。賭けてもいいわ」 「冗談言ってるの? ああ、もう。ボクはめちゃくちゃになってしまうよ。ボクには、そんなことできっこない……」 「落ち着いて。思い出してよ。これこそ、あなたが望んだことなのよ?」 「そんなことない……これはやりすぎだよ。ボクはこんなことしたくない。パーティは中止にして」 「まあ、それは無理でしょうね。お客さんたち、もうすぐ来るもの。それに、あたしは、せっかく来てくれたお客様たちに、メインの見世物の主人公が気持ちが冷めてしまいました、なんて言いたくないわ。第一、あなたはこういうこと、もうすでにヤッタことあるじゃない?」 「あの時は、相手は知らない人たちだったんだよ!」 「ただ、羞恥感に意識を集中させればいいのよ。恥辱感に。それが溜まらないほど大好きなんでしょ? それに、みんなが集まったら、あたしはちょっとアブナイ賭けに出て、あなたは何も考えていられなくなるでしょうって宣言するつもり。その途端、あなたは忙しくなるわよ。……いろんな仕事をしなくちゃいけなくなるから」 「そんなのできない……」 「あら、お客様が来たみたい! さあ、可愛い顔になって! ショータイムよ!」
 69 All Woman あなたには、私が男に見える?
 69 A Video 「動画」 ダニエルは、乳房があるわけでもないのに反射的に胸を両手で覆った。それを見て彼のガールフレンドのハンナはクスクス笑った。ダニエルは両手を脇に動かした。 「うるさいなあ」 だが、その声も甲高い声で、まるで、10代の女の子がちょっとふくれて文句を言っているようにしか聞こえなかった。 「もう、すっごくキュート!」 ハンナはそれしか言わなかった。それに、ハンナは彼が困ってるのを見て、笑ってしまうのを堪えようとしていたけど、そして実際、大半は隠せていたけど、完全に堪えきることはできず、どうしても笑みが漏れてしまうのだった。 彼は今すぐこの場で、頭からウイッグをかなぐり捨て、顔から化粧を洗い落とし、こんな茶番を辞めたいと思っていた。でも、彼にはこうするほか道はなかったのである。すでに、同意していたし、ハンナの気ちがいじみた計画に従わなければならなかったのだった。唯一、気休めとなっていたのは、これはすぐ終わること。たとえインターネットにアップされて永遠に残ることになるとしても、撮影自体はすぐに終わると。 「こんなことで、あのチャンネルを救えると、マジで思ってるのか?」と彼はハンナが運営しているユーチューブのチャンネルのことに触れた。ハンナは、そのチャンネルで主に化粧に関するチュートリアルを配信していたのである。「男が化粧するところなんて、どんな人がみるんだ?」 彼は自分のことを「男」と言って内心、忸怩たる思いだった。彼は男なのだ。どんなことがあっても、その事実は変わらない。 「あたしなら、その質問であなたが言いたいことと、まったく同じことをそのまんま言うわ。あなたに見せた他の動画、見たでしょ?」 「でも、あれは全部、化粧するところだけだったよ。あの男たちは、別に、何と言うか……女の子の服なんか着てないし……」 「あの人たちは外出しないから」と彼女は言った。「アイデアの肝心なところは、あたしがあなたをすごく綺麗にして、誰も、あなたが女じゃないって思わないようにすることなの。と言うことは、あたしたち、ちゃんと外に出て行かなくちゃいけないってこと。だから、さあ、もう着替えて」 「でも……」 「え、ちょっと待って。まさか、尻込みしようとしてるんじゃないでしょうね? これがあたしにとってどんだけ重要なことか、あなたも知ってるわよね?」 「ボクはただ……と、友だちに見られると……それは、ボクとしては……何と言うか……」 「あれぇ? ちょっと待って。あなた、勃起してる?」とハンナは、彼のどう見ても小さなペニスを指さして訊いた。彼は真っ赤になった。そしてハンナはそれを見て、満面の笑みを浮かべた。「ほんとに立ってる! すっごく、可愛い!」 「そんなことないよ!」と彼は言い、股間を隠した。「ぼ、ボクはいつも……これはただ……これは普通の状態の時の大きさだよ!」 「どう見ても、そうじゃないようだけど? ちょっと知りたいことがあるの。ちゃんと聞いて、ダニエル。今のその格好が好きになっても、全然、構わないの。あたしも、しばらく、可愛いガールフレンドがいるっていうの、一種、とてもワクワクしてる気持ちなの。それ、分かって」 「ぼ、ボクはこんなの嫌だよ。本当に」 「そう。いいわ」と彼女は言った。そして、彼の股間に向けて頷いて続けた「でも、彼は同意していないみたいよ。ねえ、これはもう起きてることなの。だから、パンティを履いて、あなたのために揃えておいた可愛いドレスを着て、一緒にダンスに行きましょう。それに、もし、あなたが今晩ずっと良い子でいてくれたら、帰ってきた時、あなたに特別のサプライズ・プレゼントをあげるんだけど?」 「さ、サプライズ? どんなサプライズ?」 彼女はまた笑顔になった。「いま言っちゃったら、そんなにサプライズにならないでしょ? さあ、その可愛いお尻をパンティで包んで。撮影してアップしなくちゃいけないんだから」
 69 A slip of the tongue 「口を滑らす」 「あたしのこと、嬉しいと思ってくれたらいいんだけど。それって、そんなにイケナイこと? あたしって、そんなに普通からズレてる? そうは思わないんだけど」 「嬉しい? お前、マジで言ってるのか? あの女、お前をこんな……ああ、俺は口にすらできねえよ。あの女、お前を、本当のお前とは違うモノに変えちまったんだぜ、アレックス。どうしてそれが分からないのか、オレには分からねえよ」 「あたしとは違うモノ? ふーん。あたしはあたし、前と変わらないけど。正直言えば、変わったのはあなたの方よ」 「俺? 俺って? お前な、何で女みたいにドレス着てるんだ! まるで今から街角に立って男を捕まえに行こうって感じの格好をしてるじゃねえか」 「え、あ、あたしの仕事のこと知ってるの?」 「な、何だって?」 「あ、チッ。いいから……今の忘れて……」 「いやダメだよ。何言ってんだよ。お前はそんなんじゃねえよ。そうだろ?」 「スタン、忘れて。あたしは話したくなかったの。あたしが言ったこと忘れて」 「まるで、お前が実際に本物の娼婦として働いてるみたいに聞こえたぞ! そんなこと、聞き逃すわけにはいかねえよ。お前は俺の弟だ。お前のことを心配してるんだぞ……」 「ありがとう! 本当にありがとう、スタン。本当のことを知りたい? 実は、そうなの。あたしは売春してるの。それを聞きたかったんでしょ? あたしはおカネのために、知らない人のおちんちんをしゃぶってるの。知らない人にアナルをやらせているの。毎晩。それを聞きたかったんでしょ? 違う?」 「なんてこったよ……お、俺は……なんで……なんでこうなった?」 「分からないわ。あたしはただ……何と言うか、始まりは女の子たち。ヘザーとあたしはおカネが必要だった。そしてヘザーは彼女の上司と一緒にこのことを仕組んだわけ。その後は、もう、日常的なことになって。知っての通り、毎晩、違った女たちがあたしのところに来て、泊まっていった。レズビアンの女性たち。みんな、相手が欲しかったのよね。あたしも楽しかったわ。最高とは言えないけど、良かった。でも、ヘザーはもっと儲ける方法を見ていたのよ。相手を男に変えたら、収入を倍増できるって。当然、あたしは抵抗したわ。でも、そうしたら、ヘザーは女の客の予約を断り始めたの。家賃とか光熱費とか、支払期限が迫っていた。そして……とうとうあたしは同意した。その後は転げ落ちるように。男の客は週にひとりだったのが、いつの間にか、週にふたり、週に3人……気がついたら、お客さんは全員、男になっていた」 「なんてこった」 「ええ。でも、おカネにはなるの。それにヘザーが言うには、1年か2年したら辞めてもいいって。そうしたら、何もかも、元通りになってもいいって」 「マジで信じてるのか?」 「もちろん。信じなきゃやってられないわ。信じなきゃいけないの」
 69 A new life 「新生活」 眠りから覚め、ボクはしばたたかせた。すぐに何かおかしいと思った。それが正確になんであるか指し示すことはできなかったが、何かが欠けている。震えるほど恐ろしい事態が起きている感じだった。 「さあ、始まりよ」と聞き覚えのある、独断的な声が聞こえてきた。ボクはすぐに、その声の持ち主はボクの元妻だと分かった。霧が晴れるようにゆっくりと視界がはっきりしてくるのに合わせて、ボクは声の方に顔を向けた。にんまりと笑う彼女の顔を見て、本能的な恐怖心にボクは喉を詰まらせた。前に彼女の笑顔を見たのは遠い、遠い昔だった。そして、その時ですら、彼女の笑顔はボクに向けられたものではなかったのである。 「い、いったい何が?」 ボクは勇気を振り絞って声を出した。すぐに声が変なことに気づく。ボクは咳払いをして、もう一度、同じことを言った。そして、声を出した途端、ボクは両手で自分の口を塞いだ。これはボクの声じゃなかった。声が高すぎる。あまりに女性的すぎる。 それを見て、彼女はいっそう嬉しそうな顔をした。「あなたが最初に何に気づくか、興味を持ってたわ。確かに、声が最初だろうっていうのは一番あり得ると思ってたわよ」 背筋にブルブルと悪寒が走った。元妻の顔に広がる、明らかに悪魔的な表情のせいもある。でも、どうしても震えてしまう要因がもうひとつあった。寒さだ。ボクはほとんど素っ裸で、下着がひとつだけ。それも、膝のところまで下げられていたのだった。 頭の中、ゆっくりと注意力が回復してくるのにつれて、ボクは他のことにも気が付き始めた。奇妙すぎることばかり。胸に感じる奇妙な重み。肩をくすぐる長い髪の毛。マニキュアを塗った爪。でも、ボクはすぐには自分の状況を本当の意味で把握したわけではなかった。下を見て、乳房がふたつ胸に揺れてるのを見るまでは。 それを見た瞬間、ボクは甲高い悲鳴を上げた。その悲鳴は、ホラー映画の新人女優が発するような金切り声だった。 「ぼ、ボクに何をしたんだ?」 乱れた息づかいをしつつも、何とか言葉を発した。 彼女は高笑いした。あの笑い声、とても人間の声には聞こえなかった。「見て分かるんじゃない? あなたを変えたのよ。完全に。後戻りできない形で。昔のあなたは、もう永遠に戻らないわ」 「お、お前……ぼ、ボクは……こんなの可能なわけがない!」 そう言ったけれど、証拠は明らかに彼女の味方をしていた。 彼女は手を近づけ、ボクの頬を軽く叩いた。「あら、でも、この通り、可能なのよ。おカネはかかったわ。難しいことだった。それに、倫理にも反するしね。でも、この通り、完全に可能なの。催眠の部分が一番難しかったわね。でも、それは必要なことだった。あなたは自分自身の意思でこうしてると、すべての人に信じてもらう必要があったから。そして、事実、みんな信じてくれたわ。みんな、あなたが生涯の夢を叶えたって思ってるわよ」 「ど、どうして……なんで、こんなことを?」 「それって、明白なはずだけど? と言うか、鏡で自分の姿を見てみたら明白になると思うけど? あなた、彼女そっくりになってるでしょ? あなたが浮気した、あのアバズレとそっくりじゃない? 顔は完璧にはできなかったわ。手術には限界があるし。でも、充分、似せられたと思ってるわ。それに、あなたの昔のアイデンティティが消え去ったことにも気づくでしょうね。おカネも全部。消え去ってると。今、あなたはただのウエイトレスなの。彼女と同じね」 「ぼ、ボクはこんな……こんなの間違ってる」とボクは自分の新しいカラダを触りながらつぶやいた。自分自身の乳房を抑えながら、柔らかく滑らかな肌に手を這わせながら、ボクは驚くほかなかった。 「そうよ。間違ってるわよ。そんなこと、どうでもいいでしょ。一番いいところは、あなたが本当の自分が何者なのか、誰にも言えないというところ。あなたは、可愛いエロ女のように行動することになる。あの女と同じ。事実、そうなってるしね。でも、明るい面もあるわよ。あなたはもはや忠誠心があるフリをしなくても済むの。誰とでも、ヤリたいと思った人とヤッテいいの。まあ、もちろん、相手は男ばっかりになるでしょうね。最近、女には興味を持たなくなっているようだし。でも、セックスの相手には事欠かなくなったのは事実よ」 ボクは何を言ってよいか分からなかった。誰だってそうなると思う。 「じゃあ、もう、服を着て。仕事に遅れるわよ。フーターズ( 参考)って遅刻に厳しいんでしょ?」
 69_A long summer 「長い夏」 「デビッド、マジで聞くけど。これ、本気?」 「尻込みしようって気なのか? 俺には他の人を見つけられるから、別に……」 「いや! 違うの。ボクはおカネがいるから。ただ、ちょっと、これって何かゲイっぽいなあって」 「ゲイ? こいつはビジネスでの取引だぜ? それ以上の何でもない。性的指向性なんてことは関係ないんだ」 「わ、分かってるよ。ただ、ちょっと……ちょっと、キミはボクと一緒になりたがってるのかなって。何と言うか……」 「お前は俺の彼女のふりをしてるんだぜ? それに、俺たちがセックスしてないってなったら、いずれみんなにバレてしまうもんなんだ。そういうときの人の力を見くびるのはやめたほうがいいぜ。いずれバレちまうもんなんだ。本当だぜ? こんなの、俺も楽しいってことじゃないんだよ。でも、やるべきことはやらなくちゃいけないんだ」 「まさにそこだよ。女の子なら、キミが誰かに声をかけりゃ、すぐにゲットできたと思うんだよ? そういう女の子たちっていっぱいいたように思うけど?」 「なんだよ、まるで俺に彼女を見つけろって言ってるみたいだな。いいか? 俺は、女の子と会っても会話すらできず、全然、彼女なんかできなかったんだ。お前は俺の親友だよな? しかも、俺はお前にちょっと金儲けができる機会を与えてる。なのに、俺に文句を言うわけか?」 「いや、そういうことじゃないんだよ。ボクはただ……ただ、これが居心地が悪いって言ってるだけなんだよ。このウィッグなんか、超ウザいんだ。それに、この脚。こんなつるつるの脚に慣れるなんてできるかどうかもわからない」 「でも、そもそも、お前は毛深いほうじゃなかっただろ? ほら大丈夫だって。俺たちならなんとかできるって。この夏だけやり過ごせばいいんだぜ? 俺と一緒に兄貴の夏の別荘に行く。何回かパーティにも出る。そして皆にお前は俺の可愛いガールフレンドだと納得してもらう。お前は約束のカネをもらえるし、俺は父親の庇護のもとに戻れると。みんなが得をするんだ」 「でも、そんなの本当にうまくいくの? 何と言うか、キミの実家にキミだけで行って何が問題なの?」 「言ったはずだぜ? 俺の父親は俺にちょっと文句があるんだよ。親父は俺を負け犬だと思ってる。ずっと学生寮の部屋に閉じこもってると。俺がすることといえば、部屋の中でずっとゲームをやってると、そう思ってるんだ。でも、俺がガールフレンドを連れて現れたら、親父も俺への評価を変えることになるだろ? それは、とりもなおさず、俺への仕送りが続くってこと。今の車も手放さずに済む。それに大学の学費も今まで通りに払ってくれることになる。単純な話だぜ、ベイビー」 「その呼び方はしないで。それイヤだって言ったはずだよ」 「でも、俺のガールフレンドだったら、違うだろ? ベイビーと呼ばれて喜ぶはずだぜ? 俺とセックスするのが好きなのと同じように。そして、お前は俺のガールフレンドだ。少なくとも夏の間は。そうだろ?」 「ま、まあ、そうだけど……。でも、ちょっとゲイっぽく感じるんだよ」 「お前は今は女なんだよ。当然、女なんだからゲイじゃない。女になり切るんだよ。いいね? 肩の力を抜いて。ひょっとすると、女でいる方が好きになるかもしれないじゃないか」
「ねえ、パパ? パパはもっと家にいるべきよ。家を空けすぎなんだから」とクリスティは言って、両腕を上げて頭の後ろで組む格好になった。リラックスしてるような雰囲気で。 あたしは主人のすぐそばに座ってるから、クリスティの様子がよく見えていた。ただでさえ裾が短いドレスなのに、両腕を上げた姿勢になったから、さらに少し裾がずり上がっていた。彼女のピンクのパンティが見えるくらいまで上がっていた。幸い、娘は両脚を閉じていたから、夫にはパンティの三角部分しか見えていなかったけど。ちょっとまずいなと思って何か言おうとしたけど、あたしが言う前にジョンが口を出した。 「分かってるよ、僕の可愛いカボチャちゃん。……確かに出張で家を空けすぎた」と彼は真面目な声で言った。 夫を見ると、クリスティの股間に視線を向けているのが見えた。彼は、あたしが見てるのに気づくとすぐに視線を反らし、一度、深呼吸をしていた。クリスティの方に目を向けると、口元に小さく笑みを浮かべている。クリスティと目が合ったとき、あたしは素早く「それ、ママは賛成しないわよ」といった表情をして見せた。 「いいわ、パパ。ママはパパがいなくてすごく淋しかったみたいだから、私は引っ込むことにするわ。もうすぐ試験だし、勉強しなくちゃね」と、クリスティは急に真顔に戻って言った。 娘があんなふうに自分の父親を焦らしてからかうなんて! 信じられなかった。いつか、娘にきちんと言い聞かせなくちゃいけないと思った。 クリスティは2階に上がる前に、ジョンのところに近寄って、前かがみになって、頬にキスをした。また夫の目を見てたら、今度は、前かがみになったクリスティの胸の谷間に一瞬、視線を走らせていた。確かに目を奪われるくらいに豊満に成長していて、ミルク色の肌の乳房がはみ出そうになっていたから、見てしまうのは仕方ないかもしれないけど。 クリスティはあたしの方に来て、キスしてくれた。そして、あたしも、どうしても彼女の胸の谷間から目を離せなかった。ああ、もう……でも、本当にツルツル肌で綺麗な形の素敵なおっぱい。 「ドアのこと、忘れないでね、ママ」 そう囁いて娘は2階に上がっていった。 多分、顔が赤くなっていたと思う。だけど、息子とジーナがやって来て、すぐにそちらに顔を向けた。 「僕たちちょっと出かけてくるよ。お帰りなさい。帰って来てくれて嬉しいよ、パパ」と息子が言った。 「ああ、本当だな……私も帰ってきて嬉しいよ」と夫は息子とジーナに手を振った。 「会えて嬉しいです、ジョン」とジーナも言い、ふたりは出て行った。 「ふーう、ようやくふたりっきりになれたね」 と息子たちが出て行ったのを見届けるとすぐに彼は言った。そして、あたしの方に顔を向け、あたしにキスをしてきた。舌を絡ませる激しくて長いキスで、どうしてもアソコからお汁が溢れてきてしまう。 両腕を彼の首に絡めて、彼の瞳を見つめながら囁いた。 「ねえ、あなた? 会えなくてすごく寂しかったわ、だから、あたしがあなたにしてほしいことは、今すぐ寝室に行って、服を全部脱いで、ベッドに入って、あたしが来るのを待っていることだけなの」 夫は目を輝かせ、黙ったまま、すぐに2階へ上がっていった。彼が何かすごいことがあると期待してるのが分かった。実際、あたしはずっとそういう仄めかしをしてきたから、彼もそれを待っている。あたしも同じ気持ちよ、ジョン! 家事をすべて終えた後、あたしは2階に上がり、寝室のドアを開けた。ジョンは素っ裸になってベッドの上、大の字になって横になっていた。しかも、おちんちんをビンビンに立てて。その雄姿を見ただけで、夫があたしがしようとしてることをどれだけ期待してきたかが分かる。それに、その雄姿を見て、あたしの方も興奮で動悸が激しくなるのを感じた。 あたしの視線はずっと彼のおちんちんに固定したまま。そしてベッドの前にあたしは立った。彼はそのあたしを見つめている。ふたりとも無言のまま。 あたしは一度舌なめずりしながらシャツのボタンを外し、乳首がすでにすっかり勃起している乳房を露わにしていった。そして脱いだシャツを部屋の隅に放り投げた。あたしが裸になっていく様子を夫にじっくり楽しんでほしかった。この官能的な女体をしっかり目で堪能して、あたしの体が欲しいって、懇願するまでになってほしかった。 上半身が裸になった後、左右の脇から体の中心に向かって、手を這わせ、胸を真ん中に押し付けながら、左右の乳首をつまんだ。それから、そのつまんだ乳首を、ちょっと痛くなるくらいまで外側に引っ張った。 「うんんんんっ……」 痛さと気持ちよさが混じった声を上げて、乳首を引っ張った後、指を離して、ぶるんぶるんとおっぱいを揺らして見せた後、今度は、両手の指をスカートの腰のところに引っかけて、ゆっくりと降ろし始めた。おへそが出て、女っぽい丸い下腹も見せるけど、まだ、パンティまでは見せていない。 焦らしながら夫の顔を見つめた。彼は目を大きく広げて、あたしのスカートのところをじっと見つめていた。時々、舌を出して唇を舐めている。あたしのあそこを舐めるのを楽しみに待っているように見えた。 ああ、あたしも、今すぐ夫にあそこを舐めてほしい。舌を固くさせて、あそこの奥に突き入れて、溢れ出ているお汁をズルズル音を立てて吸ってほしい。 あたしはジワジワとスカートを降ろし、ちょっとだけパンティが見えるくらいにしたけど、まだ、肝心のあそこは隠したまま。だけど、急に、あたし自身もじれったくなって、スカートとパンティを一緒に脱ごうと決めた。一緒に下へとずらしていく。あそこの毛は完全に剃ってあるので、彼にはあたしの濡れ切ったあそこがはっきりと見えるだろうと思った。 「あなた? あたしのためにおちんちんをこすっていてくれる?」と色っぽい喘ぎ声で言った。 彼はあたしのアカラサマな言葉に驚いたようだったけど、素早く、あたしの言うとおりに肉茎を握って、ゆっくりとしごき始めた。ぐんぐん勃起してくるのが見える。 それを見てるだけで、さらにあそこが濡れてきた。彼のアレであそこを満たしてもらえる期待で、トロトロに濡れてくる。スカートとパンティを一緒にお尻から降ろした後は、手を離したら、音もなく床に落ちていった。 とうとう、あたしは、夫の前、生まれたままの姿で立っている。今すぐ夫の上に飛び乗って、彼の大きなおちんちんを飲み込みたかった。だけど、何とかして自分を抑えた。他のことを計画していたから。 ジョンは、あたしが何をするんだろうとじっとあたしを目で追っている。あたしは衣装入れに行き、中から目隠しを取り出して、ベッドに戻った。彼の胸は、荒い息づかいで上下に波打っていて、すでに興奮してるのが分かる。あたしは目隠しで彼の目を覆った。そして、彼の耳元に囁きかけた。 「黙っていて。ただ、あたしがこれからあなたにしてあげることを楽しんで」 彼は、哀れっぽい声を漏らして頷いた。 あたしは革ひもを手にベッドの支柱を見た。どうも、彼の足を結び付けられそうなものがなかったので、彼にベッドの端に動いて、両脚を、膝から下をベッドから降ろすように囁いた。90度の角度で膝から下だけベッドから降ろすように。 降ろした両足を、革ひもで足首のところで、ベッドの下の金具に結び付けた。そして、次に彼の両手をベッドの頭の方の支柱に拘束した。 これで完成。夫は、ほぼ大の字に近い姿勢でベッドに仰向けになっている。しかも、素っ裸で目隠しされたまま。 あたしはひと仕事を終え、一度、少し離れて彼の姿を見た。……もはや自分で擦ることができなくなったおちんちん。あたしは、本当のことを言うと、こんなふうに、どうしようもできない状態になっている夫を見るのが、大好き。両手両足を縛られて、あたしにどんな変態じみたプレーをされるかを待っている夫。 あたしは、彼の広げた脚の間に移動して、そのまま、床に座り、両手を伸ばして軽く彼の太ももに触れた。触れた途端、彼はビクッと反応して、同時におちんちんもピンと跳ねあがって、お腹から離れた。 「ねえ、あなた? あたしのこと、欲しいみたいね?」 「ああ、そうだよ」 と彼は苦しそうに答えた。胸がますます激しく上下してる。あたしはジワジワと両手を這い上がらせ、彼の両脚が交わるところへと向かった。そして指先で夫の睾丸にちょっと触れた。おちんちんの先端からかなりのプレカムが染み出てるのに気づいた。
「どう? 分かる?」とジーナが囁いた。 そうだった、忘れるところだった。ふたりには、あたしは彼女たちの体を調べて、何か兆候がないかと探しているはずと思われているのだった。 あたしは両手を下に持っていき、ふたりの可愛い小さな睾丸を指に乗せてコロコロさせてみた。それから、ペニスの底部の尿道に沿って指でなぞり上げ、最後に、亀頭に指をあてた。ふたりとも、そこがピクピク震えていた。そして、あたしはふたりのそれをじっと見つめた。ふたりがどんな反応をしてるのか、ふたりの顔を見たかったけれど、あたしは何か兆候があるかどうか調べているフリをしなければならなかった。 でも、ふたりの顔を見なくても、少なくともウェンディは反応してるのが分かった。もう一度だけ彼女のおちんちんの竿をギュッとしごいたら、はっきりと固くなってくるのを感じた。柔らかい時は暖かくて触り心地がすごく良かったけれど、固くなり始めたら、罪深いほどセクシーなモノに思われてくる。 一方、ジーナのおちんちんは最初は柔らかいままだった。でも、あたしがゆっくりと手を上下に動かして、ふたりのソレをゆっくりとストロークし始めたら、ジーナのも同じように固くなり始めた。彼女はそれに気づいたようだった。 「あら、やだ! ごめんなさい!」 とジーナが言った。 「私もごめんなさい!」ウェンディもそう言った。勃起することは悪いことのように思ってるようだった。 あたしは、とても辛かったけれど、ちょっとだけしごくのをやめた。ふたりのおちんちんの感触がとても気持ちよかったから、やめたくなかった。柔らかい肌の下にゴツゴツしたコブがある感触が、すごく興奮させる。あんまり気持ちいいのでいつまでも触っていたくなる。 「いいの。それは構わないわ。さっき言ったように、これはおちんちんだから。こうなって当り前だから。今のテストはちょっと……刺激反応を確かめるため」 「刺激反応って……どういうこと?」とウェンディが訊いた。 あたしは困ったような笑みを見せながら、頭を左右に振った。 「ちょっと落ち着いて聞いて」とあたしは、左右の手の親指と人差し指でそれぞれのおちんちんをつまんで見せた。「これは、お医者さんが教えてくれた恒久性を示す兆候を見事に示しているの……」 すでにジーナの頬には涙が流れていた。それほど悲しいことなのだ。どうにかしてふたりの気持ちを支えてあげなければいけなかった。このことが必要以上に深刻になってしまうのは避けたかった。 「例えば?」とウェンディが訊いた。あたしが何か間違いをしてると期待してるような口調だった。あたしは注意をジーナに集中させることにした。落ち込んでる状態から救い出すのが先決と。 「いい? ジーナのおちんちんをよく見てみて?」 そう言うとジーナがヒーっと声を上げた。それでもジーナは目から涙を拭き、自分の股間に目を降ろした。 ここで何かを考えださなきゃいけないと思ったあたしは、こう言った。「いい、見てる? 彼女のおちんちんの先端のところ、下の方がちょっと左右に分かれているのが見える?」 「どのペニスもそうなってるわ」とウェンディが言った。 「その通り。どのペニスにもこの形がある。ただし、あたしたちの病状で回復可能なものの場合は例外なの。回復可能の場合、そこは完全に丸くなっているの。キノコの頭のように」 こんなことをでっち上げるのが簡単すぎて我ながらびっくりした。そういえば、昨日もすごく簡単だった。これまでの人生、自分の頭の中だけで生きてきて、手の込んだ妄想をし続けてきたことが、こういう事態のための完璧な才能を自分に備えてきたのかも。そんなことを一瞬、思った。ともあれ、今はこれに集中。ジーナがめそめそ泣いているのが聞こえる。このまま続けなければと思った。 あたしは、また下の方に手を伸ばして、ジーナの睾丸を撫で始めた。 「そう。それに、彼女の睾丸がどういう状態になっているか見てみて?」 彼女のキュートな睾丸を見た。元々、陰毛を剃っていた彼女だったので、そこも綺麗にツルツルになっている。肌には小さなそばかすがあって愛らしい。 あたしは何を言うか考え、そして話し始めた。「いい? 治療可能だったら、彼女の陰嚢はもっとずっと引き締まっているはずなの。袋の皮が睾丸に密着してるはずと言ったらいいかしら。でも、彼女の場合、ぶら下がってるって感じになっている」 それからウェンディの方にも手を伸ばし、彼女の睾丸を指で触った。 「ウェンディのも同じだわ。それに、あたしのも同じ」 「ああ、なんてこと!」とジーナが嘆息した。ジーナは放っておいたら、ひどく落ち込んでくかも。 あたしは素早く手を動かし、ふたりの勃起したおちんちんをストロークし始めた。何か対処しなければというのもあったけれど、それより、ふたりのアソコの肌がとても滑らかで、愛おしく感じてた。何とか話しをでっち上げなくちゃいけないということすら、忘れそうになっていた。自分自身の乳房は、ますます張ってきてて、もう痛いほど。これを、そもそも、どうにかできるのか分からないけど、どうしてよいか分からなかった。 「今は何をしてるの?」とウェンディが訊いてきた。何かを期待しているような言い方だった。あたしは、何とか、焦ってる雰囲気を見せずに済んだ。 「ええ、ちょっと。あのね、永続的かどうか確かめる本当に重要な方法は、これなの。こういうふうにふたりのおちんちんをこすってみる……」としばらくふたりをしごきながら言った。ふたりの息遣いがだんだん浅い呼吸になってくるのに気づいた。ふたりとも、無意識的にあたしの手の動きに合わせて腰を上下に動かし始めてる。「それで……もし残酷な言い方に聞こえたらごめんなさい。もし、プレカムが出てこなかったら、元に戻ることが可能なの。でも、ウェンディのおちんちんを見てみて? 先端から透明な液体が出ているわ。ジーナの方はもっとたくさん出てきてる」 それは本当だった。ウェンディもジーナもすごく興奮しているし、あたしの手に握られたおちんちん、両方ともカチコチに固くなっていた。そして、あたしはと言うと、ふたりのアレを握ってるうちに、頭の中から理性的なところが消えていった。 あたしは黙ったまま、ふたりのおちんちんをこすり続けた。少しだけ早いストロークで。ふたりのうち、特にウェンディについて、彼女があたしの手の動きに合わせて体を動かすのを感じていた。呼吸は、ふたりとも肩を上下させて大きな息づかいをしていた。もうしばらくしごき続けた。すると、ジーナが、ああん、あっ、ああんと悩ましい声を上げるのを聞いた。そしてようやく彼女は言葉を口にした。 「ああ、ウェンディ? 私たち何をしてるの? これってどういうこと? 私たちって……」 最初は真面目な質問の口調だったけれど、次第に、ヨガリ声が混じった情熱的な声に変わっていた。 「わ、わたしにも分からないわ、ジーナ。なんにも考えられないの!」 とウェンディも悶え声になっている。 あたしは下唇を噛み、しっかり、ふたりをしごき続けた。自分自身のおちんちんに目を向けたら、プレカムが信じられないほどたくさん出てて、だらだら流れていた。おちんちんも痛いほどビンビンになっているし、おっぱいも爆発しそうに張っている。 でも、ウェンディの喘ぎ声を聞いて、ジーナは少し我に返ったらしい。何が起きてるかを疑問に思ったみたいだった。 「ねえ、ラリッサ? 何をしてるの?」とジーナが訊いた。 一瞬、あたしはどうしていいか困ってしまった。でも、ふたりのおちんちんを擦るのはやめなかった。顔を上げてふたりを見たら、ふたりともあたしのことを見つめている。でも、ふたりともあたしが手を動かすのを止めようとはしていなかった。それに、ふたりとも喘ぎ声をあげているし、ウェンディは小さいけどヨガリ声すら上げていた。あたしはもう何秒か擦り続けて、ふたりに、もう少し、この感覚を味わわせた後、ようやく返事をした。 「今ふたりが経験している感覚、あたしも経験してきたわ」 ずっと作り話ばかりしてきたけど、これは本当だった。「だから、もうちょっとだけ気持ちよくなる方法をあたしは知っている。普通のことじゃないけど、でも、気持ちいいこと。あなたたち二人とも、気持ちよくなりたくない?」 少しセクシーな声で言った。言いながら、ふたりのおちんちんを少し強くしごいた。
 68_Your fantasies 「あなたの夢」 「これって屈辱的だよ。キミにも分かるだろ?」 「もちろん。でも、それこそが肝心な点。それに、その格好すると、あなたが女のあたしに期待してることがどういうことか、少しは認識できるようになるわ。なんだかんだ言っても、あなたは、その服を、あたしに着せたがっていたんだから。この『チアリーダー』のコスチュームって、あなたの夢だったんでしょ?」 「でも、チアリーダーになるのはボクじゃなくて、キミだったんだよ!」 「あら、そうかしら? どうだか? あなたこそ、簡単にここまで調子を合わせてきたんじゃない?」 「簡単に? ここまでのどの段階でも、ボクは抵抗してきたじゃないか!」 「あらほんと? 全然、気づかなかったわ。まあ、事実が何であれ、あなたは結局はその格好になったの。すね毛を剃ったり、お化粧をしたり、そのキュートで可愛いスカートを履いたり。これってどう見ても、最初からあなたが計画してきたことのように思えるけど?」 「そんなことはない! 誓ってもいい、こんなこと……」 「いいから、続けて。前かがみになって。あなたの可愛いお尻を見せてちょうだい」 「少なくとも、下着を履かせてくれない?」 「その点こそ、あなたが求めていた一線じゃなかった? あなたが言ったことよね? あたしに、ノーパンでチアリーダーの格好になってくれって。だから、あなたも下着なしになるの。そこだけは譲れないって、あなたが言ってたことなのよ?」 「ぼ、ボクは気が変わったんだ」 「そんなのダメ。下着なしのあなたが、あたし、好きよ。下着なしだと、テイルゲイト( 参考)してる時も、ずっとつま先立ちでいることになるでしょ?」 「て、テイルゲイト? ぼ、ボクはこんな格好で試合を観に行くつもりはないよ。ボクはただ……」 「あたしがしなさいと言ったら、しなきゃダメ。あら、また、めそめそ泣きだすの? それにきっと文句を言いだすわね。でも、決まって、あなたは、最後にはあたしに従うの。いつもそうだったもの。だから、もう、そういう儀式めいたことはやめて、間をすっ飛ばして、しなくちゃいけないことをしたらどう? それに、誰も気づかないって。あなたが行儀よく可愛いリアリーダーでいてくれたら、多分、スタジアムに入るときには、パンティを履かせてあげるかも」 「で、でも……でもボクは……嫌なんだよ……」 「いいから、前かがみになって。そしてにっこり笑って。彼氏の夢を叶えてあげるのに、こんなにグダグダ面倒をかける女の子って、そんなにいないものよ」
 68_Waking up 「目覚め」 目を覚まし、瞬きした。意識が戻るのにつれて、ゆっくりと目の焦点がはっきりしてくる。依然として朦朧状態だったけれど、体を起こし、自分の置かれている環境を理解しようと周囲を見回した。最後に覚えていることは、スーパーマーケットから出たところまで。妊娠している妻のために、変な取り合わせだけれども、スナック菓子とピクルスとアイスクリームを買って出てきたところだった。そして、その後、目の前が真っ暗になった。 溜息をつきながら目をこすった。 「じきに消えるわよ」と女性の声がした。振り向くと、部屋の隅に、息を飲むほど美しいけれど、どこか見覚えがある、そして目を見張る裸体の女性が立っていた。「朦朧とした状態のこと。それは麻酔の効果だから」 「麻酔?」とボクはつぶやいた。自分の声を聞いた瞬間、驚いて唖然とし、思わず手で口を覆った。今の自分の声は間違いなく女性の声だった。 「ああ、それね」と彼女は言い、ボクの方に近づいてきた。その動きは非常に優雅で、まるで床を滑走してきてると言ってもよいほどっだった。でも、ボクは、彼女の脚の間にあるモノ以外は何も目に入っていなかった。 「あ、あなたは……あなたは男なのか」 彼女は笑った。音楽を思わせる笑い声だった。「かつては、ね」と彼女はベッドに腰を降ろした。「あなたも、かつては」 かつて? 過去形? 一瞬、彼女が何を言ったのか分からなかった。そして、次の瞬間、まるでダムが決壊したように、意識が完全に明瞭になった。最初に気づいたことは、胸に感じるふたつの重み。その直後に、長い髪の房が左右の肩をくすぐるのに気づいた。 胸の中からパニック感が湧き上がり、ボクは過呼吸状態になった。それにより、いっそう、胸の重みを実感する。自分の乳房は、このミステリアスな女性のよりも大きいとは言えないまでも、同じくらい大きいとは言える。 「あ、あんたはボクにいったい、な、何をしたんだ?」 と荒い息づかいをしつつ訊いた。 彼女はボクの肩に手をかけ、なだめる様な声で言った。「落ち着いて。ショックなのは分かるわ。でも、あたしはあなたに何もしていないの、アレックス。もっと言えば、あたしたち、あなたが思ってるよりずっと似た境遇にいるのよ」 「で、でも……」 訊きたいことが山ほどあった。でも、言葉が喉に詰まって出てこなかった。自分がどんな姿になってしまったのか。それを悟り、心が圧倒されていた。 「あたしのことが分からないようね。あたし、すごく変わってしまったから。でも、あなた、あたしのことを知ってるのよ。あたしたち、高校を出た後は接触しなくなったけれど、それまでは友達だったの」 ボクは彼女の顔を見た。見覚えがあるのは確かだった。彼女が本当のことを言ってるのは分かったけれど、どうしても、彼女の特徴をボクが知ってる人物の特徴と一致させることができなかった。 「あたしはブライアン。ブライアン・ヒギンズ」 「な、なんだって? そんな、あ、ありえない……だって、ブライアンは……」 「体重93キロの全身ゴツゴツの筋肉の塊。でも、今はそんなにないわ。ダイエットやエクササイズやホルモン注入で、男の体は劇的に変えられるものなの。言うまでもないけど、あたしはもはや男じゃない。あなたも同じ。この会話から何も理解してないとしても、そのことだけは揺るがない事実として認識して。それを理解してる限り、あまり酷い懲らしめは受けないはずだから」 「こ、懲らしめ?」 依然として、自分の隣に座る美しい女性が、かつては筋肉の塊のフットボール選手だったことに驚いていたが、それでも訊かずにはいられなかった。「いったい誰に?」 「グレッグ・ラニングを覚えてる?」 ボクは頷いた。グレッグは、高校時代、ボクたちのクラス全員にとってのパンチング・バッグだった。彼が容赦なくイジメられない日は一日もなかった。そして、今は後悔しているのだが、ボクも彼の虐待に一役買っていたのだった。 「まあ、あのグレッグは今はちょっと変わったわ。ひとつ言えば、今の彼は億万長者。それに……」 「グレッグ・ラニングがボクにこれをしたと言ってるのか?」 突然、ボクの中に男性的な怒りが湧き上がってくるのを感じた。 「ええ、あなたにも、卒業時のクラスの他のフットボール部員全員にも。まあまあの姿になった人もいれば、残念な結果になった人もいる。正直、あなたは運がいいわよ。すごく可愛いもの」 「ちょっと待って、じゃあ、君が言ってるのは……」 「これは恒久的だと言ってるの。元には戻れない。あたしも逃げようとした。他にも逃げようとして人たちがいるわ。でも、ダメだった。グレッグは許してくれようとしない。そして、彼はあたしたちの体を好き放題に使うの。あたしたちにいろんなことをさせる。でも、従順にしていたら、彼は決してあなたを痛めつけたりしないわよ。それだけは忘れないで」 彼女は立ち上がった。ボクは彼女の腕をつかんだ。「待ってくれ。まだ訊きたいことがいっぱいあるんだ」 「今はダメ。でも、後でその時間があるから。今はとりあえず、言われたとおりのことをするよう頑張るの。グレッグがここに来たら、あなたが持ってるプライドがどんなものでも、全部、心の奥に封印すること。そんなプライドのためにバカなことをしないようにすること」 彼女はボクの手を振りほどいた。「もう行かなくちゃ。あたしにもしなきゃいけない仕事があるから」 そして彼女は出て行った。ボクは自分の新しい肉体を調べ始め、この新しい状況についてどうすべきか考え始めたのだった。
 68_Used 「利用された」 「ありがとう」とエディは言った。「本当に、心の底から、ありがとう。僕は……」 「ちょっと、やめてくれる?」とキャメロンはウイッグの位置を直しながら言った。「あたしは、別に、あんたのためにこんなことをしてるわけじゃないの。抗しなくちゃいけないからやってるだけ。他に道がないからやってるだけ」 「分かってる。でも……」 「『でも』って何よ、エディ。こういうことなのよ、いい? あたしはこれをやった、そしてこれで終わり。あんたはあたしにおカネを払って、その後はふたりは別々の道を行く。もう、電話はしない。メールもしない。あたしたちそれぞれの別々の生活をしていく、ってそれだけ」 「で、でも、僕たちはもしかして何とかなるんじゃないかと……」 「何とかなるって何よ? 何回かセックスしたからと言って、まさか、あたしがあんたに気があるとか思ってるの? あんたがあたしにつきまとったのには理由があるわ。あたしは女の子として通るよう、みんなが納得するように振る舞ってきたし、あんたの元彼女にちょっとは似ているように頑張ってきた。でも、それだけよ? あんたはあたしを利用している。これまでも、ずっとあんたはあたしを利用してきた。それが分かるまで時間がかかったのは事実だけど」 「僕はキミを利用したりなんかしてないよ」と彼は穏やかな声で言った。 「じゃあアレは何て言うの? あんたは、あの女装ショーであたしを見た。ちなみに、あたしはストレートだけどね。あんたは別に求愛したわけじゃない。あたしにお酒を飲ませて酔わせて、そして、あたしを犯した。その後で、あなたはあたしを愛してるとあたしに納得させようとしてきた。その間ずっと、あたしにあなたの妹として振る舞うように計画していたんでしょ? それを利用したと言わなくて何て言うの?」 「そういうわけじゃないよ。君も分かってるはずだよ。それに、キミが本当にそんなにストレートなら、どうして、これをしたんだ?」 「分からないわ。多分、あたしは自分が思ってるほどストレートじゃないのかもしれない。あんたのせいだからかも。それとも、あたしが飛んでもないバカで、本気であんたはあたしのことを好きなんだと思い込んでいたからかもしれない。分からないし、そんなのどうでもいいわ。あたしは、ただ、これを何とかしたいだけ。あんたが約束したモノが得られれば、後はあたしは姿を消すわ。もうあたしに会わずにすむでしょうね」 「じゃあ、キミはただ遺産の分け前を奪うだけだったということなのか? この2週間、ふたりで分かち合ってきたことを忘れるつもりなのか? それが最初からの計画だったと?」 「そう、それがあたしの計画」 「分かってると思うけど、キミはこれをもうひと月かそれ以上、続けなくちゃいけないんだよ。ティナは姿を消してから2年以上になる。今どこにいるかなんて誰も分からない。だから、キミの姿がティナと違うからって、その違いはあんまり問題にならない。でも、ただ姿を見せて、書類にサインして、現金が詰まったカバンを持って『はい、さよなら』っていうほど簡単なことじゃないんだ。君はしばらくは……」 「自分がしなくちゃいけないことは分かってるわ」とキャメロンは言った。「あなたはあなたの役割を、あたしはあたしの役割をする。でも、あそこに行った後は、あなたは、この『愛してる、どうのこうの』の話は棚上げにしなくちゃいけないの。あなたとあたしは兄と妹になるのよ。あなたが何か愛に狂ったマヌケのように振る舞って、この話を台無しにしてほしくはないのよ」 「ああ、いいよ」とエディが言った。「僕がキミのことを諦めていないと知っててくれている限りは、ね。これが全部終わったら、僕は……」 「やめて」とキャメロンは遮った。「その話はストップ。今から後は、その種のことは、全部、禁止」 エディは頷いた。「ああ、分かった。さあ、服を着て。あと20分もしたら、ウチの家族が来る」
 68_Unexpected complications 「予期しなかった厄介ごと」 「今日のこと、あなたが言い出したことよね? あたしは、あなたがみんなにあたしのことについて言う気持ちができていなかったなら、別に、家にいても全然かまわなかったのよ?」 「分かってるよ。バカなことを考えたと思ってる。いずれ、分かってしまうことだと考えておくべきだった」 「あたしは、別に、あなたの気持ちが分かっていないとは言ってないわ。あたし自身、丸2年間、フルで生活するまで両親にはカミングアウトしなかったのよ。ちゃんと理解してるの」 「じゃあ、どうしたらいいと? 親のところに進み出て、あなたたちの息子の婚約者のことをお二人ともあれほど愛しんでますが、実はトランスジェンダーなのですって言うのか?」 「それって、そんなに悪いこと?」 「キミはウチの両親を知らないんだよ。頼むよ、ほんとに。父はバプティスト教会の牧師なんだ。そんな父が、ボクとキミで教会に一緒に手をつないで入ってきてほしいなんて、本気で思うか? 母親はもっと悪い。母は優しく振る舞って、キミの顔を見て綺麗な人だねって言うとは思うけど、陰では酷いことを山ほど言うと思う。しかも、それに加えて、これから先ずっと、家族で集まるたびに、母はキミに極々小さなイヤミや攻撃をいっぱい仕掛けてきて、それが積み重なっていくんだよ」 「じゃあ、あたしのことを心配してくれているのね」 「もちろんだ。キミのことが心配だ。僕はキミを愛しているんだから。もし、あの人たちがキミは連中が考える正しい枠に収まっていないと思ったら、どうなると思う? あいつら、バカ者の群れになるよ。僕の兄の元の奥さんを、母がどんなふうに扱ったか、キミに見せたかったよ。そして、僕とキミに対しては、もっとひどい扱いをするだろうって、予想がつくだろ?」 「多分、あなたのお姉さんは黙っていてくれるんじゃない? それとも、お姉さんはそもそも見ていなかったかも。ほんの一瞬だけだったから。それに……」 「見てたよ。それに、あの目ざといアバズレ女は、聞く耳を持つ人なら誰にでも話すと思う。姉は、厄介ごとを掻きまわして大騒ぎするのを生きがいにしてるんだ」 「じゃあ、いずれカミングアウトするのね。お姉さんが、あたしのおちんちんを見たとみんなに話す。あたしたち、それに何とか対処すればよいと。それだけの話じゃない?」 「でも……」 「トム、もう『でも』はナシにして。すでに起きてることなのよ。それを何とかすればよいだけのこと。それだけのこと。あたしたちが互いに力を合わせている限り、問題はないわ。最後には上手くいくわよ」 「僕もキミくらい楽観的でいられたらいいのに」 「これはあなたにとっては初めてのこと。その気持ちは分かるわ。でも、請け合ってもいいけど、あたしは、もっとひどいことを潜り抜けてきたの。これは、道にできたちょっとしたでこぼこにすぎないの。あたしたちなら乗り越えられる。誓ってもいいわよ」
 68_Tagging along 「つるんで遊ぶ」 自分の裸の体を見下ろし、ケイシーはつぶやいた。「これ、よく分からない」 同じく裸になっているローラが答えた。「これはあなたのアイデアなのよ。あなたが大学の大きなパーティについてきたいって言ったんでしょ? だから、望み通りになったじゃない。あなたはここに来た。そして、こういうことになった。と、そういうこと。だから、めんどくさいこと言わずに、楽しみなさいよ」 「でも、素っ裸でプールに入るなんて言ってなかったじゃない?」 そう訴えても、彼の言葉はローラの耳には入っていない。彼女はすでに、ダレンの姿に気を取られていた。ダレンはトランクスを脱いでいるところだった。逞しい太ももに沿って降ろしていることである。ケイシーは自分の体とダレンの体の違いに気づかずにはいられなかった。どうして彼女はダレンのような男を見てあからさまに発情しているのに、自分のような男を友だちグループに入れてくれているのか、その疑問が再び頭をもたげてくる。「それにみんなボクのことを女の子と言ってるし」 「基本的に、あなたは女の子よ。だって、あたしの服を着てるし。髪を伸ばしてるし、他のところも全部。そう思うのが普通だわ」 「キミがボクに着せるから、キミの服を着てるんだよ? ボクの持ってた服は流行っていないからって」 「その通りよ。それに、あなたも楽しんでたのは否定できないでしょ? あなたがマークといちゃいちゃしてたの見たわよ」 「イチャイチャなんかしてなかったよ」とケイシーは嘘をついた。「ぼ、ボクはただ……ただ、みんなに優しくしてただけだよ。ボクは別に……」 「でも、マークの方はあなたから目が離せなかったようだけどね」とローラは、そのマークがいる方を顎で指して見せた。彼はすでに素っ裸になっていて、プールの端に座り、脚を垂らし、水につけていた。ケイシーは彼の脚の間にあるモノに目を向けずにはいられなかった。 「ボクには無理。できないよ。本当に……」とケイシーが訴えた。 「あたしのアドバイスが欲しい?」とローラが言った。 ケイシーは頷いた。 「自分ができないことについて考えるのをやめること。したくないことについて考えるのをやめること。本当の自分と違う姿について考えるのをやめること。自然と思えることをすること。もし、それがマークと一緒にいることを意味するなら、その本能に従うこと。それが女の子になり切ることなら、それこそあなたがすべきこと。少なくとも、あたしはそう思うわ。あたし個人のつまんない考えだけどね。あたしのアドバイスを受けるか、受けないなら、帰ればいいんじゃない? でも、あたしはあっちに行って、あそこにいる逞しい彼にめちゃくちゃにエッチしてもらうつもり。あなたもマークと同じことをすべきだと思うわよ」 それまでウジウジしていたケイシーだったけれど、突然、ひらめきを感じた。自分が求めているのを否定するのは馬鹿げている。確かに、それを認めることには山ほどの重荷がつきまとう。中でも、大きなのは、自分が女装について本気で考えたことがなく、ましてや、女の子になるとか、男とセックスをするとか考えもしなかったという事実。……だけど、あの時は、彼は思考が多量のアルコールで柔軟になっており、そんなことは何も問題にならないように思えたのだった。 「分かった、するよ」とケイシーは言った。 「よろしい」とローラは答えた。「あなたなら、正しい選択をすると思っていたわ。さあ、一緒に、おちんちんをゲットしに行きましょう」
 68_Survival 「生き残る」 その人は背が高く、細面で鉤鼻をしていた。そのため、特にハンサムとは言えないが、印象的な顔をしていたと言える。あたしのお客さんの大半に当てはまることだけれど、この人も、このような機会のために、それなりの服装をしてきていて、この人の場合は、高価そうに見える青いスーツと赤いネクタイを締めていた。濃い色の髪の毛は短く刈り揃えられ、あごには剃り残しを思わせる部分が全くなかった。 「この仕事の調子はどうなのかな?」と彼はコートを脱ぎ、ベッドの上に放り投げた。そして、シャツのカフスボタンをいじりながら、質問をつづけた。「まずは、お喋りをして、互いに知り合うのかな? それとも、今は、『直ちに始める』といった状況なのかな?」 あたしはいつもの作り笑いをした。「お客様の好きなやり方でいいわよ」とあたしは片手で彼の腕をさっと触れた。この巧妙な接触はお馴染みのサインで、これからはるかにもっと接触することを示すサイン。「すべて、お客様次第」 彼は微笑んだ。冷たい、死人のような表情で、あたしは裸の背中に寒気が走るのを感じた。急に、どこかに行きたくなった。……どこでもいい、ここじゃないところに逃げたいと。その不快感を隠そうと、あたしはゆったりと背伸びした。そのポーズはあたしの裸体を隅々までじっくりと客に見せる効果を持つのを、あたしは知っている。このカラダを作るのに、多くの時間、労力、そして金銭をつぎ込んできた。この自慢の作品を見せることに不安はまったくない。それでも、彼の視線があたしの柔らかい白肌を舐めるように這いまわるのを感じ、どうしても身震いしてしまった。あたしは、何千人とまではいかないけれど、何百人もの男たちにカラダをじろじろ見られてきた。だけど、この人の視線の這わせ方は特別で、どうしてもドアへと逃げ走りたくなるような視線だった。 「ちょっとお話ししたい気分なんだが」と彼は言い、ベッドに腰掛け、袖をまくり、細かなタトゥだらけの前腕を露わにした。そのタトゥには見覚えがあり、あたしは息を飲んだ。でも、職業柄、あたしは素早く動揺を隠した。その記憶は遠い昔の別の人生を歩んでいた時の記憶。忘れてしまった方が、どれだけよかったか。そう思えるような記憶。 白金色に輝く髪の毛を払いながら、あたしはもう一度、微笑んで彼の方に近づいた。誘惑的に腰を振りながら。近づいた後、ちょっと、彼を見下ろした。彼の目はあたしの胸の真ん前に位置している。でも、この男はあたしの乳房を見ていなかった。たいていの男なら、女が裸の胸を目の前に突きつけられたら、必ず、そこを見つめるはずなのに。彼の視線はあたしの胸ではなく、あたしの顔に向けられていた。射貫くような視線を感じた。もし、この手の仕事に不慣れなままのあたしだったら、彼の目を見た瞬間、あっという間にヘナヘナと崩れ落ちていたことだろう。でも、あたしには経験がある。こういう不快感を隠す方法をマスターしている。 さらに彼に近づき、脚を広げ、彼にまたがりながら、ゆっくりと彼の股間へと腰を降ろした。両腕を彼の肩に絡め、乳房を両脇から締め付け、突き出し、彼の左右の目の間のあたりを見つめる。「何を話したいの?」 彼はさらに嬉しそうな笑顔になった。「ああ、たくさんあるんだよ。ありすぎて困るくらいだ。私はお前のことをずっとずっと探し続けてきた。お前のことを見つけるのは不可能だっただろう。よっぽど運が良かったのか、あの、人がよさそうだが意志の弱そうな医師のところにたどり着けなかったなら、お前を見つけることはできなかったな。そういう、人が良いが意志の弱そうな医者。それに当てはまる人を知ってるんじゃないのか?」 心臓が喉奥から飛び出そうになっていた。心臓の鼓動が彼にも伝わっていると思った。それほど、ドキドキと高鳴り、あたし自身の耳にも聞こえていた。とは言え、あたしは表情を変えなかった。変えることができなかったと言ってもいい。あたしは下唇を噛み、視線をあさっての方に向けながら返事した。「知らないわ。あたし、あんまりお医者さんに知り合いがいないのよ。あなたお医者さんなの?」 彼は笑い出した。その笑い声の陰気な音は、とても人間の発する音に聞こえなかった。「いいや、違う」と彼は両手であたしの腰を押さ、腰の柔肌を揉み始めた。ほとんど痛いくらいに強く揉んでいた。「でも、君ならその医者をしてるだろう。この美しい乳房を作った医者だよ。乳房ばかりじゃない。このほっそりしたウエストや、お前の美しい顔もだ」 「あ、あたし、あなたが何の話をしているのか分からないわ」 それまで平然としていたけれども、その演技が崩れだしていた。 「いや、分かってるだろ。と言うのも、お前はただの女体化した高級娼婦じゃないからな。確かにお前は高級娼婦だ……ちょっと女体化に熱心になりすぎたようだが、間違いなくお前は娼婦だ。だが、最初からそうだったわけじゃないだろう。昔々のこと、お前は会計士だった。そうだろ?」 偽装は剥がされ、終わりだと知った。だけど、どうしたらよいか分からなかった。いま彼はあたしのウエストに両手を持ってきていて、指が深く食い込むほど強く押さえつけていた。たとえそうしていなくても、あのタトゥを見れば、この男が熟練の殺し屋だと分かっていた。逃げるチャンスが見当たらない。 「お願い……あたしは、本当は……」と呟いた。 「いや、お前は、ラモス氏から盗んだのだよ。実に多額のカネを、そうだよな? お前が生活のために、こんなことをしなくても済むような、充分なカネだ。となると、なぜだ? なぜお前はこんなところにいるんだ? その点だけが、私には理解できなかった点だ。私はお前をタイのどこかのビーチで見つけると思っていたのだよ。こんなところで娼婦として働いてるとは、とても……」 「それこそが、あたしがカネを盗んだ理由なのよ!」 小声だけど強い口調で言っていた。声に自分でも信じられないような自信に溢れた調子が籠っていた。「この姿こそ、あたしがなりたかった姿。でも、それを実現するおカネがなかった。胸の豊胸ひとつだけでもどれだけかかったことか……だから、あたしを逃がして。あたしを見つけられなかったと連中に言って。でなければ、ジム・リチャードは死んだと言って。実際、ジムはもう死んだのよ。公的には。メキシコ・シティーに行けば、あたしの昔の特徴にマッチする男性の死亡証明書を得られるわ。だから、こんなことをする必要がないのよ、あなたには。ラモスがいくら払うか知らないけど、あたしはそれ以上の額をあげるわ」 少しの間、彼はあたしの提案を考えている様子だった。だけど、次の瞬間、光のスピードで彼はあたしに襲い掛かり、あたしの首を両手で絞めつけていた。もちろん、あたしは抵抗したけれど、彼の方が圧倒的に強かった。呼吸ができなくなり、命が断たれるのを感じながら、あたしはひとつの単純な真理を悟った。すぐに死ぬことになると知りつつも、あたしは自分の行為を後悔していないという思い。短かったけれど、自分は思い通りの生き方をすることができたという気持ち。組織暴力団連合の雇ったヒットマンに殺されることも含めて、何一つ、あたしの自由を奪うことはできないのだという思い。夢に思い続けてきた人生を送ることができた以上、満足して死ねるという気持ち。 しかし、意識がもうろうとなり始める直前、じたばたしていたあたしは、手の先に何か固いものがあるのを知った。その時は分からなかったけれど、それは重々しい合金の燭台だった。一番のお得意さんのひとりからもらった燭台。首を絞められ、両目が飛び出そうになりながら、あの殺し屋を見つめつつ、あたしはその燭台を掴んでいた。そして、それを使って男を殴りつけた。弱々しい打撃だったのか、男は気絶することはなく、ただ、驚いた表情を見せた。それでも、あたしの首を絞めるチカラは弱くなり、少しばかりとは言えをもたらす呼吸をすることができた。そしてあたしは打撃を加えた。さらに、もう一度。彼は両手をだらりとさせた。さらにもう一撃を加えた。今度は装飾的な燭台の土台に血がついてるのが見えた。男は立っていることができなくなり、ベッドに倒れ込んだ。あたしは、彼にまたがり、その場しのぎの武器を両手で握りしめ、自分が持っているすべての力を振り絞って、燭台を打ち下ろした。彼の額が大きく割れ、赤い裂け目ができるのが見えた。さらにもう一撃。そしてさらにもう一度。何度も繰り返し打撃を加え、男を死に追いやった。恐怖と奇妙に力強い生存本能が一緒になって、あたしの打撃に力を与えていた。そしてやがてその力も尽き、あたしはぐったりとなった。この行為に息を乱し、血しぶきが、あたしのミルクのように白い肌を覆っていた。彼は死んだ。彼の、かつては印象深かった顔は、今は、ぐちゃぐちゃになった血だらけの肉の塊に変わっていた。 どのくらい、血だらけのまま呆然として彼の上にまたがっていたか、覚えていない。でも、男の死体から降りたころには、血が固まり始めていた。でも、あたしは気にしなかった。自分は生き延びたのだ。試練を与えられ、それに勝利した。血まみれで吐き気がするような勝利であったとしても、この勝利はあたしに自分自身の未来への希望を抱かせるものだった。とても長い間、あたしは見つけられるかもしれないという恐怖の中で生きてきた。だけど、床に横たわる殺し屋を見つめながら、あたしは、以前の自分とは異なり、今の自分は簡単な標的ではないのだと悟った。それを悟った瞬間、あたしは誰がどんな非難をあたしに投げつけようとも、自分は必ず生き残ると思ったのだった。
 68_Someone has to do it 「誰かがしなければいけない」 「さあ、ここにいるのが彼よ。あなたのプロム・パーティの時の王様」 「ちょっと待って。ええっ? まさか! レイシー、これ、本当に彼なの? あの胸の……あれ本物なの? あなた、どうやって彼にこれをさせたの?」 「すっごく簡単だったわ。彼はあたしの言いなりよ。混ぜ物にちょっとアルコールを加えて飲ませたら、彼、何でもあたしが望むことをするわ」 「で、でも……彼、胸が。しかも本物のように見える」 「違うわ。偽物とメイクで誤魔化してるだけ。たくさんメイクしてるの」 「でも、すごいわ。ビックリするくらい。でも、なぜなの? 彼をどうするつもりなの?」 「『なぜ』の方は単純よ。あいつは、高校時代、あんなにたくさんの女の子たちを利用しまくった最低男だったから。酔わせたり、クスリを使ったりして。どっちでも同じ。女の子が酩酊状態になると、必ずあいつが出てくる。あなた自身、誰よりも、それを分かってるでしょ?」 「あ、あなたが知ってるなんて知らなかったわ」 「知ってたわよ。この卑劣野郎はあなたをレ〇プした。だから、あたしはこいつに償いをさせたいと思ったわけ」 「でも、どうやって?」 「まずは写真を使って始めるつもり。誰でもいいけど、こんな格好になってる彼を見せる。そうしたら、こいつの評判が生き残るのは不可能になるでしょ。彼を知ってる人ならたら、誰でも、彼はシシーだったんだと思うでしょうね。とすると、こいつは、そんなことにならないようにするためなら、何でもするはず」 「彼にどんなことをさせるつもりなの?」 「これね。恒久的にこの姿になるようにさせる。もちろん、ゆっくり徐々にするわ。一度に小さなステップずつ。でも、完成したら、こいつのおっぱいは本物になってるはず。それに、あたしのストラップオンで犯してくださいって、毎晩おねだりしてることになるでしょうね。その時になったら、パーティを開いて、こいつが犯してきた女の子たち全員を集めるの。そして、こいつがどんな人間になったかをしっかり見せてあげるわけ」 「でも、なぜ? なぜ彼を? なぜあなたが?」 「誰かがこいつを懲らしめてあげなくちゃいけないからよ。あたしにはソレができる。それだけの話よ」
 68_Someone feminine 「女性的な人」 私が女性的な人とデートしたいからと言って、その人は女性でなければいけないとはならない。
 68_Roommate 「ルームメイト」 「ううっ……!」とジャッキーは歯を食いしばった。「ああっ、うううっ……」 「こうされて、感じてるんだ。そうだろ?」とティムは、ジャッキーのバージンのアヌスに太いペニスを突き入れながら言った。「お前が感じてるのは分かってるんだよ」 「い、痛いのよ!」とジャッキーは叫んだ。「痛くないって言ったのに!」 だが、苦痛の編み物には幾筋もの快楽も織り込まれていた。そして、ジャッキーは震えるようなヨガリ声が口から漏れてしまうのを防ぐことができなかった。今なら簡単に分かると彼女は思った。ティムとアパートをシェアし、一緒に住むようになって以来、様々なことについてもそうだったが、ティムは正しかったのだと。自分は本物の男性とセックスして感じまくるだろうと彼は言っていた。その通りだったと。 それでも、ティムにぐいぐい出し入れされ、快感と苦痛の混じった叫び声を上げつつも、一瞬だけ、ジャッキーは意識が明瞭になる瞬間があった。そして、一瞬の間に、彼女は、自分がこんな短期間にずいぶん変わってしまったことを改めて思った。彼女がティムと部屋を共有し始めてから、まだ1年半も経っていない。その短期間の間に、彼女は、アニメ好きのオタクの大学生から、美しい女性へと改造されたのだった。目を見張るべきことだった。 ティムとジャックは、最初は、ロームメイトとして、最初のセメスターの間は一緒につるんで遊ぶという、普通の男子学生の友人同士として付き合った。しかし、ティムは、ハロウィーンの時、ジャックがあるコスチュームを試着してるのを見たとき、すべてが変わった。そのコスチュームは、ジャックが冗談として買ったセーラームーンの衣装だった。 次の日、ティムは、衣類店の紙バッグをいくつも抱えて寮の部屋に戻ってきた。そのバッグの中には、様々な種類の女性用衣類が入っていた。ビクトリアズ・シークレットからはランジェリー。フォエバー21( 参考)のようなお店からはドレスやスカートやパンツやトップス。アルタ( 参考)からは化粧品やスキンケア用品。彼はそれをベッドに放り投げ、ジャックに言ったのだった。「もうすでに君の男物の服は全部破棄したぞ。今日から君は女の子になるんだ」と。 もちろんジャッキーは文句を言った。だけど、ティムは聞こうとしなかった。それに、ジャッキーには長期にわたって抵抗する根気もなかった。そして、気がついた時には、ジャッキーは女性化への道を進んでいたのだった。ユーチューブの動画を見て、ジャッキーは化粧、スキンケア、体毛除去を学んだ。……どんなことでも、試してみた。 新しく女性的になり始めたジャッキーは、胸が次第に膨らみ始めたのを知って、ようやく彼女は、この女性化は恒久的なものになるかも知れないと悟ったのだった。明らかに、ティムはこっそりと毎朝ジャッキーが飲むスムージーに女性ホルモンを混ぜていたのだろう。そして、次の1年間の間に、彼女の持つ衣類が変わっていったのと同じように、彼女の体もみるみる変わっていったのだった。 そして今、ティムが自分の中に射精したのを感じ、ジャッキーは、もはや元に戻ることはありえないと悟ったのだった。ジャックに戻ることはないだろう。それに、正直な気持ち、このことはそんなに酷いことなのかと言うと、そうだとははっきり言えない気持ちでもあった。
 68_Relief 「猶予の瞬間」 「やめて……」とあたしは弱々しくつぶやく。「あたし……あたし、こういうこと、したくないの」 そう言いながら脚を大きく広げ、彼にもっと触りやすくしてあげている。彼の指があそこの中を探り回るのを感じると同時に、乳房を優しく揉まれるのも感じる。あたしは、目を閉じたまま、悩ましい声を上げ始める。「でも、どう見ても、こうしてほしがってるんじゃないのか?」 彼の声には笑みが混じっているように聞こえた。 「そ、そんなことない」とあたしは言う。あたしは、指よりもずっと大きなモノを切望なんかしていないならいいのに。あたしは女の子のように見えていないといいのに。あたしには乳房がないといいのに。柔和で女性的な顔をしていないといいのに。そして、こんなに切なく、彼に犯してほしいと思っていなければいいのに。そのいずれの願いも実現しそうもない。事実は、あたしは指より大きなモノを求め、女の子のような姿で、乳房を持ち、顔も女性的。そして最後の願い、彼に抱かれたくないという願いも、本当は、その正反対なのだ。 彼が立ち上がった。あたしは目を開けるまでもなく、彼がベルトを緩めているのを知る。音を聞くまでもなく、ジッパーが降ろされるのを知る。そして、すぐに、彼のズボンが、床に脱ぎ散らかされたあたしの服の上に積み重ねられるだろうということも。そして、頬に彼の熱い息が吹きかけられるのを感じるまでもなく、彼があたしの上に覆いかぶさったことを知る。 「してほしいことがあったら、ちゃんと懇願してほしいな」と彼が囁いた。 「そんなこと、ありません」 かろうじて声に毅然とした印象を持たせることができた。自ら進んで女体化し、それを後悔していない。その事実を前にすれば、ほとんど、抵抗などできない。でも、そんなかすかな抵抗の素振りをしたおかげで、わずかながらも、チカラが湧いてくる。しかし、彼の固いペニスにアヌスの入口をくすぐられるのを感じた瞬間、その最後のチカラも消えていった。 「してほしいの」 と荒い息づかいで答えた。 「それは分かっている。さあ、懇願するんだ」 拒否しようとした。でも、欲望の方がはるかに強かった。抵抗した。それはいつものこと。でも、負けるだろうと分かっている。屈服してしまうと分かっている。これまで何回も繰り返してきたことだから。あたしにはどうしようもできない。 「お願いです。あたしを犯して。アレ、あたしに下さい」 「それじゃあ、充分な懇願とは言えないな。本気で懇願するんだ。本当にアレが欲しいのか? 俺になるほどと思わせるように言うんだ」 「お願い!」 叫んだ。かすれ声になっていた。「あたしをヤッテ!」 これ以上、癒しの瞬間を焦らされ続けたら死んでしまうと思った時、ようやく、彼は言った。「そんなにして欲しいと頼むなら、しかたないな……」 そして彼はあたしの中に力強く入ってきた。そして、ようやく、あたしは死刑執行の猶予を得たような気持ちになる。
 68_Rachel 「レイチェル」 「こ、こんなこと上手くいくはずがないよ。そうだろ?」とボクは、ビキニのトップの肩ひもをいじりながらつぶやいた。「誰もボクは彼女だと信じないと思うよ。それに、たとえ信じたとしても……」 「大丈夫だって」 とキースがボクを遮って言った。彼はじっとボクを見つめた。その彼の目に浮かぶ表情を見て、なおさらボクは居心地が悪くなった。「彼女そっくりだよ」 「着ると落ち着かないんだよ」とボクはビキニの下の方を手にした。小さすぎる。小さすぎる布地に糸みたいな紐がついているだけ。それを公の場所で着るなんて、間違いなく、恥ずかしさの極みだと思った。でも、仕方なく、それに、すべすべ肌の脚を通した。 「平気でいられるようになるんだ。これは大事なことなんだよ、レイチェル」 「その名前で呼ばないで。すごく変だよ」 「でも、これから2ヶ月くらい、君はレイチェルになるんだよ。君も同意しただろ? 君もそうする必要があるんだろ?」 ボクは顔をそむけた。もちろん、キースの言ったことは正しい。彼が最初にこのアイデアを言った時から、ボクには正しいと分かっていた。そして今、姉のビキニを着て彼の前に立ちながら、改めて、正しいと認識しなおす。何も変わっていない。ただ、このアイデアが現実になりかかっているということ以外は。 あたしは腰を降ろし、両手で顔を覆った。「どうして彼女はボクにこんなことをしたんだ?」と呟いた。 気がつくと、キーズが隣に座っていた。逞しい腕をボクの肩に回していた。「彼女が自己中の最低女だからだ。誰より、僕自身がそれを知っている」 彼は正しい。ボクは自分自身の不快感にかまけて、彼の痛みを忘れていた。レイチェルが失踪したことにより、ボクは姉を失ったのだが、キースはフィアンセを失ったのだ。 「あっという間に終わるよ。2ヶ月くらいかけて、君はレイチェルとして人々に知ってもらう。そして結婚式。そして、君の存在は消えてもらう。君が思ってるほど悪いことじゃないよ」 計画は理解していた。それに、ボク自身、不安を感じてはいたけれど、キースが会社から追い出されてしまわないように保証するには、これしか方法がなかった。その会社は、彼がボクの姉と一緒に設立した会社だ。でも、彼のガールフレンドのふりをするというアイデアは、ボクにとってあまり楽しめる考えではなかった。ボクは、どんなにレイチェルに似ていようとも、女ではない。それに、キースがこのアイデアを得てボクに近づいてきた時、ボクは女の子のフリをすることすら、一度も考えたことはなかった。実際、ほんのちょっとお化粧して、高価なウイッグを被り、ちょっとだけ胸に詰め物をしただけで、こんなに自分が変わってしまうのかと、恐怖を感じたほどだった。 「そして、すべてが終わったら、ちゃんと、代償の分をボクに出すんだよ」と、ボクは、ボクがこの計画に乗った理由のことに触れた。「それが約束だったんだからね?」 「ああ、約束だ」と彼は頷いた。「さあ、そこのアレをテープで内側にしまってくれ。それから、お客さんたちを迎える準備に取り掛かろう」 ボクは心の中でうんざりした唸り声をあげた。どうして、ボクをレイチェルとして大々的に紹介するパーティが、プールでのパーティでなければいけないのか、理解できない。だけど、ボクは頷き、小声でつぶやいた。「あたしはレイチェル、あたしはレイチェル、あたしはレイチェル………」と。 パーティが始まる頃までには、ほとんど、ボク自身も自分はレイチェルだと思い込んでいるだろう。
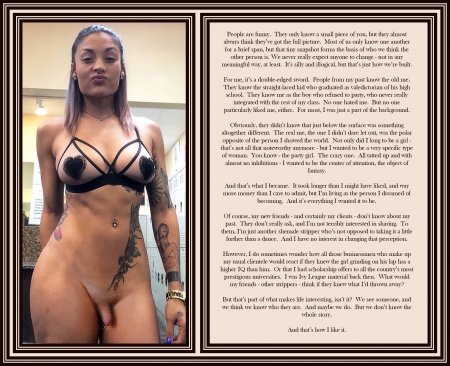 68 Pieces 「断片」 世間の人たちって、笑える。ほとんどみんな、他人の小さな断片しか知らないくせに、全体像を知ってるように思ってる。たいていの人は、他の人のことを短期間しか知っていないはずなのに、そんな小さい断片的なスナップショットで、その人がどんな人間と思うかの根拠にしてしまう。人々がそんな状態から変わるだろうなんて、少なくとも、意味がある形で人々が変わるだろうなんて、あたしたちは真面目にそう思ってはいない。バカで非論理的。だけど、人間はそういうふうにできている。 あたしにとって、このことは両刃の刃。あたしの過去の人たちが知ってるのは、昔のあたし。彼らが知ってるのは、卒業生代表として高校を卒業した真面目な若者。パーティに参加するのを嫌がり、クラスの他の者たちに本当の意味では馴染んではいなかった若者。誰もあたしを毛嫌いしたりしなかったけれど、特にあたしを好きだった人も誰もいない。大半の人たちにとって、私はただの背景の一部にすぎなかった。 はっきり言えることとして、彼らは、その表面のすぐ下に、何かまったく異なるものが隠れていたことを知らなかった。本当のあたし。決して表に出そうとしなかった真のあたし。その本当のあたしは、あたしが世間に見せていた人物の正反対の人物だった。今や、別に特記することでも何でもないことだけど、あたしは女になりたかった。そればかりか、あたしは、非常に特別なタイプの女性になりたいと思っていた。そう、パーティ好きの女の子に。しかも、クレージーなパーティ・ガールに。全身にタトゥーを彫って、全然気にしない女。みんなの注目の的、みんなのイヤラシイ妄想の対象になりたいと思っていた。 そして、あたしはその通りの人間になった。望んでいたより時間がかかったし、使ってもいいと思ったよりもずっとおカネがかかったけれど、でも、今、あたしは、なりたいと夢見ていた人間として生活している。まさにあたしが望んだすべてを叶えて生きている。 もちろん、あたしの新しい友人たちは、あたしの過去について知らない。ましてや、あたしのお客さんたちは、絶対に知らない。と言うか、みんな実際、あたしの過去について訊いたりしないし、あたしも特に話したいとも思っていないのだ。彼らにとって、あたしは、ただのありきたりなシーメールのストリッパーにすぎない。ダンスよりちょっと進んだのことも拒絶しないストリッパー。そして、あたしは、そういう見方をされることを変えるつもりはまったくない。 でも、時々、あたしは、どうだろうと思うことがある。あたしの常連となっているビジネスマンたちが、自分たちの膝の上に乗って股間をグリグリ擦りつけている女の子は、実は、自分たちよりも高いIQを持ってると知ったら、どんな反応をするだろうと。その女の子が、アメリカ中の複数の超有名大学から奨学金を申し込まれた人だと知ったら、どんな反応をするだろう? 当時、あたしはアイビー・リーグに入れる素材だった。今のあたしの友人たち、つまり他のストリッパーたちだけど、彼女たちが、あたしはその申し出を放り投げてきたと知ったら、どう思うだろう? でも、それこそ、人生を興味深くするもののひとつじゃない? あたしたちは誰かを見て、そして、その人はどういう人物か分かったと思い込む。実際、分かるときもあるかもしれない。でも、実際は、その人の全人生まで分かっていはいないものなのだ。あたしを見て、あたしのことが分かった気になる? さあ、どうかしらね。 そして、まさに、そういう点が、あたしは好き。
 68_Permanent 「恒久的」 「おはようございます、ケイト様」 あたしはお辞儀をしながら可愛らしく頬む。そして、体を起こして続けた。「朝食はあと10分ほどでご用意ができます。それまでの間、何かできることはございませんか?」 これが通常の朝の挨拶である。この半年間、毎朝、私はこれを繰り返してきたので、彼女がどう返事するかも知っていた。それでも、ベッドから起き上がる彼女にしっかりと注意を払った。眠りから覚め、目をこすり、そして私に目を向ける彼女。彼女が私の態度を吟味するのを感じる。でも、私はすべて完璧だと分かっている。黒と白の制服は、正確にあるべき姿で整っているはず。 「それ、脱ぎなさい」と彼女は言った。 私はためらわない。「はい、ケイト様」 そして、すぐに背中に手を回し、ドレスのチャックを降ろす。以前は時間がかかったけれど、今はそんなに手間取ることはない。ケイト様のメイドになってから、私は実に多くのことに慣れるようになった。2分ほどで、私の制服は綺麗に畳まれ、彼女のベッドに置かれ、そして、私は裸でその脇に立っていた。 ケイト様はじっと私を見据えた。表情が読み取れなかった。何か調べるような目で見据えられ、私は文字通り体を震わせていた。何か欠点を探しているのだろうか? それとも、単に私の体を目で堪能しているだけなのだろうか? 私には分からなかった。ただ、どちらの場合にせよ、彼女は失望しないだろうと分かる。私は自分の外見に充分すぎるほど手入れすることを学んできたのだから。 どのくらい時間が経ったか、ようやく彼女は反応した。溜息だった。「もう、これには飽きてきたわね。あなた、もうクビ!」 それまで取りすましていた私の仮面が壊れた。「クビ? 私をクビになんて、できるはずがないわ」と呟いた。 「もちろん、できるわよ。でも、心配しないで。あなたは自立するでしょう。あなたのような可愛い子はいつでも仕事を見つけることができるものなの。それに、私も輝かんばかりの推薦状を書いてあげるから」 私は打ちひしがれた。最も予想していなかったこと、それが、彼女が私をクビにすること。状況を見れば、そんなことができる可能性すら考えもしなかった。 「分かりました」 私はがっくり力が抜けて、肩を落とした。計画通り、丸1年続けるところまでは到達できなかった一方、昔の自分の生活に戻る準備をするなど、思ってもいなかった。「お医者様に予約を取ります。そうすれば元の状態に戻れるでしょう。こういうモノも取り除きます。そして……」 「何の話しをしてるの?」 と彼女は私を遮った。 「元の夫と妻の関係に戻ること。ずっと前からそういう計画だったから。つまり、丸1年は続けられなかったけれど……」 彼女は声に出して笑い出し、私は口ごもった。「夫と妻? お願いよ。そんなのありえない」 「じゃ、じゃあ、何の話しを?」 「私があなたを再び男性として見ることができるなんて、本気で思ってるの? このようなことを続けてきて?」 「でも私は男性なのです」 自分の口から間抜けな言葉が出ていると思いつつも、言い張った。「私はあなた様の夫なのです」 「確かにね。確かにかつてはそうだったかも。でも今は? 身分証明書にはイサベラ・ラモスってあるんじゃない? あなたに関係した人たちには、ジャック・レインは『自分探し』にチベットに行ったことになってるわ。2週間もすれば、死体が発見されて、ジャックの死体だと認定されるでしょうね。世の中の人たちにとって、あなたは、ただの違法移民のラテン系メイドにすぎないのよ」 頭の中がぐるぐるしていた。彼女は正しい。彼女は細かな点を見逃すとか、間違いを犯すようなタイプの人間ではない。彼女が私の昔のアイデンティティは消失したと言ったら、間違いなく、そうなっているのである。それを思い、私は大変困った状況になったと知った。 「お願いです。ど、どうか、そんなことはなさらないでください」 「もう決めたことよ。今日かぎりで、ここを出て行きなさい」 「でも、どこに行ったら?」 「そんなこと知らないわね。これはすべてあなたが思いついたこと。覚えているでしょ? あなたはロールプレイが大好きな人だった。まあ、そのロールプレイが恒久的なものだったと考えてみればいいんじゃない? セクシーなメイドとして1年だけ、ということじゃなかったと。そう思ったら、あなたみたいな人にとって、すごくワクワクすることじゃないの? さあ、朝食はどうなったの? あなたは、まだ、もう数時間は時間通りに働かなきゃダメなのよ。そういうふうに振る舞ってほしいわね」 「かしこまりました、ケイト様」 どう反応してよいか分からず、反射的にそう言っていた。私は、そそくさと、散らばった服をかき集め、仕事へと戻った。
 68_Nymphs 「ニンフたち」 その島には何か変なところがあった。 だが、私たちはもう何ヶ月もこの島に取り残されていて、流れる月日について意識的に考えることでもしなければ、月日はただの日々として流れていくだけのように思えた。時が経つにつれて、この島は自分たちが住むべき故郷のように感じられ、たとえ救助隊が来たとしても、ここを離れたいと思わなくなるのではないかと恐れた。ハリーも同じ感じでいると思う。いや、彼女の方はすでに、その一線を越えてしまっているかもしれない。彼女はこの島が大好きになっているように見える。 でも、それを言うなら、ボクも同じだろう。風が魔法の不吉な唸り声をあげてる時ですら、ボクはそれまで経験したことのないような快適さを感じた。ボクたちは、ボクも彼女も変わってしまったし、もし、何かのおかげで鏡が出てきて、それを見たら、ふたりともほとんどそっくりになっているのを発見するだろう。それは分かっていた。でも、ボクはその事実を困ったことだとは感じていない。ハリーもそうだ。それは、この島での生活の一部にすぎないから。 ボクたちふたりの服は、ここに来た最初の日になくなってしまった。でも、それで困ったという感覚は数分しか続かず、すぐに、ふたりとも素っ裸でいても何の問題もないことに気づいた。ふたりの顔が変わったときも同じだったし、体が変わったときも同じ。島に来る前は、ハリーは明るいブロンド髪をして、背が高く、彫像のような見事な体つきをしていた。一方、ボクの方は男の中でもガッチリとして荒くれタイプで、ひげを生やし、体毛が多く、喧嘩慣れしてる男の顔をしていた。そして、この島にいてしばらく経つと、ふたりとも変身していったのだった。でも、ボクも彼女も新しい肉体を嬉しく思っていた。この島がボクたちに望む姿かたちに、ボクも彼女も満足していた。 でも、何かが変わっていった。ふたりともそれを感じていた。この島のどこにいても聞こえる、あの魔法の唸り音は、次第に大きくなり、やがて、耳をつんざくほどの轟音になっていった。ふたりとも音を気にしないように努めたけれど、あまりに大きな音なので、頭の中でガンガン鳴り響いてるほどに思われた。 そして、ある日、急に音がやんだのだった。ボクはうれし涙を流した。 突然、背の高い、普通の人間とは思えない人物がビーチに現れた。彼はスポーツマンのような体つきをしていた。全身、引き締まった筋肉で、手足は非常に長く、生まれながらのハンターを思わせる動物的な、余裕に満ちた優雅さを持ち合わせていた。顎はきれいにひげを剃られていたが、角ばっていて、黒髪が両耳を覆うように伸びていた。彼も裸で、ボクには彼の男性器と比べたら、明らかに、自分のそれは小人のそれにしか見えないだろう。 「おお、私の美しいペットたちよ。とうとうお前たちに会えて、私は嬉しい」 「あ、あなたは誰?」とハリーがやっとのことで声に出した。でも、ボクには彼女がどうして声を出せたのか分からない。恐ろしくて声が出せなかったから。この男性が……彼が人間であるならの話だが……彼がオーラのごとく発しているパワーに、ボクは恐れおののき、声が出なかった。 「そのうち分かる。だが、さしあたり、お前たちが何者かの方が、はるかに重要だろう。お前たちはニンフになったのだ。変身させられたばかりのニンフ。そして今日からは、お前たちは私の快楽のために奉仕するのだ」 それは事実だった。彼がその言葉を発した瞬間、ボクには理解できた。彼はボクたちのご主人様になるべき人で、ボクは彼のあらゆる命令に喜んで従うことになるだろうと思った。不服従など考えることすらできなかった。 「さあ、来なさい。島の中央に連れて行こう。そこでお前たちは、新しい姉妹たちと会うのだ」
 68_Not enough 「まだ足りない」 タミーが言った。「認めざるを得ないわね。ずいぶん進んだわね。正直、これが可能だなんて思っていなかったの。でも、あなたは、日に日に女の子らしくなっていくわ」 リッキーは褒められてにっこりとした。「それって……」 タミーは頭を左右に振った。「でも、まだ、そこまでは行っていないわ。あなたには早くそこまで行ってほしいけど、まだ達していないの。ごめんね」 それを聞いてリッキーはがっくり来るのを感じた。「でも、キミ自身で言ったじゃない?」としどろもどろになりながら言った。「言ったよ……ボクは女の子らしく見えるって。ぼ、ボクは……キミのためにこれを頑張って来たんだよ」 「別に、あたしは頼んだことは一度もなかったけど? あなたが自分で決めたことじゃない?」 リッキーはどう反応してよいか分からなかった。彼は、タミーと結ばれるチャンスを求めて、自分の全人生を、もっと言えば自分のアイデンティティのすべてを捧げてきたのだった。リッキーはタミーを愛していた。そして、彼女の方も、男性には惹かれない事実にも関わらず、彼を彼女なりに愛していた。リッキーは、自分が女の子の姿になれば、どういう姿か分からないけれど、なんとか女の子っぽくなれたならば、彼女と一緒になれると、そう思ってきたのである。 「分かってる」とリッキーは腰を降ろした。もうこんなに姿が変わってしまったが、それでも、まだ足りないのだ。そもそも、完璧になれることがあるのだろうか? ようやく、リッキーは顔を上げた。「手術を受けてもいいよ。豊胸手術。ヒップへのインプラント。キミが望むなら何でも。ボクは……ボクは、キミが望む人になりたいんだ」 「そう言うと思った」とタミーはカウチの上、彼の隣に座った。「でも、それが可能かどうか分からないわ。同じことを1年前にも言ったはず。手術とかって、あなたにできるかどうか、あたしには分からないの」 「きっとするよ。ボクはキミが望むような女の子になる。どんなことをしてでも」 「ならば、あたしは何も決めつけずにいることにするわ。でも、何も保証はできないの。それは分かってるでしょ? あなたを愛している。本当よ。でも、あたしは自分のセクシュアリティを変えることはできないの。自分を変えることはできないの」 「ボクはできるよ」とリッキーは力説した。「きっとそうする。キミのために」
 68_Mother's Day 「母の日」 手を離れたバッグが、音を立てて床に落ち、中身がタイルの床に散らばった。私は、母の姿を見ながら、口をあんぐり開けたまま。言葉が喉に詰まって出てこない。声が出ない。何も考えられない。それに、私の目の前にいる人のことを信じられないでいた。 「多分、ちょっと説明っぽいことをしなくちゃいけないわよね」と、浴室の真ん中に立つ母が言った。母の好きなローブがいつものフックに掛かっているけど、手にしようとはしなかった。むしろ、意図的に堂々と裸で立っている感じだった。彼女の脚の間にある、本当ならあるはずのないモノについて、何か言いなさいよと挑みかかっているようにすら見えた。 「あ、あたし……何が何だか分からないわ」 ようやく言葉を出せた。 「そうよね。分からないと思う。あなたが悪いわけじゃないのよ。ママはずっとずっと前にあなたに話しておくべきだったの」 ようやく、ありがたいことに、母は手を伸ばしてローブを掴んでくれた。それを肩にはおり、前を閉じた。「ちょっと長い話になるけど、いい?」 「え、いいわよ」 とあたしはつぶやいた。 母はあたしの横を通り過ぎ、廊下へ出て、リビングへと進み、そこのソファに腰を降ろした。あたしは頭の中が麻痺したまま、母の後についてリビングへ入った。目にしたモノの意味を理解しようとしながら。理解できなかったけれど。 あたしが腰を降ろすと、母は話し始めた。「始まりは、あなたが生まれた時だと思う。私は……」 「あなたは、本当にあたしのお母さんなの?」 母の話しを途中で遮り、あたしは叫んだ。 「どういうこと? もちろん、私はあなたの母親よ」 「あたしを育てたという意味じゃなくて。そうじゃなくて、あたしはあなたのDNAを持っているのかという意味で。あたしのことを9ヶ月間、お腹の中に入れていたかという意味で。あなたがあたしを出産したのかという意味で。それを教えて」 「テレサ、複雑なのよ」と母は眉のあたりを曇らせた。「私は一度も……どう説明してよいか分からない。鏡の前で何千回も練習してきたことなのに。どう言うか知っていたはずなのに。なのに、今は、どう言ってもふさわしくないようにしか思えない」 そう言って、母は両手で顔を覆った。「ああ、どうしてもっと早くあなたに言わなかったんだろう。そうしてたら、ずっと簡単だったのに」 「お願い、話して」とあたしはなだめるような声で言った。 母は溜息をつき、体を起こした。目に涙を浮かべていたし、両頬が濡れているのが見えた。「私はあなたの父親なの。生物的な意味で言って」 「でも、お母さんは父は死んだって言ってたんじゃ……」 「ウソだったの。というか半分ウソだったかも、分からないけど。あなたの本当のお母さんが家を出た時……それは私のせいだったんだけど……その時、あなたのお母さんはあなたを私のところに置いて出て行ったの。私は彼女を探したわ。でも見つけられなかった。まだ彼女が生きてるかすら分からない」 そう言って母は再び溜息をついた。考えをまとめている様子だった。あたしは何か言いたかったけれど、何を言ってよいか分からなかった。だから、母が泣いている間、あたしはじっと黙っていた。 ようやく母は顔を上げ、啜り上げながら言った。「私はトランスジェンダーだったけど、あなたのお母さんはそれに対処することができなかったの。当時は、社会は今ほど許容的じゃなかったから。私はバレることがとても怖くて、こっそり女装して、隠し続けた。でも、あなたのお母さんに見つかったの。そして彼女は家を出た。私にひどいことを……いろんなことを言われた。私の友だちみんなにも全部バラした。私の親にも兄弟にも。私は故郷を離れる他に道はなかったわ。ああいうことが周囲に渦巻いている環境であなたを育てるのはイヤだったから」 母は立ち上がり、壁に顔を向けて立った。「でもね、それは、次の段階に進むために必要なことだったの。だから、悪いことばっかりだったとは思わないわ。それに、あなたには母親が必要だった。女の子は誰でもそう。母親が必要なの。だから私は変身した。女性化が完了したころまでには、私たちは新しい町に住んで、新しい生活を始めていた。そして、私は、あなたに幻想を崩さないでいて欲しくて、本当のことを話さなかった。あなたから母親を奪いたくなかったの」 母はあたしの方に向き直った。「私を許してくれる? あなたをずっとだまし続けてきたから、あたしを恨んで当然だと思う。でも、すべてあなたのためを思ってのことだったのよ。私は……私はあなたに、あなたの父親が……父親が変人だなんて思ってほしくなかったの」 あたし自身の頬も涙で濡れていた。母が歩んできた人生のことを思い、涙が止まらなかった。そして、ようやく、あたしは返事した。「あなたはあたしの父じゃない」 「何て……?」 「あなたはあたしのお母さん。ずっと前からそうだったし、それはどんなことがあっても変わらない。お母さんが以前どんな人だったかは関係ない。お母さんの脚の間に何があるかなんて、関係ない。あなたはいつもお母さんとしてあたしのそばにいてくれたし、これからもずっとそうしてくれるはず。ママ、ママのこと大好き。母の日、おめでとう」
| HOME |
次ページ≫
|
